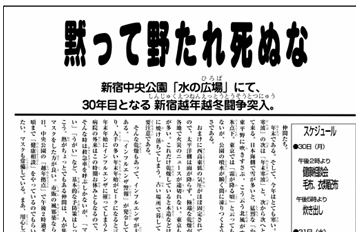24-25年の冬も、おおかた終わった。
教会系支援が厚いクリスマスの時期が過ぎ、年末年始 は炊出し三昧で公園で過ごし、それが終われば大寒波の中、手足を凍らせながら街を歩き、西口地下広場火災の 献花式も終わり、そうこうする内に梅も咲き、東京マラ ソンも終われば春の足音を聞き、寒の戻りで都心でも雪 が降ったものの、そうこうする内に早咲きの桜も咲きはじめ、そして、もうすぐ花見の季節である。
何もなかった冬が良かったのであるが、やはり、新宿の冬はそうとも行かず、正月の都庁下放火事件、そして 大ガードでの仲間の凍死など、やはり冬は一筋縄にはいかない。
春は願ってもいない季節である。命に関わる心配事が少なくなる。たったそれだけで、楽にはなる。
新宿区内の公園には、そこで定住するテント生活者は1人も居らず、都庁の下や駅周辺に、定住、半定住のダンボールハウスが点在する程度。残りは流動型、昼間はどこかに居て(仕事だったり、炊出し巡りであったり、 休息だったり)、夜になるとやって来て、隠しておいた 段ボールや寝袋を表に出し、そこで睡眠を取る仲間が、もはや多数派である。こちらは新宿駅西口を中心に、夜の街の中に同化している。新宿駅は小田急本店の建替え 工事の真っ最中で寝場所もかなり制約されてしまったが、それでも少しでも暖かい場所、少しでも静かな場所、出来るだけ実入りになる場所を、それぞれ見つけている。
この冬の夜間、新宿では160名程度の仲間が確認されている。終電逃してと云う一般の人は居ない。冬場、駅で寝ている人々は、駅や路上で寝ざるを得ない状況となった本当のホームレスと云うことになる。
これが「実態」であるが、この「実態」は、時間帯が時間帯だけにあまり多くは知られていない。
他方、色々な団体が公園や広場や通路でやっている 「炊出し」や「物品配布」に集まる者の半数(下手をすれば半数以上)は、今は路上暮らしをしていない、生活保護を受給している人などでもある。この「実態」は支援の側に立つ者の中では、もはや常識レベルであるが、 世間一般では、こちらもあまり知られていない。
今は、それらの人々も含めて「生活困窮者」であると、便利な言葉が出来たが、これら「ホームレスの炊出し」に集まる、「非ホームレス」の人々は「生活困窮者」の中のごくごく一部でしかない。
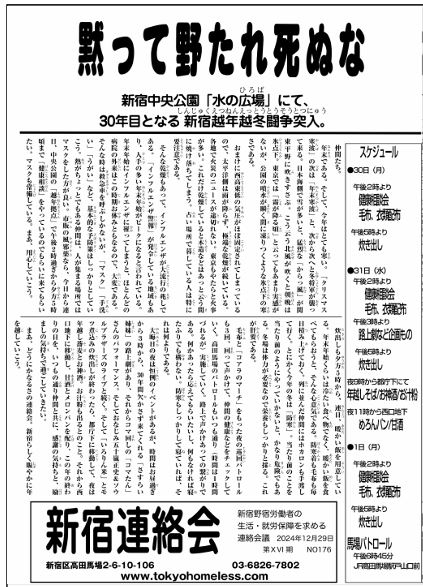
実はここら辺の人に厄介な人々が居て、誰かに見られてやいないかと、恥を忍んで炊出しに並ぶならまだしも、それが当然かの如く、得たものを転売するであるとか、何回も並んで、要らなくなったものはそこらに捨ててしまうような人も居る。足りているからそうするので あり、これらのほとんどは、「無料パス」で都内を動きまわり、もはや「職業人化」しているようでもある。路上や公園での「支援」は、そう云う、思いもよらない新 たな人々も生み出してしまった。
もちろん当事者の責を云々などしたくはないし、場から締め出すことは簡単であるが、よほどのことがない限り。そこまではしたくない。
そう云う、そうせざるを得ない人々を多く作り出した責任は、支援の側にもある。
「分断」なんてのは既に出来ている。「何で国から金もらっている奴らが、ここに並ぶんだい」「おかげで、こちとら必要なものが貰えないじゃないか」と云う声はしょっちゅうで、「本当に必要な人々に必要な量だけ渡す」と云う「理想」通りにやることは、とても難しい。
巡回、アウトリーチ、宅配型を中心にした方がよほど確実であるが、それでも結局、どこかで情報聞きつけ、いつの間にか並び始める。
何年やっていようが、結局は同じ問題に悩まされ続けている。誰が、何を、どうして必要とされているのか? そこを見極めるのは至難の業である。
それはともかく、新宿駅周辺のこの160名前後の、現に路上生活者を余儀なくされている仲間の数をどう考えるかは、そこそこ重要な視点であるかも知れない。
この数はコロナの前と比べても、この10年、そうたいして変わらない。調査方法や時間帯にもよるが、だいたい150から200名の間で推移している。そして、実際に歩いて回っている現場の支援者や、新宿福祉事務所や道路管理者などが把握しているこの数は、都市雑業や収入へのアクセスが多少変わったとしても、都市開発の関係で寝場所が制限されたりしても、オリンピックな どイベントの関係で一時的な退去を求められても、その 都度、調べ直しても、あまり変わらない。多少探すのが難しくなる程度で、新宿を知る人の目からすれば、すぐに「捕捉」される。
対策や制度を知らないことはない。連絡会の(「紙の爆弾」=)「チラシ」は30年間、支援の情報を載せ毎週新宿の隅々まで届けられている。最近は新宿福祉事務所も独自の「チラシ」を作り、その配布も盛んになった。
医療単給で病院に行ったり、相談所「とまりぎ」を利用したりと、役所を嫌っているわけでもない。低いレベルで生活が成り立ってしまっている中、困っていることは「お金がないこと」ぐらいで、あとは集団生活の中、それぞれの関係性の中で、生活が出来上がっている。そんな中、幾ら生活保護を取ってあげるよと「あめ玉」ぶらさげても、そこになびく人は、今は少ないし、また、「権利」「権利」と云う世代でもなく、何か大きなきっ かけがない限り、生活を変えようとはしない人々の層が、これだけ居るのが「実態」かも知れない。
その生活のレベルはともかく、一定程度、その生活が安定してしまうと、保守的となるのは、これは仕方がな い。何かの「きっかけ」がなければ、変わることはない。人の入れ替えはあるのであるが、結局は同じような 人々を補給し続け、同じような数字となる。
新宿ならではなのか、摩訶不思議な数字でもある。
ホームレスを取り巻く環境や、対策もまた、時代に合わせ変遷している。
かつては、「役所の世話にはなりたくない」と云う失業したばかりの労働者としての自尊心から来る、福祉へ 拒絶が多く、それならば後腐れのない支援と云うことで、「自立支援センター」や「地域生活移行支援事業」での低家賃住居の提供となり、これらにより都立公園で 起居するテントの仲間はとても少なくなった。
ここまでは、バブル崩壊後の「ホームレス」現象が社会を驚かせ、路上からのたたかいが生まれ、やがて具体的な要望となり、当事者が様々な施策を勝ち取って来た前期の頃。
その後、リーマンショックの不況と、製造業での「派遣切り」で、派遣労働者などの失職若年層が路上に至り そうになり、政権交代などもあり、為政者は生活保護の申請基準を意識的に下げ、路上に至らないようし、生活保護制度、自立支援制度をフル活用、おまけに「生活困窮者自立支援法」をこしらえ、これら若者の失職が社会問題に転じることを、どうにか乗り切った(路上生活者の若年化と云うのは、本当は、あまりなかったのであるが…)。
ここら辺から路上を直接見ようとする視点よりも、「生活困窮」全体を捉えようとする鷹の目視点となり、福祉行政が政治的な手段となったが、おかげで、状態に応じた、ある程度きめ細かな施策(セーフティネット)が全国ででき上がった。
選択肢が多くなるのは良いことでもあり、路上の人々も積極的に生活保護を受給するようになったが、何でも、誰でも生活保護をかけ、どうにかしてくれと云う世論の中、それが「乱発」されると、「不正受給」の問題やら、「貧困ビジネス」の問題やら、「生活保護手配師」の誕生やら、制度の歪みが多く出て来た中期の時期でもある。
門戸を広げればそこに人が殺到する。そうなると様々な課題があがってしまうのは仕方がないが。生活保護の「魅力」もまた、こう云うことがあると減退もする。
そして、「コロナ渦」を挟みながら、現在、これらの施策を知っていながら、路上に暮らし、そこで都市雑業などで自らの生活が成り立ってしまっている人々の層が残る。そこら辺の人々はこれまでも居たのであるが、他の人々が路上から去ると、残った者が主流となる。
けれど、そう云う自立心や独自のコミュニティをもった人々も年を取る。そして長年の路上暮らしは健康を著しく害する。そして、彼、彼女らにとって安定した生活と云うのは、何かがあればその関係が崩れたり、居場所の移動を強いられたりと、不安定でもある。今は良くても、「きっかけ」はいくらでも出てくるので、支援の側はそれを根気強く待っているしかない。
今や必要なのは「対策」「施策」ではない。それは既に揃っている。肝心なのはそこにつなげる努力と忍耐の問題である。
近年の都の概数調査(こちらは定住層の昼間の数)で減ったのは、「自然減」。つまりテントから救急に運ばれたり、そこで亡くなったり、そんな数としか思えない。「長期・高齢化」の先は、まあ、そう云うことになる。「認知症」のようになって、街を彷徨う仲間も居る。「住所不定」状態でサービスも受けられない。まずは生活保護を受給して、どこかに住んで、住民登録をして、通院して病名をもらい、等級をもらい、初めて介護サービスなども使える。しかも、そもそもご本人が病気であると自覚をしていなければ、そうもいかない。
食べるものは食べられる。餓死はないが、着るものがなかったり、飲んで寝たりすると凍死はある。
そんな「不幸」な老後を極力避けたいのが人情でもあるが、理念や理想通りに動くことは少ない。そうやって数も減っていくが、それはドラステックにではなく、 徐々にである。
…………
前号にも書いたが、「水銀」「鉛」などの有害物質が 検出され、公園の半分が閉鎖されている都立戸山公園、その後も(大して予算がつかないのか)そのままである。
ここにも今はテントは一軒もなく、定住者も先日の追い出しのため、居なくなった。
西戸山公園とあわせて、この一帯、朝ともなれば、建設関連の手配師が多く集まり、それに合わせて日雇や飯場仕事を求める労働者が集まる西の「寄せ場」の一角であった。今はビルに変わってしまったが、山手線の線路の向こうの西戸山公園側には日雇職安もあり、アブレ手当てを貰いに、その日、職にありつけなかった労働者が昼前まで集まり、賑わっていた界隈である。今もある都営団地などは、戦後の混乱のなごり。その頃から携帯電話やネットやらが発達した90年代ぐらいまでは、仕事探 は「相対」で、東の筆頭格でもある「山谷」などの 「寄せ場」が日雇職安を中心に、あちこちにあった。それもバブル崩壊と共に建設仕事が少なくなり、日雇仕事も縮小。この国の高度成長期に「出稼ぎ」などで都会に出、飯場を転々としたり、簡易旅館に泊まりながら仕事を求めたりする労働者の群れは、やがて「宿なし」になり、「野宿労働者化」「ホームレス化」することになった。そして、その多くは50代以上の年齢層で、病気などにより仕事も思いように出来ず、年々、そんな人々は制度の側に吸収され、公園や街頭から消えて行った。
そんな象徴でもある地の戸山公園にも、かつては100を越えるテントがあり、そこを拠点におのおのが生活をして居た。建設日雇いの求人が「派遣型」となり、かつ若年層を優先して雇用するようになり、かつての人々が集う「寄せ場」もその機能が失われると、テントに残った人々は古本回収やアルミ缶回収など都市雑業に従事しながら、その場で生きることを選択した。
「寄せ場」や都市雑業は、とにかく朝が早い。日が暮れる頃には、横になり、寝に入る人々も多い。
そんなこともあって私たちの高田馬場のパトロール(巡回)の時間は30年前から午後6時代となっている。それより遅いと皆、寝てしまい、話も聞けないからである。

それから状況が変わっているにもかかわらず、何故か同じ時間で回っていた。仕事をして帰りがけにそのまま巡回できると云う利便もあった。が、そうすると、出会える仲間の数は次第に10名を切り、皆、高齢で無年金のため、生活保護などを勧める内に、その内に2名とか3名とか、そんなになってしまった。
何か違うなと思い立ち、深夜帯に回れる支援者に仕事の帰り道、回ってもらうと、横になるだけであるが、一段と狭くなったこの公園の片隅に、冬場にも関わらず10名程の仲間がコンスタントに寝ていることが判明した。もちろんチラシでの情報提供、非常食を渡し、起きていれば声をかけてもらっている。皆、どのように暮しているのか、都市雑業系のように思われる。また、場所柄、アジア系外国人の仲間も居たりする。駅の方では正体不明(?)の方が、こちらは居たり居なかったり、声をかけても無視されるので、とりあえず心配しているよのサインは送り続けている。
こんなのも、この冬の新たな「発見」。
地道にやっていると、何かが見つかる。
…………
『野宿すら出来ない都市は本当の都市ではない。そう思うようになったのは、新宿駅西口地下の火災事故の後、やみくもに東京の街を歩き始めた頃である。土地の光景には歴史の流れや思想が凝縮されている。もう一度、山谷や新宿などという固有の土地から離れ、この東京という大都市を客観的に見ようと思ったからである。
もちろん都市には大金持ちや成り金がいたっていい。大金持ちが高台に豪邸を建てても文句は言わない。金持ちが遊べる場所があっても良い。しかし、それと同じように、都市には貧しい人々がいても良いのである(無論、貧しいと言っても限度はあるが)。そういう場所がこの都市には著しく少なくなった。そして、だからこそ 木造アパート街や河川敷の仮小屋や場末の汚らしい歓楽街などが新鮮に見えた。もちろん、そんな場所は山谷などにはいくらでもある。しかし、そればかりを見ていると対比が出来なくなってしまうのである。この都市がどうなっているのか、「寄せ場」から世界が見えるかと言えば、見えているようで実は見えていなかったりもするものである。ひとつの場所にいる限り見落としが多いのである。
この都市の中に野宿者がいる。雑業者がいる。そうあってはならないと、多くの識者は原理原則を掲げていうが、この世に「不幸」がある限り、さまざまな「不幸」の形態はあってしかるべきだと考える。良いか悪いかなんて言う評価は後から付けるものである。肝心なのはその「不幸」を社会の「不幸」と感じられるかどうかだけである。人の営みは肯定する所からしか始まらないと思う。それがあらゆる関係性の始まりである。この社会が路上で暮らす人々を排除してきた歴史を持つ以上、そうあってならないと諭すことなど誰が出来ようか?徹底的に肯定した上で、その中からの不足を明らかにしていく作業以外の方法を私は知らない。酒飲みのおっちゃんに 酒を止めろと諭すより、一緒に酒飲みながら話し合う。そういう事からしか始まらないのではないのかと考えるのである。屋根があったって、路上で寝たい時はあるさ。仲間が欲しい時もあるさ。それをどうしろ、こうしろなんて言われた日にゃ世も末だ!』(「新しくもあり、古くもある下層」日本寄せ場学会年報「寄せ場」13 号 2000年5月13日発行より)
これを書いたのは今から25年前、西口地下広場火災の後、そして「ホームレス自立支援法」が制定される2年前。
連絡会30周年と云うことで、古い資料を読み漁っていた昨年、段ボール箱の奥底に残っていた資料の中にあった。
当時、勢いに任せて書いたものであるが、自分で自分の言葉に納得したりして、熟読した。まあ、変わっていないものは、今も変わっていない。
路上生活の問題を「不幸」の形態としてざっくり考えているのは、横山源之助の影響である。横山も書いている「いかなる時代いかなる社会においても、貧民なきはあらじ。」「…しかしてその貧民と成りたる因由を探れば、あるいは一家の所得に比較して家族多く、生活の不如意なる者あり、親を失ひ夫を失ひたるがために、貧民の群に落ちたるもあり、あるいは身体の不具なるがために貧民たるものもあり、もしくは酒食の為に貧民となるものもあり、しかしながら其の多くは偶然の事情のために不幸を来たし負債生じ不義理生じ、終(つい)に貧民の境遇より身を脱するを得ざるは最も多し。…要するに日本の貧民は人生の不幸者のみ。」(明治31年「日本の下層社会」岩波文庫版より)。
現状を人々の規範から批判することより、また、その「不幸」をやたらと強調し、お涙頂戴のお話を作るより、その現実をまずは認め、そこへ分け入り、その当事者と共に、その改善を科学的に考える。
横山が現実を知れば知るほど、「悲惨さ」を強調するありきたりのルポルタージュや、言葉面だけの文明批判とは違い、同情すればする程、その、「解決」「改善」を考え、そして、「教育の拡大」「融通機関の設置」を提起し、「労働運動」に希望を託したよう、私たちも現実を知れば知るほど、そしてそこにずっぽりとはまればはまるほど、「追い出し反対」だけではなく、「路上からの提言」のよう当事者の開発と多角的な施策実現を要望し、またNPOを作り自らの力で実践したよう、どこかベクトルが似ているし、恐れ多いが、とても親近感がある。
横山が新聞記者として全国を歩きまわり、木賃宿にとまり、現場に入り調査をし、そしてこれを記し、その都 度記事にし、そしてそれをまとめ出版したのが、何と28歳の時。欧米列強に負けじとこの国が資本主義化、列強化する中、病弱な明治の青年が、「上」へ「上」へと行くのではなく、社会の在り方に矛盾を感じ、社会の「底」へ「底」へと進み、その「解決」を模索する姿 は、とても感銘深いものでもある。
どんな時代にも、風変わりで、臍曲りな人は居たのである。
経済だけの問題のみならず、この世の「不幸」と多角 的な要因を社会問題の基本に置き、社会の改革、下層労 働者の地位向上を模索し続けた横山の切り口は、その後の社会施策や社会福祉、また科学的調査や社会学にも影 響を及ぼしたのは周知の通り。そして、路上生活者対策 の切り口が「複合的な問題」「総合的な対策」とされるなど、その流れは今日まで受け継がれている。
何せ「社会福祉の先覚」の偉人である。127年ほど前となるが、この長い間、社会は同じ問題を常に抱え、それが問題だと、繰り返し、繰り返し、語り、そして、社会は、同じようなことを、その都度施策化しながら、試行錯誤して来たのである。
貧しさの問題や、「不幸」の問題は、そうそうたやすく「解決」するようなものではないし、それは見えやすくなったり、見えにくくなったり、新たな問題になってみたりで、なくなりはしない。
その歴史を知らず、これらの問題に性急な態度を取ると物事はややこしくなる。
ちなみに、横山源之助は、最底辺で暮す「細民」「浮浪者」を、「イクジナシ」であると、面白い規定をしている。「イクジナシ」とは、「気力」がない状態を表わすのであろうが、底辺の生活を知れば知るほど、もどかしい気持ちが芽生え、語れば語るほど、「何とかしろよ」となるのは、とても良く分かる。それを知らずに同情だけすれば「救済」一辺倒となるのであるが、生きる 「気力」を呼び戻すことも考えねばならぬ。「支援」の手法は、そう云うところから来ているのかも知れない。
「支援」なんてのは断っても良い。支援する側はそんなものだと思っているし、押し付けはしない。所詮サポ ートでしかなく、決めるのは「あなた」であることを良く知っている。
横山は「救済」中心の慈善家ではないし、体制やら制度やらで上から解決しようとした人でもない。そうではなく「労働運動」の側に飛び込んだ(若き日の片山潜 〈セツルメント運動の先駆者、後に共産主義者となりソ連邦で客死〉や高野房太郎〈労働運動、労働組合や消費組合の父〉、幸徳秋水〈後にアナキズムに傾斜、大逆事件で刑死〉らと一時歩みを共にした)人である。
「労働運動」は労働者の自主的な運動である。すなわち、自分達のことは自分達で決め、そのためにたたかおうと云う立場であった。「社会のゴミ」と言われたら、「俺たちはゴミじゃない」と叫ぼう、訴えよう、そうやって生きる「気力」を、「反逆の思い」を呼び戻そうとする立場である。
「評伝」(「評伝 横山源之助ー底辺社会・文学・労 働運動」立花雄一著)によれば、横山は福井の漁村で網元の下女の子として生まれ、私生児故に、魚津の左官職人の養子となり、育てられたとのこと。生涯に亘る下層の人々への共感は、そんな「不幸」な生い立ちからも来ているのであろうか。
身体が弱かったようで、学業の道に進み、その後弁護士を夢見て上京するも、挫折を味わい、それでも、二葉亭四迷など文士との交遊を重ね、社会の矛盾をより多く知り、記者の名で各地を放浪、調査を重ね、記事を書き、それをまとめ、再調査もしながら、「日本の下層社会」「内地雑居後の日本」を続けて出版した。その後新聞社を辞めてから労働運動にのめりこみ、都市下層調査 も何度も何度も行い、記事を書き続けた。そして、労働運動が壊滅させられると、今度は移民問題(当時の移民政策は貧困の打開のための、今で云う自立支援のようなもの)に興味を持ち、ブラジルにまで調査に出かけた。
魚津の実家も落ちぶれ、家族が上京し、その生活も面倒見なければならないなど経済的にも不遇だったようで、そして、調査の日々と文筆の日々の過労によるのだろう、病に倒れ、小石川の6畳一間の間借り部屋で結核で知人に看取られ亡くなった(享年45歳)。
作家樋口一葉の晩年(彼女も若死で享年24歳、同じく結核で亡くなる)、菊坂の家に出入りし、親交を共にしていたと云うのも驚きであるが、貧しさの問題や、差別の問題、制度の問題、また、その中の人々の暮らし、そして喜怒哀楽。自ら体験し、自ら飛び込み、そして議論し合い、批評や文学にして表現してきた人々の熱意は、今もどこかで読み継がれている。
そんな先駆者達に思いを馳せてみるのも、また楽し。
…………
脱線しまくりであるが、まあ、そんなこんなで、冬は終わった。
私たちの「救済」一辺倒ではなく「支援」「共助」の活動は、今も昔も複雑な世の中、同情だけではなく、何があっても仲間と共に生き抜こうとしている下層の人々への共感から始まっている。
そんなことを、何度でも、何度でも確認するのも冬の仕事。
何も難しいことはない。
「不遇」だとしても、「不幸」だとしても、今を諦めず、どんな暮らしでも、そこで力強く生きる。
一人で生きていけない時は二人で生きていこう。二人 で生きていけない時は三人で生きていこう。三人で行きていけない時は、仲間と生きていこう。
ただ、それだけである。
色々と考えさせられることが多い新宿の冬であった。
(了)
初出:「新宿連絡会(野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議)NEWS VOL92」より許可を得て転載 http://www.tokyohomeless.com/
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔eye5924:250327〕