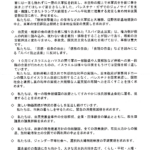2月6日はちょうど13年前(1999年)にパリ郊外のランブイエ城でSRJ=新ユーゴスラヴィア(セルビアとモンテネグロから成る連邦国家)のコソヴォ危機解決のために国際会議が開始された日である。それは1999年2月23日ま
本文を読む岩田昌征の執筆一覧
旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(9)
著者: 岩田昌征22 弾丸ははずれた モニカ・グラスがヤンコヴィチの助力でつくったドイツ・テレビのルポルタージュは世界に大きな反響を呼んだ。私のまわりに危険な網がはりめぐらされていると言う最初の警告であった。 1993年7月 ドゥシ
本文を読む旧ユーゴスラビィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(8)
著者: 岩田昌征19.再び「NIPPON」へ コザラツ地区で発生した戦斗を家族と共に滞在していたバニャルカでテレビ・ニュースで観ていた。戦斗終了後数日たって、私は弟(or兄:岩田)リュウボとコザラツへ行き、家族の土地財産をみてまわっ
本文を読む旧ユーゴスラビィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(6)
著者: 岩田昌征13.二つの塹壕 バニャルカの公安部長ストヤン・ジゥプリャニンは将来のセルビア人共和国領内のすべての警察署を完全に統制しようとはかった。警察勤務員全員に民族を問わずセルビア人権力への忠誠署名と新しいセルビア人共和国の
本文を読む旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(5)
著者: 岩田昌征11、疎開 マイキチがハンドルをにぎった。私は、ムスリム人見張番がコントロールしている地域を安全に通り抜ける道を探す役目だった。教会の中庭を出る直前、SDAのムスリム人活動家がやじった、「タディチよ、私達が一番つら
本文を読む軍事クーデター⇒秩序⇒最小限流血か、民主化⇒内戦⇒最大限流血か、筋道のディレンマ
著者: 岩田昌征〈解説〉 2011年12月25日と26日の『ポリティカ』紙(ベオグラードの日刊紙)に社会主義ユーゴスラヴィア時代のユーゴスラヴィア人民軍(JNA、連邦軍)の最高幹部の一人、ブランコ・マムラ提督のインタビューが載ってい
本文を読む旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(4)
著者: 岩田昌征8.セルビア人共和国の土台 コザラツの町の中心に「聖ペタルと聖パヴレ」セルビア正教会があった。すなわち、プレェドル・オプシティナの最もラディカルなムスリムス人地区の真中に存在していた。しかし、長年、そこで行われて来
本文を読む旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(3)
著者: 岩田昌征旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(2) https://chikyuza.net/archives/17644より続く (以下訳者=岩田コメント) この文章には紛争当事者達が実名で描かれている
本文を読む旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(2)
著者: 岩田昌征旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(1) https://chikyuza.net/archives/17391より続く 4,戦争へ 省略 5,和平ミッション ある日、突然、私の先生だった隣人のA
本文を読む旧ユーゴスラヴィア戦争をめぐる、「ハーグ戦犯1号の日記」(1)
著者: 岩田昌征2010年の何月か忘れたが、見ず知らずのボスニア・セルビア人から著書が送られて来た。ハーグの旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷ICTYの第1番目の被告ドゥシコ・タディチ氏であった。 2011年1月14日付けの手紙をそえて
本文を読む自主管理社会主義の教訓――協議経済論・アソシエーション論の盲点と資本主義幻想の霧消――
著者: 岩田昌征1.協議経済化過剰の無理 ソ連東欧の集権制計画経済の危機が表面化して以来,特にその全面的崩壊以後,資本主義に降伏せず,その批判者としての社会主義に思想的意味を認める人達の間に,資本主義市場経済と対置されるべきは,官僚的
本文を読む書評 岩田昌征著『二〇世紀崩壊とユーゴスラヴィア戦争―日本異論派の言立(ことだ)て―』
著者: 鶴田満彦1.本書の構成 本書は、比較経済体制論、ユーゴスラヴィア地域研究については世界レベルの専門家である著者が、ソ連型集権的社会主義・ユーゴスラヴィア型自主管理社会主義の成立と崩壊を総括した最近の論文集である。多くの社会主義経
本文を読む原発封印と神ながらの道
著者: 岩田昌征『週刊朝日』(6月3日、6月10日号)に「歴史に学ぶ地震」と題して、森浩一、日下雅義、そして寒川旭による座談会が組まれていた。古い所では『日本書紀』天武紀や鴨長明『方丈記』の地震記録が紹介されている。ところが、史実とは
本文を読む退避勧告のうみだすプラス・マイナス/危険情報開示のプラス・マイナス
著者: 岩田昌征退避勧告のうみだすプラス・マイナス 日本に留学していた外国人留学生が3月11日の大震災・原発大災後数日で日本を自主的に去った。アメリカ国務省は3月16日に自主的国外退避勧告を出したと言う。実は、我が家もそんな動きと無縁で
本文を読むビンラディン殺害の謎
著者: 岩田昌征5月2日未明、かのウサマ・ビンラディンが米特殊部隊によって殺害された。前イラク大統領サダム・フセインの場合と違って、アメリカはビンラディンを生きたまま捕獲する意図が全くなかったようである。その意図があれば、アボタバードの
本文を読む自然災害と戦争の相違
著者: 岩田昌征私は、1991年から2001年に至る旧ユーゴスラヴィア多民族諸戦争と現地で、つまり直接的戦場すれすれの所でほぼ毎年付き合って来た。そこで、阪神大地震が起きると、戦争による破壊と地震による破壊との相違を知りたくて、数週間後
本文を読む福島原発・作業員の放射能汚染と、さる大学教授の国外避難
著者: 岩田昌征昨日3月24日、福島第一原発の危機対処中に下請け会社の現場作業員が放射能で火傷した。東電の説明によれば、装着した警報器が現場に入った瞬間になったが、作業員が誤作動だと判断して、そのまま作業に入ったからという。さすがに作業
本文を読む原発と原爆
著者: 岩田昌征現在、私たちが多少の恐怖心を抑制しつつ見守っている福島原発凶事に関して、数年前に出版された小冊子『原発を並べて自衛戦争はできない』(山田太郎著)は、素人にとって必読書ではなかろうか。 ―原発で最も危険なのは、原子炉そのも
本文を読むNATOの対セルビア1999年戦争の本音目的
著者: 岩田昌征中東北阿の雲行きが怪しい。2003年に米軍の対イラク武力侵攻がなかったならば、フセイン政権は、チュニジアとエジプトのように民衆運動で打倒されたのか、リビアのカダフィ大佐の道をたどるのか、それとも、安定性を誇示しているのか
本文を読む「チトー主義は進歩か退歩か・再論」
著者: 岩田昌征拙論「チトー主義は進歩か退歩か」に関連して、石塚正英氏と吉澤明氏から助言的コメントが寄せられた。記して感謝したい。 石塚は、エクメチチの退歩論を批判して、ファシズムやナチズムを労働大衆の運動が創りだした面が「退歩or進歩
本文を読むTPPと福澤諭吉
著者: 岩田昌征TPPが国論を二分しているといわれる。第三の開国、つまりは完全開国は、農業のみに関わることではないにせよ、農業者の一憂一喜が一番強いようである。日本の全産業がほぼ完全に国際市場というより世界市場における自己競争力によって
本文を読む労働搾取論私論
著者: 岩田昌征2月15日(火)、伊藤誠教授の「わが著書『現代のマルクス経済学』(2010年、社会評論社)を語る」アソシエ・セミナーに参加して、久しぶりに健在なマルクス経済学者の話を聞くことができた。伊藤教授はSteedmanのMarx
本文を読むHuman Rightと人権
著者: 岩田昌征去年ある大学で国際研究集会があって、若い日本人研究者が近代的人権概念Human Rightが中世後期までさかのぼれると報告した。中国人学者も参加していたので、中国においてもHuman Rightの訳語が「人権」であること
本文を読む「連帯」その後のトピックス
著者: 岩田昌征2月6日、突然ポーランド人の友人が一冊の本を送ってきた。それはリシャルド・ブガイの自伝『自分自身と他の人々について』(The Facto、ワルシャワ、2010年)であった。ブガイはワルシャワ大学経済学部出身で、1980年
本文を読むコソヴォ生体臓器密輸出に関する欧州評議会議員会議の1月25日決議
著者: 岩田昌征ポリティカ紙〈2011年1月26日〉によれば、ディック・マーティ〈スイス人、検察官〉の調査報告書(ちきゅう座における岩田による関係論述を参照)に基づいて1月25日、ストラスブルグの欧州評議会議員会議は「コソヴォにおける非
本文を読むチトー主義は進歩か退歩か?―労働者自主管理をめぐって
著者: 岩田昌征ベオグラードの週刊誌ペチャト(2010年12月31日、2011年1月14日)に二号続きで1928年生まれの高名な歴史家ミロラド・エクメチチ教授のインタビューが載っていた。そこでエクメチチは、チトー主義を評して、それはスタ
本文を読む旧ユーゴスラヴィアの経験と日本のアソシエーション論
著者: 岩田昌征基礎経済科学研究所編『未来社会を展望する 甦るマルクス』(大月書店、2010年)の合評会に出席する機会があった。「よみがえる」という和語を使い、例えば「マルクスのルネサンス」のようなカタカナ語を用いていないところが気に入
本文を読む戦争賠償と平時債務返済の関係―ギリシャとドイツ
著者: 岩田昌征第二次世界大戦の戦争責任問題に関して、ドイツは誠実に問題解決に努力したのに対し、日本はドイツほどに誠実に問題を直視していなかったという声が我が国の市民社会で聞かれる。たしかに、ナチス党が反ユダヤ主義イデオロギーを国家権力
本文を読む欧州評議会・法人権委員会の「コソヴォ臓器摘出密輸出」調査報告書の背景
著者: 岩田昌征旧ユーゴスアヴィア戦争犯罪ハーグ法廷のスイス人主席検事カルラ・デル・ポンテ(1999-2007年)は、退任後の2008年末に回想録『狩、私と戦争犯罪者』The Hunt.Me and the War Criminals
本文を読むユーゴスラヴィア自主管理社会主義の歴史実験:その意味とよみがえり(ルネサンス)の兆し(2)~(1)
著者: 岩田昌征ミーラ・マルコヴィチ「自主管理者の反乱」(1993年1月26日) ここ数日ベオグラードで、権威ある諸施設のトップが政府決定によって新しく任命されることに関して苦情が増えている。クリニック・センター、博物館、劇場などの責任
本文を読む