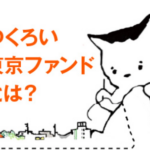当ブログの前記事「女性天皇・女系天皇に期待する人たちへ、その先を考えてみたい。」(4月14日)は、4月11日の東京新聞社説「皇位巡る議論 安定的な継承のために」が「女性・女系天皇を認めることは、男女同権を目指す社会の在り方とも一致する」として「女性・女系天皇」容認に踏み切った論調への批判であった。
そして今日4月19日の「社説」下の「ぎろんの森」は「皇位継承策と国民の支持」と題して、読者から多くの意見が届き、「そのほとんどが『社説は国民の常識・感情に寄り添ったものだ』などと賛意を示すものだった」という。この記事でも、共同通信の世論調査をあげて女性天皇を認めることに計90%が賛同し、女性皇族が皇族以外の男性と結婚して生まれた子が皇位を継ぐ「女系天皇」にも84%が賛成です」として、末尾に憲法の第一条をあげ、「主権者である国民の意見とかけ離れ、理解と支持が得られないような制度は安定的とは言えません。国民代表である国会議員は、そのことを忘れてはなりません。東京新聞は引き続き、読者と共に考え、主張すべきを主張していきます。」と結んでいる。
しかし、当ブログの前記事でも書いているように、日本国憲法第一章にある「天皇」に「女性天皇」ないし「女系天皇」となる人を当てはめてみればわかる通り、基本的人権が認められないばかりでなく、慣習や慣例にしばられ、“宗教的”な振る舞いや行事への参加が強制されることになるのはないか。「皇后」という立場であっても、そこを突破する過程で失語症や適応障害という病に直面したのである。
少し立ち止まってみれば、「女性天皇」や「女系天皇」が可能となれば、民主的な、男女平等の皇室制度が実現するかのような言説は、幻想に過ぎないのではないかと思う。その辺のことをスルーして、世論調査に追従するのみでは、ポピュリズムに堕した論調といってもよい。
いま、「東京新聞はなぜ、空気を読まないのか」(菅沼堅吾著 東京新聞 2025年1月)という本が、広告によく登場する。著者は、東日本大震災発生当時の東京新聞の編集局幹部で、「空気を読まず、読者に知らせるべきことを果敢の報じる」ジャーナリストの神髄を示す回顧録、ということである。


先の「ぎろんの森」の結語でもある「東京新聞は引き続き、読者と共に考え、主張すべきを主張していきます。」というが、天皇制になると、あまりにもストレートに「空気を読む」「空気を読み過ぎる」論調になってしまうのは「なぜ」なのか。
ところで、私はかつて、かつて、「時代の<空気を読む>ことの危うさ」(『短歌研究』2009年6月)という題で、書いたエッセイがあることを思い出した。「空気が読めない」といういい方が流行していた頃のことではなかったか。「空気が読めない人」をKYなどと呼ぶことも流行っていたようだ。
ご参考までに。

『短歌研究』2009年6月号より
初出:「内野光子のブログ」2025.4.19より許可を得て転載
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/04/post-89f671.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14208:250421〕