表題の番組に、図書館時代の友人のEさんが、「市川房枝記念会女性と政治センター」の資料紹介で、出演するという知らせが入った。当初は9月17日の予定だったが、十島の地震で、1週間後に延期、当日は、またニュースの延長で15分遅れた。「歴史探偵」は初めて見る番組で、スタジオには、タレントの探偵社所長?とアナウンサーが司会を務め、取材のアナウンサーとゲストの「選挙オタク」という若い女性タレントが登場。なんかなじみのない人ばかり。「日本人と選挙」と、テーマは大きいが、ちょうど100年前、1925年に普通選挙法が成立・公布され、はじめて実施された1928年の「男子普通選挙」、1942年の「翼賛選挙」、1946年の「戦後初めての選挙」に焦点をあてるという構成だった。それぞれの選挙の時代的背景にはあまり踏み込まず、選挙の仕組み、取り組み、結果をさまざまな資料で紹介していた。そして、取材先は、国立フィルムセンター、慶応大学メデイアセンター、高知市自由民権記念館、斉藤隆夫記念館、市川房枝記念会女性と政治センターのある婦選会館など多岐にわたっていた。婦選会館以外は行ったことがなかったので、興味津々だった。女性の選挙権獲得の運動、市川房枝の果たした役割について、Eさんの資料解説もわかりやすく、穏やかな話しぶりが、昔のままだった。


1925年5月、普通選挙法の成立・公布を経て、1928年2月20日に実施された選挙は、治安維持法などによる弾圧が厳しいなか、男子のみに与えられた選挙権だったが、まるでお祭り騒ぎのようだったという。ポスターも制限がないので、あちこちと張られ放題。結果は、政友会と民政党の接戦に終わった。この選挙で無産政党からは8人が当選、社会民衆党からは、議長の安部磯雄、西尾末広、鈴木文治、亀井貫一郎の4人が当選、当時の書記長は片山哲だった。

1941年10月に東条英機が首相に就任、12月8日には太平戦争突入、翌年1942年4月30日に実施された選挙は、「翼賛選挙」と呼ばれる。政党はすでに解散させられ、1940年10月、「大政翼賛会」が発足、大政翼賛会の推薦候補か非推薦かの候補者によって争われたが、政府、メデイア、地域をあげて推薦した候補が圧倒的な多数を占めた。


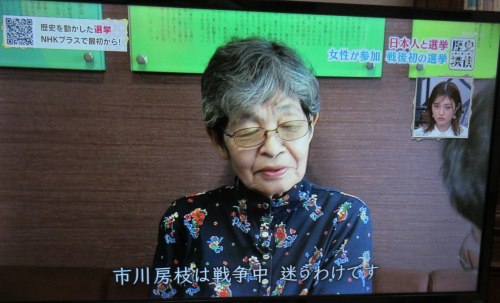
市川房枝は「婦選なくして普選なし」と闘ってきたが、翼賛選挙に際して、「女性の権利獲得のためには政府に協力する姿勢」を示して、「翼賛選挙貫徹婦人同盟」の代表者となっている。Eさんは、市川の苦渋の選択を語っていた。
そして敗戦後、1946年11月3日の新憲法公布に先だって、4月10日に女性が初めて選挙権を行使する総選挙が実施された。大方のメディアの予想に反して、女性の投票率は67%に達している。「日本ニュース」14号(1946年4月18日)では、各地の投票所に列をなし、駆け付ける女性たちの姿を伝えている。アイヌの女性たち、大島のあんこたち、託児所まで設置された投票所、和服姿で投票に向かう京都の女性たち・・・。そんな一コマに、高峰秀子の姿も映されていた。
その選挙結果は党派別で言えば自由141、進歩94、社会93、協同14、共産5、諸派38、無所属81で、女性の立候補者82名中39名が当選したのである。

あとは番組を見ての、感想ながら、大学での研究者が何人かが登場したが、多くてやや散漫にはなりはしなかったか。むしろ、資料に密着した人たちの話をもっと聞きたかった。これからは、女性と選挙、女性と政治についての特集番組があってもいいのではないか。とくに、最近の女性候補者にアナウンサー、タレント、コメンテイターなど、ただ名前が売れている人たちが多くなってしまい、でなければ、二世議員が多くなってしまったのは、ほんとに政治が「軽く」なってしまったのではないか、と思わざるを得ない。
初出:「内野光子のブログ」2025.9.27より許可を得て転載
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/09/post-762d5c.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14447:250927〕





