パナマ運河「回復」をめぐって
トランプ大統領は1月20日の就任演説で「パナマ運河を取り戻す」と宣言した。
運河の歴史を少しでも知っていれば考えられない発言であるが、知ってか、知らずか。いずれにせよ、「トランプ氏のトランプ氏たる所以」ということであろう。
運河をめぐる米国とパナマの攻防からは、中国の進出やラテンアメリカ諸国の米国離れを前に米国がいかにして覇権を維持しようとしているのか、また、パナマも運河ナショナリズム一筋ではいかない複雑な状況を抱えていることが見えてくる。
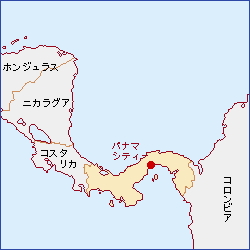
(外務省ホームページから)
スエズ運河の開設に成功したレセップスが難工事のためにパナマ運河の建設を断念すると、米国は1903年に運河建設を拒むコロンビアからパナマを分離、独立させて運河条約を結んだ。パナマを米国の保護国とし、運河の主権は米国が握り、運河と運河地帯は米国の永久租借地とする、というものであった。運河は1941年に完成した。
1977年末に米国とパナマの間で新運河条約が結ばれ、運河は1999年までに全面返還されることになった。以来、運河の運営は米国からパナマ運河庁(ACP)に移管され、国際運河として中立が宣言され、船籍や軍民を問わず通航が保証されてきた。
しかし、1989年末、ブッシュ政権はパナマに軍事侵攻し、最高権力者のノリエガ国家防衛隊長官を拘束した。ノリエガは独裁者であり、麻薬取引に加担しているという理由であった。ノリエガが即時返還の動きをみせていたこともあるが、1979年にニカラグアで反ソモサ独裁革命が成功したあと、エルサルバドルやグアテマラなどでも反政府ゲリラ活動が激化しており、米国は中米の左傾化を恐れたのである。
運河は親米政権下の1999年12月31日に全面返還された。
今年の2月初旬にマルコ・ルビオ国務長官がパナマを訪れ、インフラ整備と引き換えに米軍の艦船からは通航料を徴収しないこと、中国との覚書を更新しないことで合意したと発表した。ところが、パナマ政府はすぐさま、米艦の無料通航は運河の中立の原則に反するものであり、特定の国を特別扱いすることはないと否定した。ルビオ長官はなぜ、「嘘」を発表したのであろう。なお、米国が求めていたベネズエラやイランなどの船舶の通航制限については、米国が制裁を課している国であるという理由で、パナマは受け入れの姿勢を示している。
一方、中国との覚書の更新は、欧米諸国の投資拡大と引き換えに、停止された。ルビオ長官は運河の中立が損なわれた場合には武力行使もあり得ると強く警告したと言われている。
覚書は資金や技術協力を謳ったもので、パナマが台湾と断交し、中国と国交を樹立した2017年に調印され、3年毎に更新されてきた。以来、中国は運河関連部門だけではなく農業や不動産業なども含め広範な分野に進出し、アメリカ大陸最大と言われるコロン・フリーゾーンも中国企業が中心を占め、バルボア港とクリストーバル港の運営も香港の企業が手掛けている。
就任式でトランプが打ち出した不法移民の強制退去については、コロンビアとホンジュラスは、はじめ軍用機による送還は非人道的であるとして反対していたが、トランプが関税引き上げをちらつかせると、税率の低減と引き換えに受け入れた。
トランプが掲げる“Great America Again”は衰退しつつある覇権国家の復活を目指したものである。国務長官のマルコ・ルビオも、反中派として知られているだけではなく、フロリダ州出身のキューバ系移民2世の上院議員であり、キューバやベネズエラに加え、中道左派政権に対しても強硬策を主張してきた。
ラテンアメリカでは1990年代から米国と距離を置く政権が次々と誕生し、「ピンクタイド」と呼ばれた。しかし、第一次トランプ政権(2017~21年)下では右傾化の波に洗われ、2019年だけでも、ブラジルでは「第2のトランプ」と呼ばれるボルソナロ政権が成立し、ベネズエラでは野党の無名の国会議員のグアイドが突如、「臨時大統領」を宣言している。トランプは、2016年にオバマ大統領が半世紀ぶりにキューバと国交を回復し、制裁緩和措置を実施すると、政権を握るや、直ちに反故にし、今年1月にバイデン政権が離任直前にキューバをテロ支援国家リストから除外したときにも、大統領就任式に撤回した。「モンロー主義者トランプ」と言われる所以である。
しかし、米国の対ラテンアメリカ政策の基本理念は「西半球においては米国と異なる社会体制の存在を認めない」という点にあり、共和党政権、民主党政権を問わず、米国の意に沿わない政権に対してはあらゆる干渉を行ってきた。バイデン前大統領もトランプ第一次政権下で導入されたキューバに対する「制裁」強化策の見直しを掲げていたが、何もなさずに任期を終えている。
第一次トランプ政権下で衰退したピンクタイドはすぐさま復活し、2018年にはメキシコでロペス・オブラドール政権が、22年にはチリのボーリチ政権とコロンビアのペトロ政権が、次いで23年にはブラジルのルーラ政権が誕生している(ちなみに日本では「ボリッチ」と表記されているが、現地ではボーリチと呼ばれている)。
米国にとってとくに打撃だったのは、「新自由主義の優等生」といわれてきたチリと、米国の南米支配の拠点となってきたコロンビアの政権転換であろう。
チリではピノチェ軍事政権が崩壊し、民政に移管したあとも新自由主義体制が維持され、高度成長が続いたことから「成熟した新自由主義」として国際的に高く評価されてきた。しかし、2006年に高校生が教育の不平等や質の劣化に抗議してデモを開始すると、「社会爆発」と呼ばれる全国民的な反新自由主義運動に発展し、22年3月には学生運動出身の30代のボーリチが大統領に就任した。
コロンビアも、麻薬とゲリラの国と言われ、治安維持が最優先課題とされて強権的な保守政権が続いてきたが、ゲリラとの和平交渉が進むとともに、チリと同様、21年に「社会爆発」が発生し、22年8月には反新自由主義、民主化、環境保護を掲げるペトロ政権が成立した。ペトロは都市ゲリラ組織M-19の元メンバーである。M-19は2000年にM-19民主同盟という政党になっている。
しかし、ピンクタイド政権も必ずしも盤石ではない。
ボーリチ政権も、またペトロ政権も、全国民的な社会運動に支えられて成立しながら、議会で多数を占める保守派に阻まれ、「何もできないでいる」。選挙制度の制約もあるが、それだけではなく、国民の半数近くが依然として保守派を支持しているのである。
ボーリチが当選した2021年の大統領の決戦投票では軍政派のカスト候補が44%の支持票を得ている。2022年の新憲法草案の是非を問う国民投票でも反対票が61,86%に上り、否決された。民主化を進めるためには、まず第1歩として基本的人権や自由の制限を規定したピノチェ憲法、すなわち1980年憲法の改正が不可欠であっただけに、敗北のショックは大きかった。
このときには投票が義務化され、投票率は85.86%、通常の選挙と比し550万人の増加であった。あるシンクタンクの調査によれば、その多くは「大都市に住み、情報源はテレビなどの伝統的メディア、政党や労組など組織との繋がりがなく、政治に不信感抱く人々」であったという。とくに反対が多かったのは女性の完全な平等と先住民の自治権である。保守派が反対キャンペーンを大々的に繰り広げていた項目である。
長引く新自由主義体制のもとで国民はやり場のない不安や不満に苛まれ、政治的アパシーに陥っている。にもかかわらず多くの人々が現状維持を選んだのであった。
米国の対ラテンアメリカ政策は、かつてのようなクーデタなどの直接干渉は影を潜め、内部から政権を崩壊させる戦略に移っている。経済的に締めつけて経済情勢を悪化させ、国民の不満を高めるという政策もその一つである。ラテンアメリカ諸国はコロナ禍や世界経済の低迷のために極めて厳しい経済状況にあり、そのための条件は整っている。
しかし、今日、最も重点が置かれているのは情報操作である。民主化の時代でもあり、強権支配や政治腐敗や選挙の不正などを訴えれば民心に与える影響は大きい。しかも、情報化の時代にあって「常識」が拡散し、多くの人々の心に浸透している。
情報操作は極右勢力の台頭にもつながっている。
「極右のミレイ政権」と接頭語がつけられて呼ばれているアルゼンチンのミレイ大統領は、「リバタリアン」を標榜し、新自由主義経済化を推進し、福祉体制を解体しているだけではなく、軍政時代(1976~83年)の人権侵害の犠牲者の記憶館を閉鎖し、追悼式典も廃止した。今年1月のダボスにおける世界経済フォーラムではフェミニズムを「幼児的悪習」と批判している。ミレイは経済情勢が悪化し、経済再生が最大の争点となった2023年の決戦投票で、前政権の再分配政策を「バラマキ」と批判し、経済運営能力の欠如を訴え、当選した。第2、第3のトランプ政権成立の土壌が整っている。
ラテンアメリカのピンクタイド政権はトランプ旋風を乗り切ることができるであろうか。
初出:「リベラル21」2025.02.19より許可を得て転載
http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6687.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14109:250219〕






