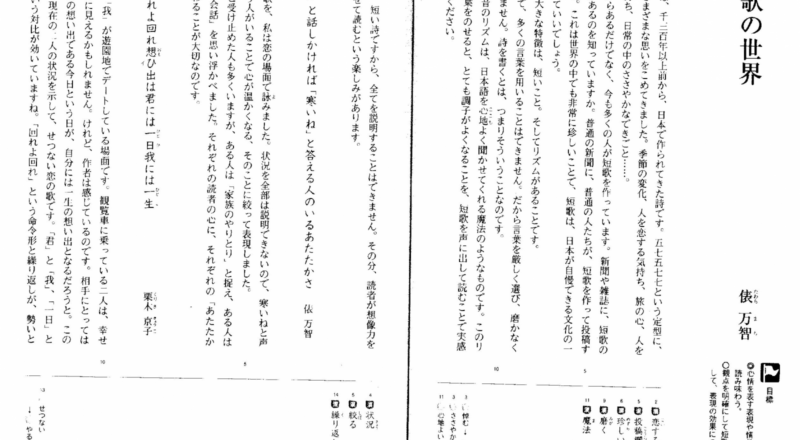2025年4月から中学校の教科書が新しくなった。2016年から採用の中学校の国語教科書、2年生で扱われる「近・現代の短歌」について調べたことがある。この10年間にもう一回の検定を挟むが、今回の検定で、どう変わっているのか、変わっていないのか、調べてみようと思う。十年前には、三省堂、東京書籍、教育出版、学校図書、光村出版の五社であったが、今回は学校図書が撤退して四社となった。学校図書は、親会社の数研出版の伝統もあって理系に重点を置きたかったのかなとも。
三省堂『現代の国語2』

「第3章ものの味方・感性を養う」に登場するのが短歌で、俵万智「短歌の世界」という書下ろしのエッセイが冒頭に置かれている。ここでは、短歌は、伝統のある定型の詩形であること、短いこととリズムが特徴であり、自作と栗木の二首をあげ、いずれのも「恋の歌」と紹介されている。「心の揺れ」が作歌の第一歩とする2頁ほどの短い文章。
・「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ(俵万智)
・観覧車回れよ回れ想ひ出は君には一日我には一生(栗木京子)
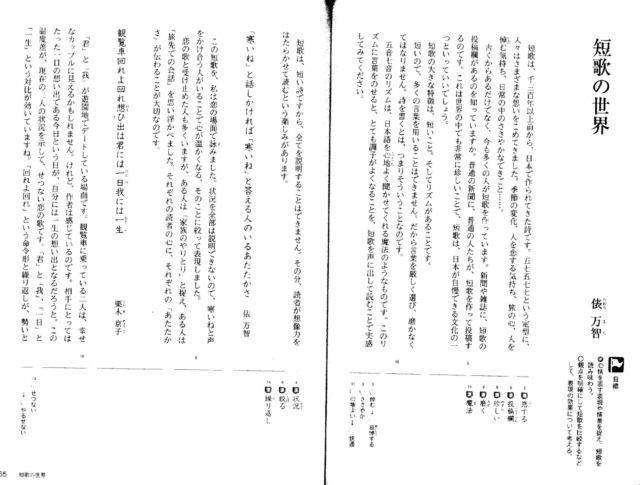
「短歌十首」では、(括弧内は、2016年度版の収録教科書)
・くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる(正岡子規)
(三省堂・学校図書・東京書籍・光村)⇒三省堂
・その子二十櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな(与謝野晶子)
(三省堂)⇒三省堂
・みちのくの母のいのちを一目みん一目みんとぞたたにいそげる(斎藤茂吉)
(教育出版)⇒三省堂*新
・草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり(北原白秋)
(東書・三省堂)⇒三省堂
・白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ(若山牧水)
(東書・三省堂・教育・光村)⇒三省堂
・不来方のお城の草に寝ころびて/空に吸はれし/十五の心(石川啄木)
(東書・学図・三省堂・光村)⇒三省堂
・列車にて遠く見ている向日葵は少年のふる帽子のごとし(寺山修司)
(三省堂)⇒三省堂
・シャボンまみれの猫が逃げ出す午下り永遠なんてどこにもないさ(穂村弘)
(三省堂)⇒三省堂
・空をゆく鳥の上には何がある 横断(ゼブラ)歩道(ゾーン)に立ち止まる夏(梅内美華子)
⇒三省堂*新
・細胞のなかに奇妙な構造のあらわれにけり夜の顕微鏡(永田紅)
(三省堂)⇒三省堂
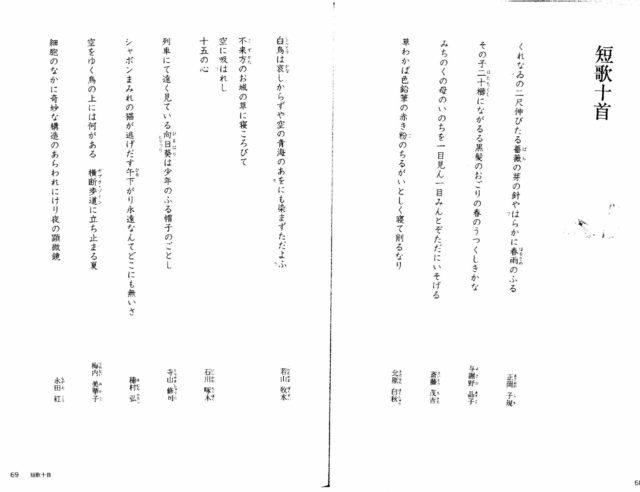
2016年版と比べると、茂吉の「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞こゆ(学図・三省堂・教育)」が上記と入れ替わり、釈迢空「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」が除かれ、梅内の作品が新規に入ったことになる。俵「「寒いね」・・」と栗木「観覧車・・・」は俵のエッセイで触れているからか、「十首」には二人とも登場しない。今回新しく収録された歌人は、迢空と入れ替わった梅内のみで、これはかなり大胆な変更であったが、作品が替えられたのは茂吉だけという異動であって、全体的には、オーソドックスな人選と選歌がなされているのではないか。
また、歌人の顔写真がモノクロとカラーの違いがあるのは、まさに世代の違いを表しているのは興味深い。「私の本棚広がる短歌の世界」として、以下の3冊が書影入りで紹介されている。
俵万智『あなたと読む恋の歌百首』朝日新聞社 1997年8月
栗木京子『短歌をつくろう』岩波書店 1999年12月
枡野浩一『ドラえもん短歌』小学館 2005年9月

巻末の「小さな図書館」42冊の中には、村上しいこ「歌うとは小さないのちのひろいあげ」(講談社 2015年5月)をあげ、短歌甲子園を目指す高校生の物語が紹介されている。
なお、三年生で、俳句と古典和歌―萬葉集、古今集、新古今集を学ぶのは変わらない。
教育出版『伝え合う言葉中学国語2』
短歌は、「第六章想像を広げる」に含まれる。穂村弘の書下ろしエッセイ「短歌の味わい」では、つぎの自作を含めた四首の鑑賞がなされている。斎藤史の登場はいささか唐突にも思えた。教師も生徒も、この一首の時代的背景を理解するのは、容易ではないかもしれない。
・白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ(若山牧水)
・濁流だ濁流だと叫び流れゆく末は泥土か夜明けか知らぬ(斎藤史)
・観覧車回れよ回れ想ひ出は君には一日我には一生(栗木京子)
・春のプール夏のプール秋のプール冬のプールの星が降るなり(穂村弘)
「短歌十首」ではつぎの作品を挙げている。
・くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる(正岡子規)
(三・学・東・光)⇒三省堂、教育出版
・ああ皐月(さつき)仏)蘭西(フランス)の野は火の色す君も雛罌粟(コクリコ)われも雛罌粟(コクリコ)(与謝野晶子)
⇒教育出版*新
・みちのくの母のいのちを一目見ん一目みんとぞたたにいそげる(斎藤茂吉)
(教育)⇒三省堂*新、教育出版
・不来方のお城の草に寝ころびて/空に吸はれし/十五の心(石川啄木)
(東書・学図・三省堂・光村)⇒三省堂、教育出版*新
・日本を脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも(塚本邦雄)
⇒教育出版*新
・海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり(寺山修司)
(東書・光村)⇒教育出版*新
・俺は帰るぞ俺の明日へ 黄金の疲れに眠る友よおやすみ(佐佐木幸綱)
⇒教育出版*新
・自転車のカゴからわんとはみ出してなにか嬉しいセロリの葉っぱ(俵万智)
⇒教育出版*新
・おねがいねって渡されているこの鍵をわたしは失くしてしまう気がする(東直子)
⇒教育出版*新
・もう二度とこんなに多くのダンボールを切ることはない最後の文化祭(小島なお)
⇒教育出版*新
2016年版は、「近代の短歌」として晶子2首、茂吉3首、白秋1首、牧水1首、啄木2首、合計9首が収録されていたのが、「短歌十首」として、大幅に世代交代が行われ、新しく塚本邦雄、寺山修司、佐佐木幸綱、東直子、小島なおの短歌が採られ、その異動が顕著であった。
作品としては、晶子の「なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな」「小百合さく小草がなかに君まてば野末にほひて虹あらはれぬ」が上記の1首に。
啄木は「やはらかに柳あをめる北上の岸辺目に見ゆ泣けとごとくに」「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」の2首に替わって「不来方・・・」が入り、俵は「『寒いね』・・・」に替わって、上記の作品が採られている。
穂村のエッセイに登場する4人の短歌は、ここには入っていない。
なお、穂村はもう一本「少しだけ変えてみる」というエッセイで、啄木の「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」などを例に、一文字、一語変えるだけで、一首の世界が変わり、広がることを説いている。
各章ごとに「広がる本の世界」という読書案内が付されているが、第六章では以下が紹介されている。
小島なお・千葉聡「短歌部、ただいま部員募集中!」(岩波書店2022年4月)
コラムの「四季のたより」では、古典和歌一首と俳句が掲載されている。また、三年生になると、俳句と古典和歌の単元があり、萬葉集、古今集、新古今集を学ぶようになっている。さらに評論として、穂村弘「青春の歌―無名性の光」が登場する。
教育出版は、穂村の重用が目立つほか、若手歌人の起用が顕著であることもわかる。ちなみに、私が住む佐倉市は、この国語教科書を採用して久しい。
初出:「内野光子のブログ」2025.8.25より許可を得て転載
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/08/post-3706f1.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14400:250826〕