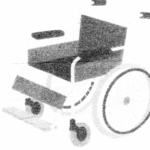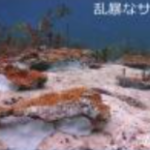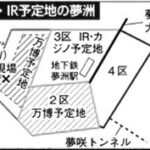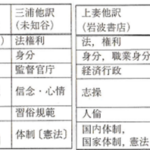日窒延岡工場のアンモニア合成装置が完成し、発明者カザレーの手によって試運転が始まったのは1923年9月のことだった。日本初のアンモニア合成であり、日本の化学工業界全体においても慶事であった。
ところが日本はその月、たいへんな凶事に見舞われていた。関東大震災である。死者・行方不明者は推定10万5,000人にのぼる。
【朝鮮人大虐殺】
震災の被害は、地震や火災の被害だけではなかった。9月1日正午の地震後の恐怖と混乱のさなか、地震の被害が大きかった関東一帯で、朝鮮人が「死人のものを盗んでいる」、「放火した」、「井戸に毒を入れた」という流言が飛び交い、各地の警察に通報された。2日夕方、内務省警保局長は「朝鮮人が各地で放火している」、「東京市内で爆弾を所持」「石油をまいて火をつけている」などと伝え、厳密な取り締まりを加えよと通牒し、戒厳令を発令した。これは翌日3日、船橋海軍無線送信所から全国に打電された。
そうして警察、軍、自警団と称する集団は朝鮮人をみつけては捕えて殺害した。朝鮮人と間違えて殺された中国人、日本人もいる。また、朝鮮人を保護した庶民も多いし、一部、積極的に保護した警察もいる。2日夜か3日、警察は朝鮮人暴動の実在を疑い、3日には「大部分の鮮人は順良だが注意せよ」と、やや修正するが、虐殺はすぐには収まらず、数日間関東一帯で続いた。
こうして多くの朝鮮人が虐殺されたが、殺人事件として立件されたのはわずか53件。その被害者は233人だが、もちろん実際の死者ははるかに多い。震災の混乱で死体の処理も進まないなか、当時の政府は、遺骨を朝鮮人とわからないように処置しろと命じて虐殺の隠蔽と矮小化を図っている。被害者の数の確定はほぼ不可能であるが、関東地方には概ね2万人の朝鮮人がいて、生存が確認されたのが1万1千人で他不明とされている。朝鮮の罹災同胞慰問班は6415人の犠牲者を数えたそうで、これは大きく外れた数ではないだろうと言われている。
ちなみに当時、特別高等警察(特高)のトップは正力松太郎。彼は1918年、警視庁監察官時代に「米騒動」の鎮圧で昇進している。国内朝鮮人の動向や、社会主義者、共産党結成の動きにはいつも目を光らせていた。震災の9月に起こった亀戸事件や甘粕事件の公然の黒幕である。
また当時の内務大臣は水野錬太郎、警視総監は赤池濃(あつし)。水野は1919年朝鮮の「三・一運動」のとき朝鮮総督府の政務総監、赤池は同じく警視総監であった。
【三・一運動で見たもの】
震災時の日本政府や警察の判断には、植民地化以降最大の民主化運動であった「三・一運動」の体験が働いている。
1918年、ロシア革命後にアメリカのウィルソン大統領が発表した「民族自決主義」は朝鮮の民衆に火をつけた。もし国際会議で朝鮮の独立が決議されれば、欧米はそれを支持するのではと彼らは考えた。その火種は東京にあった。監視が厳しかった朝鮮国内より、大正デモクラシーの空気が広まっている日本本土にいる朝鮮人留学生が最もまとまった組織であった。彼らは「新年会」「忘年会」と偽装しては集まり、議論を重ねていた。(特高は彼らをしっかり監視していたことが内務省の資料に残っている。)
朝鮮人留学生たちは1919年2月28日、東京神田YMCA館で「二・八独立宣言」を発表する。それが密かに朝鮮に持ち込まれた。
3月1日、京城(現・ソウル)ではかつての国王、高宗の葬儀が行われるところで、地方からも多くの民衆およそ千人が中心部パゴダ公園に集まっていた。そこで「独立宣言書」が発表された。すると人々は太極旗を振りながら「大韓独立万歳」と叫びながら歩き始め、それはたちまち十万人に膨れ上がり、半島各都市にも伝播した。朝鮮内外での参加者総数は2百万人にも及んだと言われている。
日本政府は驚き、軍隊と武装した憲兵警察を派遣し、次々と取り締まり、殺害した。日本人居留民も刀などで武装して殺している。特に水原(スウォン)の教会では37人を教会堂に閉じ込めて教会まるごと焼き殺している。運動の先導者は拷問の挙げく殺された者も多かった。こうして7,509人が殺され、15,961人が負傷した。逮捕者は46,948人にのぼった。
1919年4月、独立運動家たちは亡命し、海外で独立運動を行っていた運動家らとともに上海で臨時政府を組織する。首班は李承晩であった。なお、5月には「三・一運動」の影響をうけて中国では「五・四運動」と呼ばれる抗日運動が起こっている。
この4年後が関東大震災であった。混乱に乗じて朝鮮人が悪さをはたらいているという通報の真偽はともかく、当局は「三・一運動」でみたような朝鮮人たちの爆発的な結束力の記憶が蘇ったに違いない。その恐怖と、彼らからの報復に怯え、即座に、手段を選ばずに取り締まる(=殺してよい)という判断をしたかもしれない。
もう一つは、民族差別の強化である。植民地主義には民族差別が不可欠である。行政府はつねに差別を構築し維持し利用することを心がけている。一般市民の差別意識に火をつけ、その手で朝鮮人を殺させるということは、民族差別の維持におおいに貢献するはずだと、正力ほどの人物ならば即座に判断するだろう。
【日本に渡航した朝鮮人たち】
関東大震災が発生した1923年、正確な数の把握は難しいが、日本には十万人を超える朝鮮人が居住していた。なぜそれほど多くの朝鮮人が日本にやってきたのか。
日露戦争後、日本は急速に工業化を進めるなか、農業人口が減少した。そこで農産物(特に米)の生産量を補うために朝鮮を穀倉地帯化しようとした。初期の植民地政策は「勧農政策」に重点が置かれた。
「併合」以前、1905年、第二次日韓協約に基づき設置された朝鮮統監府は、1908年、国策会社「東洋拓殖株式会社(東拓)」を設立した。
1910年に朝鮮を「併合」してから朝鮮総督府が最初に行った大きな政策は、明治維新でいうと地租改正だった。しかし方法は杜撰で、所有者が曖昧な土地を次々と没収していった。また王朝の所有地13万ヘクタールも没収。それらの土地は東拓を中心とした日本の農業会社に安く払い下げられた。
そうして多くの農民が土地を失い小作化し、さらに地租の金納化によって困窮し、換金労働を探さなくてはならなかった。半島内の工業化は1920年代を待たなくてはいけない。それまでは海外(ロシア、中国、日本)で職を探した。半島南部のひとたちは多くが日本に渡航した。
大戦景気に湧いていた日本は慢性的な人手不足だったが、危険で労働条件の悪い炭鉱の鉱夫、ダムや鉄道工事、労働環境の劣悪な繊維産業などから、朝鮮人労働力を充填していった。彼らには平均して日本人の約7割の賃金しか支払われなかった。
こうして日本人の職場環境には「危険で汚いところで低賃金で働く朝鮮人」の姿が定着し、植民地主義(民族差別と支配者意識)が日本人庶民の意識に内在化していったのである。
【1923年の状況】
このときの社会状況として重要なことは、既に不況だったことである。大戦景気時代、労働力を補うために受け入れた企業は、景気が悪くなると賃金の安い朝鮮人をすすんで雇用したので、雇用を奪われた日本人の憎悪が朝鮮人(中国人)に向けられていた。
震災直後は日本に渡航する朝鮮人は一時的に減ったが、それでも半島での失業率は深刻で、1924年には渡航者が増加した。そこで日本政府は、1922年に廃止していた旅行証明書制度を復活させ、渡航を抑制した。
【硫安をめぐる状況】
ここまで、日窒が朝鮮半島に進出する時代背景の一面を確認したが、ここからは進出の契機を辿ってみる。
関東大震災の1923年9月に日窒延岡工場はアンモニア合成に成功し、合成硫安の工業的な生産が見えてきたところだった。前述したが、それまでの製造法のわずか半分のコストで製造することができるようになった。
第一次世界大戦は日本とアメリカが国際市場における物資や軍需の供給国となって好景気を謳歌していたのだが、当然、同時に安い輸入品が途絶えたため内需が劇的に増加した。新参の日窒の経営が軌道に乗れたのはそのためである。
大戦が終わると、米国産の安い硫安(鉄鋼産業の副生硫安)が流入してくると推測されていたが、実際は英国とドイツの硫安が増えてきた。それでも1922年までは輸入硫安の量はそれほどの伸びを見せず国産は50%をキープしていた。 ところが1923年4月、英国のブランナ・モンド商会がアメリカより安い値で攻勢を仕掛けたことを契機に「安値競争」が始まった。
特にドイツ製は安く、しかも品質がよく、あっという間に英国製を追い抜き、1925年には輸入量の5~6割を占めるようになった。戦争中、公海を封鎖されたドイツは火薬の原料をすべて自国の合成アンモニアでまかなっていた。戦後、軍需が肥料産業に転向していたのである。ちなみにアンモニア合成の発明者フリッツ・ハーバーは1925年、化学産業カルテルであるIGファルベンを結成し、のちに化学兵器の分野でナチスに積極的に関与することになる。
野口は、合成硫安によってコスト面で外国産硫安に対抗できると考え、生産設備を拡張し合理化を図ったが、ドイツの価格には追いつけなかった。ボトルネックとなっていたのは電気代だった。
【同窓生からの打診】
帝国大学電気工学科で野口の同窓であった森田一雄は、技師として日本各地の水力発電所の設計に携わっていた。なかでも1908年に大井川上流に、当時世界最大の堤防を築くという日英水電(英国からの外資導入、大井川の水力開発、東京への電力供給を目指した会社)の計画にアメリカ人技師の元で関与したことがある。この計画は地元の強い反対にあって中止された。
その後、九州水力が筑後川に計画した女子畑(おなごはた)水力発電所では1911年に技師長となり計画の中心にいた。これは九州初の1万Kw超の発電所で、当時主流の流れ込み式ではあったが、中間に貯水池を持っていて、水量変化を平均化できる特長を持っていた。
またその後、北海道空知川に造られた日本初の重力式コンクリートダムである富士製紙野花南発電所の設計でもその中心にいた。ちなみにこの工事は困難を極め、朝鮮人を中心とした3000人ほどがいわゆる「タコ部屋」労働をさせられた。
森田はこのように従来の常識を覆す大規模で先進的な設計や工法に触れ、自身でそれを野心的に取り入れてきた。だが、どの計画も地元住民の強い反対にあい、着工後は業者側から批判を矢のように浴び続けたと述懐している。そういう森田が、植民地朝鮮に関心を持つのは自然だったかもしれない。
朝鮮総督府の機関紙「京城日報」と日英電気の社長を務めていた副島道正が、森田に朝鮮での電力開発について相談してきた。それで調査をしようと朝鮮の地図を借りに1924年、東京の「久保田工業事務所」を訪ねたのが久保田豊との出会いだった。久保田は既に京城にも事務所を開設していて、たえず東京と往復していた。森田は二ヶ月後、「久保田君、大へんなものがあるよ。出願しようじゃないか」と興奮した様子で事務所にやってきた。
中国との国境を流れる大河、鴨緑江にそそぐ支流、赴戦江(ふせんこう)と長津江(ちょうしんこう)が森田の考える適地であった。その年の10月、森田は朝鮮に向かった。咸興から馬を使って現地を100kmほどまわり測量すると、予想どおり工事が可能だと判断し、京城に戻ると、さっそく副島道正とともに朝鮮の実業界の人間を発起人に並べて法人を組織し、総督府に水利権の申請をしようとした。
ところが赴戦江も長津江も既に三菱が水利権を申請していたことがわかる。だが、三菱はなかなか計画を進めていなかった。しかも総督府からは「山の中の電気を何に使うのか?あのへんでは何百kwぐらいの電力しか使っていない。京城まで送電線でもってきても、数万kwぐらいのものでしょう。消化の方向がきまらないと、取り上げられない」という返事だった。確かにそのとおりで、三菱もそういう理由で計画を進めていなかったのだろう。
だが1920年代に入ってから朝鮮総督府は半島の工業化を急いでいた。電気を使う産業設備もいっしょに提案すれば通るかもしれない。森田と久保田はすぐに「電気を使う方法を考えよう」となった。本末転倒のようだが、当時の電力開発の思想がうかがい知れる。
森田の頭に浮かぶのは幾人かの同窓生だった。電化の藤田、日窒の野口、日立の小平。久保田に相談すると「藤田さんはすぐに金は出すだろうけど着工は慎重だろう、野口さんだったらすぐに仕事を始めるでしょう」という回答だった。久保田は野口と仕事をしたことがあった。
森田は野口に「こういうわけだから、名目だけでよいので買電予約をしてもらえないか」と手紙を出すと、すぐに本社に来いと電報が返ってきた。大阪本社に行くと野口と市川誠次が出迎え、同級生の再会となった。
電力コストのボトルネックに行き詰まっていた野口にとって「朝鮮の電力原価は日本の1/3」という森田の計算は魅力的で「買電契約などというまわりくどいことはやめてぜんぶ俺にやらせろ」と回答をした。
今度は野口側の人脈を使って根回しを行い、電力使用計画を揃えて総督府に申請した。すると、三菱側から日窒がうちの計画を盗んだと訴えがあり、結局、赴戦江は日窒に、長津江は三菱に許可が下ろされた。三菱は日窒のメインバンクである。
かくして1925年1月27日、日窒の全額出資により資本金2000万円の朝鮮水電株式会社が設立された。社長に野口遵、専務に森田一雄が就任し、赴戦江発電所工事が始まることになる。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔study1312:240815〕