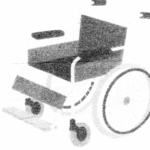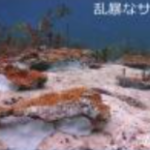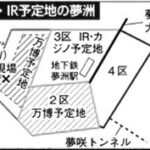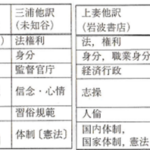1945(昭和20)年9月2日東京湾に停泊した戦艦ミズーリの甲板にて、日本は降伏文書に署名し、無条件降伏が確定した。同日、GHQ(連合軍総司令部)が開設され、軍の解体と軍需生産の全面停止が命じられた。
日本の戦後処理は、ドイツのように連合国での分割占領の検討は行われたが、トルーマンがアメリカの主導権を譲らず、他の連合国は名目的な役割しか担わなかった。
ドイツと違い、日本を敗戦に至らせた軍はアメリカ軍であったことにはどの国も異論は無かった。また分割占領を許すとソヴィエトがそこに入り込む恐れがあることは西側の連合国も察しただろう。
一方ソヴィエトも、ヤルタ会談で約束していた南樺太と千島列島、満洲(その約束通り後に中国に返還)を獲得できたので、アメリカと対立して日本の占領権益を主張することはしなかった。(日ソ戦は満洲、樺太、千島列島などで9月5日まで続いた。)
これによって、朝鮮半島に引かれた「38度線」が日本海を越えてくることはなかった。
【占領政策】
アメリカは戦争中から対日占領政策を組織的に構想していた。しかし首脳部には日本に対する関心の低さと知識の乏しさがあった。日本語という言葉の壁も高かった。そのため、在日経験のある知日派外交官の活躍によって占領政策はその基礎が形成されていったという。
最高司令官のマッカーサーは8月26日に厚木に降り立った。彼は太平洋戦争の初期、フィリピン派遣軍司令官だった。1942(昭和17)年1月日本軍が侵攻しマニラを占領、そのとき「I shall return」の言葉を残してオーストラリアに撤退した。「shall」に込めた意志を叶えたかたちとなった。
GHQは占領政策を開始した。憲法をはじめとして、日本の諸制度・機構を根本から改革しようとした。GHQの改革の基本は、徹底的・恒久的な武装解除であった。憲法9条に軍備や戦争の永久放棄が謳われたように、物理的、思想的、政治的、経済的に、再軍備の根を完全に絶やそうとした。その他の占領政策も、戦争放棄を軸に派生したものであった。
その裏には、アメリカの世界覇権の筋書きがあった。日本および朝鮮は、アメリカの極東政策であり、同時に極西政策であった。
日本は敗戦を境として戦前の価値観をひっくり返され、まるで生まれ変わらされたように認識されることが多いが、よく調べるとアメリカの改革は不徹底ぶりが目立つ。
まず天皇制と官僚制が残った。前者は政治的なものだが、後者については、非軍事化と民主化が優先されたのと、官僚機構を用いた間接統治が占領政策において効率的で実効性があると判断したためだった。そのため日本側としては抜け道が多かった。
特に「軍需省」は徹夜作業で物理的に看板をかけかえることで「商工省」として人員構成とともに生き残った(軍人は除く)。(1949年に通商産業省と名称変更)
結局解体された省庁は内務省と警察だけだった。それ以外は機構も人員もそのまま戦後に引き継がれた。GHQが新たに設置したのは総務省だけにとどまった。
ドイツのように中央政府が完全に解体され、戦時中の指導者層が完全に一掃されたのとはまるで対照的な結果となった。
また占領政策実施中に、アメリカの核技術がソ連へ「流出」したことにより、「冷戦」状態に急展開したことでGHQの方針が変化(軟化)したり、さらに朝鮮戦争の勃発(1950~)により講和(独立)を急ぐ状況になったりして、混乱のなか改革は朝令暮改的となったことも、不徹底の要因となった。
【戦争経済の「改革」】
軍備・軍需の根を絶やすためにGHQは経済政策を重視した。
まずは戦争によって利益を得る構造の解体、すなわち財閥解体が第一に進められた。
”War does not pay”=「戦争は儲からないことをすべての日本人の脳裏に深く刻みつけろ」(GHQ経済科学局長クレーマー大佐)というのが占領軍の考えを表しているが、深読みすれば、それは「軍需の蜜の味」を日本は禁忌とする政策だった。
しかしその割に、経済改革にこそ不徹底ぶりが目立つ。
まずは銀行である。戦争末期には企業の資金は株式ではなく銀行貸し出しが9割以上にも及んでいた。それらの銀行が、植民地のものを除きすべて生き残った。
GHQの金融財政課は、集中排除法を銀行にも適用しようとしたり、銀行と産業の分離を図った改革制度案を提示したりしたが、どういうわけかいずれも採用されなかった。
1942年にナチスのドイツ帝国銀行法を模倣して制定されたといわれる日本銀行法にも手を付けなかった。1998年に改正されるまで、戦後の経済基本法のひとつであった。
そして、日窒に莫大な融資を行っていた日本興業銀行も、GHQから一度目をつけられたものの、なぜか生き残った。(1950年に普通銀行に、1952年に長期信用銀行となる)
そして興銀の復興金融部が独立し、1947年1月、全額政府出資で復興金融金庫が設立された。(1951年 日本開発銀行→2008年 日本政策投資銀行)
復興金融金庫は「ドッジ・ライン」が制定されるまで、まるで戦中の興銀を彷彿とさせるような、莫大な資金を市場に投下した。
【財閥解体】
財閥解体は1945(昭和20)年の9月から早速始まった。当初は旧財閥(三井、三菱、住友、安田)に加え中島飛行機が指定され、のちに日窒を含むいわゆる新興財閥が対象とされていった。日窒がどの時点で指定(GHQからの資料提出命令)されたか諸説あってはっきりしないが、指定を受けたことは確かである。
1945(昭和20)年11月に日本政府はGHQの指導のもと「制限会社令」を公布。財閥や大企業の通常業務執行以外の資産移動の制限を目的としていた。日窒を含むその傘下29社が指定を受けた。
1946(昭和21)年8月には持株会社整理委員会が設立され、段階的に83社が指定された。日窒も指定を受けた。
両指定を受けた日窒は、著しく企業活動の自由を制限されながら、再出発を模索することとなった。
1947年12月にはGHQの財閥解体政策を受けて、日本政府が自主的に「過度経済力集中排除法」を制定した。これは特定の企業が持つ経済力が過度に集中することを防ぐことを目的としていた。特定325社にも日窒は指定された。
【逃げ足が早かった延岡】
日窒は巨大な財閥だったので様々な指定を受けたが、8割の資産を海外植民地に有していたので、それらは(資産を国内に有していた日窒鉱業を除き)すべて自動的に解散となった。
水俣工場は1945(昭和20)年10月に既に生産を再開していたが、それでも12月の『東洋経済新報』には「結局解散するほかなかろう」と書かれている。
財閥解体の方針は示されたが、まだ具体的内容や法律、手続きが明確ではなかったので、日窒としては「延岡」を取り込んでの再建策、というよりも「延岡」にすがって解散を避ける道を模索していた。
ところで「延岡」は、火薬部門が日本窒素火薬と、繊維部門は旭ベンベルグ絹糸となっていたが、戦時体制下、高品質化学繊維の需要が激減したので、日本窒素火薬と合併し1943(昭和18)年1月15日、日窒化学工業株式会社となっていた。(1944(昭和19)年1月17日軍需会社の指定を受けている。)
敗戦の時点で、日窒による日窒化学工業の資本参加率は100%ではなかった(86.1%)。
日窒は次のような案を用意していた。
日窒化学工業の繊維部門を独立させ新会社を発足し独立させる。そしてその他の事業に、日窒から分離させた水俣工場を統合させ、基幹である硫安事業を守る。
ところが日窒化学工業には日窒から独立する意見が多かった。早くも1945年11月の重役会の時点で独自に再建する意見が出ていた。社長の宮崎輝は社内で独立宣言をしていたという。すでに1946(昭和21)年4月1日には「旭化成工業」と社名と定款を変更していた。
日窒は、「進駐軍の集中排除方針」を盾にとって独立しようとする旭化成の動きを止めることができず、1946(昭和21)年7月2日、独立を承認。翌年12月、日窒が保有する株式をすべて持株会社整理委員会に譲渡した。
日窒重役会は旭化成独立承認のさい「朝鮮等からの引揚者にたいして旭化成もその責任を果たすことを信頼し支配を停止する」としている。しかし実際、旭化成は少数の優秀者しか受け入れなかったと言われている。
日窒は「事業の継続」と「引揚者対策」ともに頼りにしていた「延岡」(旭化成)に足早に逃げられてしまったかたちとなった。
【帰還者の雇用創出】
日窒は、単独での海外からの引き揚げ従業員の受け入れは不可能だったため、工場や新会社を設立した。財閥解体に指定されているなか、綱渡り的にそれらは行われた。
様々なかたちで設立・再興した事業もあった。代表的なもので現存しているものは次のとおりである。
(徳山肥料工場)
日本政府の農業振興のための方針で、いくつか残存していた旧海軍燃料廠を肥料工場に転用することがGHQに提案され、了承された。
四日市・名古屋の旧海軍燃料廠は日本肥料(1940年 肥料統制のために設立された国策企業)、岩国は三菱化成、徳山を日窒が分担することになった。ただし日窒は「制限会社」に指定されたため、日本肥料からの施工請負と完成後の経営委託という体裁が取られた。
しかし7400万円も投入し完成間近までこぎつけたところで、GHQから工事中止命令が出された。産業復興公団が買い上げて精算された。
(積水産業)
敗戦時に東京事務所次長であった上野次郎男が1946年の夏頃、プラスチックの総合事業化を提唱し、その後中堅幹部も加わって構想された。そして日窒の7名のメンバーが飛び出して1947年3月、日窒奈良工場を借用して設立した。初期メンバーには提唱者の上野は入っていない。
「積水」の由来は、甲子園近くにあった日窒の「積水寮」だが、その名付け親は野口遵で、古代中国の孫武の作とされる『孫子』の「軍形篇第四」にある「勝者の戦いは、積水を千仭の谿に決するがごときは形なり」に因んでいる。「積水」とは「水豊ダム」のことであるとは定説となっている。[b]
(日窒鉱業)
日窒鉱業開発は国内に所有していた江迎炭業所(現・佐世保市)、土倉鉱業所(滋賀県長浜市)、秩父鉱業所(埼玉県)を継承し、1950(昭和25)年8月に日窒鉱業として再設立した。現在では「株式会社ニッチツ」となっている。
初代社長は永里高雄。父親は、野口遵が東京の飲み屋で意気投合して共に曽木電気を興した永里勇八である。
(扇興運輸商事)
日窒専属の物流会社「富田商会」が、戦後、日窒のマークであった「扇」を「再興」するという意味で「扇興運輸」と改名した。現在はセンコー株式会社としている。
(日之丸商会)
戦前は日窒が出資した肥料の代理店だったが、敗戦と同時に解散。1947年新たに再設立された。現在ではヒノマル株式会社となっている。
(新興電業)
水豊発電所の社長で、多くのダム・発電事業や鉱山開発を担当した久保田豊は、引き上げ後、吉岡喜一(後の社長)が社長に推薦したところ皆の反対を食らったという。そのせいかどうかは不明だが、日窒には留まらず、関係者とともに日窒を飛び出して「新興電業」を興した。1947(昭和22)年10月に日本工営株式会社とし、東南アジアを中心とした旧植民地の開発コンサルタントとして活躍し、「戦後補償」をビジネス化した。それはODA(政府開発援助)に継承された。
【会社の再建】
<特別経理会社の指定を受ける>
政府は企業を再建し健全な経済活動の復活を目指した。
多くの企業の再建の重荷となっていたのが、旧植民地の資産=負債であった。
政府は、1946(昭和21)年8月15日「会社・金融機関 経理応急措置法」を公布。
これらにより、同年8月11日時点で外地資産が10億円を超えていた起業は「特別経理会社」と指定された。当然、日窒は指定を受けた。
<旧勘定と新勘定>
そして、特別経理会社の指定を受けた会社(および資本金20万円以上の会社で、戦時補償請求権を有するもの)は、1946(昭和21)年8月11日を区切りに旧勘定と新勘定に分離された。
新勘定には、現金や国債などの流動性の高い資産が分類され、旧勘定にはそれ以外の資産や負債が分類された。
<戦時補償の打ち切り>
戦時中、日本政府は民間企業に対して軍需生産の未払い分や戦争保険金に関する補償を公約していたという。日窒を含む多くの大企業がこれを当てにしていた。日窒は総額で565億円にものぼっていた。
ところがGHQの「戦争による利得の除去」方針により、政府は補償はしない方針とした。政府は上記の法律とあわせて、1946(昭和21)年10月19日に「戦時補償特別措置法」を出し、戦時補償の支払いに対して100%の税率で課税し、全額回収することで、実質的に戦時補償はゼロとなった。
<企業再建整備計画>
さらに同時に、1946(昭和21)年10月19日に「企業再建整備法」を公布し、特別経理会社の指定を受けた企業は、企業再建整備計画を政府に提出し、監視を受けながら支援を得て、特別損失を処理していくことになった。
<集中排除法>
政府はGHQの指導のもと財閥解体を進めるために1947年12月「過度経済力集中排除法」を公布した。特定の企業や業種に対して直接的な再編成措置を講じることができる法律で、1948年2月8日、日窒も旭化成もその対象とされた。
<冷戦と紆余曲折>
そのため最初に練られた再建計画では、新会社を2つ作り、(旧)日窒を解散するという計画だった。(1947年6月)
やがてGHQと折衝を重ねながら、2つの新会社のうち1社は売却する計画になったりしたが、そのうち東西冷戦が明確になりアメリカの対日占領政策が変容してきた。1949(昭和24)年12月7日、過度集中排除法の指定が解除された。
<再び再建整備計画>
それで、当初の予定どおり「特別経理会社」として再建整備計画を立てることになった。
日窒は、新・旧勘定の分離を行ったところ、新勘定が水俣工場を中心に1億2241万円。旧勘定が14億3885万円であった。比率では7.8%:92.2%と、著しく旧勘定が多かった。
旧勘定には8億3116万円の特別損失が生じていた。
水俣工場をこの重荷から解放させるため、日窒が水俣工場を現物出資させ、新会社を設立するという方針を固めた。
【公職追放】
GHQが「財閥解体」とセットで行った占領政策に「公職追放」がある。
GHQは、1946(昭和21)年1月、”Removal and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office”「好ましからざる人物の公職罷免排除に関する覚書」を発した。
公職には企業等の「要職」も含まれていた。同月、日窒では1946(昭和21)年9月13日、榎並直三郎社長が「元日本火薬統制株式会社監事」として第一号となった。翌年2月にはほか7名が指定され、辞任した。
だから日窒の再建は、幹部の交代も同時に行われていた。しかし実際は引退幹部たちは「院政」のかたちで指示を下していた。
【新会社の発足】
1950(昭和25)年1月12日「新日本窒素株式会社」が資本金4億円で発足した。50円株を800万株発行した。
また同年5月の株主総会において、日本窒素株式会社の旧勘定の貸借対照表が承認され、解散し精算手続きに入った。
取締役社長には敗戦時興南工場で企画部次長であった北山恒が43歳で就任。副社長には吉岡喜一が就任。常務取締役のひとりには上野次郎男がいた。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔study1323:241010〕