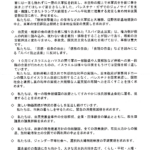M・バルガス・リョサ(ペルー、1936~2025)の人となり――権力構造の地図と、個人の抵抗と反抗、そしてその敗北を鮮烈なイメージで描く
彼は1936年3月26日、ペルー南部の町アレキーパに生まれた。ペルー第二のこの都市は母の故郷で、首都リマに対して根強い敵愾心を抱いていることでも有名。当時父母は折り合いが悪く、母親は独り帰郷して出産。翌1937年、彼女の父が領事としてボリビアに赴任するのに母子は同行し、以来1945年までボリビアで祖父母や母親と暮らす。
母や祖父母と共にペルーに帰国したマリオ少年は北方のピウラの町に移り住む。物心ついて初めて踏んだ祖国の地、このピウラの町は九歳の少年の前に驚異に満ちた新しい世界を開くことになった。多感なマリオ少年にとっては見るもの聞くもの全てが物珍しかったが、中でも砂原にぽつんと立っている緑色の建物が彼の心に強烈な印象を焼き付けた。
昼間こそひっそりと静まり返っているが、日が落ちると途端に灯火で明るく輝き、賑やかな音楽や嬌声が聞こえ始める。マリオを始め町の少年たちは好奇心に駆られ、近場の橋の上などからその模様を眺めた。町に住む顔見知りの大人たちが彼らの前を通り、こっそりあの建物の方に向かっていく。一体あそこで何をしているのだろう。大人に尋ねると、「悪いこと、罪深いことさ」と言われるか、問いをはぐらかされるのが落ち。
それまで赤ちゃんはコウノトリがパリから運んでくると信じていたマリオ少年の神話が崩壊したのはこの頃のことだ。いつしか<みどりの家>と呼ばれるようになったあの建物は、禁じられた蠱惑的な世界として少年の空想を掻き立て、彼の心に消し難い印象を残すことになった。
引っ越して一年目に、それまで長年別居していた父母が和解し、マリオは母と共に父の住むリマに赴く。死んだと思っていた父が生きていること自体大きな驚きだったが、実際に父と暮らしてみて一層深い失望感を味わうことになった。というのも、性格的に全く相反する父とは何かにつけて意見が合わず、同じ家で暮らしてはいたがまるで他人同士のように互いに不信感を抱き合っていたという。
幼い頃から物語小説を愛読していたマリオはピウラ時代から創作の真似事を始める。祖父母や伯父たちに励まされた彼は、リオに移ってからもこっそり小説を読んだり創作を続けた。祖父母に甘やかされたせいで息子には女々しいところがある、そう考えて常々苦々しく思っていた父は息子が文学にかぶれていると知って仰天する。
バルガス・リョサ自身も言っているように、識字率が低く、本を読む人、まして小説を手にする人などは殆どいないペルーのような国で文学にかぶれ、作家に憧れるというのはとんでもない話で、その意味では父の驚きも無理からぬところがあった。
父親は息子マリオの柔弱なところを直し、併せて文学とも縁を切らせようと考え、一九五〇年に、軍人の養成を目的とする厳格な規律で有名な<レオンシオ・プラード学院>に入学させる。彼自身もそういう学校に入れば何か得るところがあるだろうと考え、多少の期待を抱いて入学する。リマ市内の裕福な家庭の子弟から山間部の貧しい農民の息子に至るまでペルーの全階層の少年たちがひしめくこの学校は大変な処だった。
大半の教師は平気で生徒に体罰を加え、上級生は下級生を掴まえ、リンチにかける。生徒たちは陰ではタバコや酒を飲み、金を賭けて博打をする。野蛮な暴力と狡猾な知恵の支配する世界は、マリオにはとても耐えられなかった。彼は三年生でこの学校を中退するが、いつかこの体験を基に小説を書こうと心に決め、やがてそれが『都会と犬ども』に結実する。ビブリオテーカ・ブレーベル賞を受ける。将校らが反発し、本を焼却する騒ぎが起きて国際的な注目を浴びた。
1966年、ペルーのアマゾン地域などを舞台に娼婦、原住民、軍、僧院など五つの物語が同時進行するスケールの大きな作品『緑の家』を発表し、作家的地位を確立する。70年代に入ってからは、それまでのリアリズムによる全体小説的な作風が幾分変化し、軍隊社会を風刺したユーモラスな作品『パンタレオン大尉と女たち』(1973年)、どたばたする半ば自伝的な青春小説『フリアとシナリオライター』(1977年)などを発表している。
1974年にペルーに帰国し、翌々年に四十歳の若さで国際ペンクラブの会長に就任し、79年まで務めた。1981年、ブラジルのカヌードスの乱を題材にした『世界終末戦争』を発表。この作品で85年にリッツ・パリ・ヘミングウェー賞を受けた。
以後は民話の要素を作品に採り入れた『密林の語り部』(1987年)、ポルノグラフィックな『継母礼賛』(1988)などを発表。1993年にスペイン国籍を取得。翌年に『アンデスのリトゥーマ』などの作品で、スペイン語圏最大の文学賞セルバンテス賞を受けた。
多くのラテンアメリカ作家と同様に、社会や政治に対する発言を積極的に行っている。当初の左翼的なものから次第に保守的・自由主義的なものに移行。1990年には新自由主義的な改革を唱道する考えから、中道右派連合「民主戦線」よりペルーの大統領選に出馬。決戦投票でアルベルト・フジモリに敗れている。
2010年、ノーベル文学賞を受賞。1982年のガルシア・マルケスの受賞以来、長年にわたり有力候補とされ続けて後の受賞だった。ペルー国籍のノーベル賞受賞は史上初である。
2025年4月13日、リマの自宅で死去、89歳だった。
初出:「リベラル21」2025.5.15より許可を得て転載
http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6755.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14222 250515〕