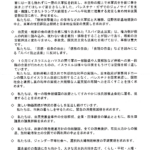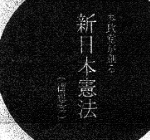討論集会は西川、本田お二方のじつに力のもこもった報告と、あの戦争の時代を身も持って体験された岩垂さんのコメントとで中身の濃いものとなった。
ただここでは「学問の破壊が戦争につながる」というサブタイトルについて思うところを述べておく。
「学問の破壊が戦争につながる」という一つの「命題」は20世紀以降の様々な戦争の経緯に照らして、妥当性は立証しがたい。「学問の破壊」なしに戦争に至ったケースの方がはるかに多い。
日本のかつての『大東亜戦争』遂行にあたって学問・思想の自由が著しく侵害されたのは、それが「白人帝国主義からのアジアの解放」という世界革命を目指すもので、その解放とは単に植民地支配からのそれだけではなく、「白人帝国主義世界観」ようは欧米の自由主義的資本主義、民主主義からの解放というイデオロギー戦争であったためである。共産主義、社会主義はいうにおよばず、リベラリズムまでやり玉に挙がったのはそのためだった。
そうしてみると、今般の「法人化」を直ちにかつての戦争体制と類比的に捉えるのは、いささか無理筋の発想なのではないか。
まずもって学問の自由は、どうして担保されなければならないか、学術会議の役割は
どう捉えるべきか。
私は経済から物を見るのが癖になっているが、それは政府からの中央銀行の独立性の問題とパラレルなように思える。
中央銀行が政府と独立でなければならないのは、そうでなく中央銀行が政府の言いなりになって安易に金利を引き下げたり、はなはだしくは国債の引き受け(いわゆる財政ファイナンス)をしたりしては、中央銀行が政府のポピュリズム政策の道具と化してしまうからに他ならない。中央銀行の役割とは、通貨価値の安定維持と場合によっては失業率の自然率実現なのだ。政府の恣意的政策の金融面からのサポートなんぞでは決してない。そんな基本中の基本のルールを鼻っから無視しているトランプがFRB議長の解任や金利引き下げを恫喝的言辞でもって迫っている事態を見れば、中央銀行の独立性の意義が逆照射されていることが知れてこよう。
それとパラレルで学問の自由、学術会議の政治からの独立性は一義的には学問それ自体の自由で健全な発展のために必須であるとともに、政権の恣意的政策の道具にならないためにも要請されるものだ、と考えるのが妥当だろう。その政権の恣意的政策の一つに時と場合よっては「戦争」が含まれてくる、こう捉えておくのが基本だ。
そう抑えたうえで、昨今の自民党政権下で進められてきた、安保法制や防衛費の飛躍的拡大などが、いかなる戦争を想定してのものなのか、そのことが次に考察すべき領域となる。それは、先に述べたような「白人帝国主義」の打倒を目指した「大東亜戦争」の再版であるのか、どうなのだろうか?むしろ戦後80年間、日本は全くの反転した位相、「白人帝国主義」にひたすら拝跪してきたことは指摘するまでもない。そこは明白だとして、では今ここで迫りくる日本の戦争とはいったい何のか、そのことの考察がこの討論会の報告やその後の質疑応答でもすっぽり抜け落ちていたように思う。
打倒克服すべき対象の不明なままでは、逆にいつの間にやら「戦争体制」に組み込まれしまうことも避けられない。
憲法第九条の現在的な意義をも含んで、ここは絶対に外せない考察領域であることを指摘しておきたい。
(感想おしまい)
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14229:250520〕