<はじめに>
1945年5月29日、ドイツの無条件降伏のすぐあとに、国民的作家トーマス・マンは、亡命先のアメリカで――と言っても1944年に帰化している――「ドイツとドイツ人」と題する講演をおこないました。英語での講演ということもあって、ドイツの精神史と破滅的な現在との関連について、内容的には深刻ながら、比較的平易に語られており、外国人にも理解しやすいものになっています。いま深刻といったのは、講演が、人類史上未曽有の大災厄となった第二次世界大戦の元凶である祖国ドイツについての反省と自己分析――ドイツおよびドイツ人たる自己――を主題とするものだったからです。それは期せずして、世界の多くの人々が抱いた疑問、つまりゲーテやベートーベンを生みだすような優れた文化芸術の伝統を持つドイツが、何ゆえにホロコーストのようなおぞましい悪魔的な戦争犯罪を犯したのか、という問いへの答えともなっていました。
マンの立ち位置は、よきドイツを代表するノーベル賞作家として、悪しきドイツを断罪するという一方的なものではありません。最初から戦闘的な民主主義者であったマンの実兄であるハインリッヒ・マンと違って、トーマス・マンは、第一次世界大戦中に出したその書「非政治的人間の考察」では、ドイツの文化的伝統の主流であるロマン派―それを最もよく代表するのは音楽精神であるとした―を擁護し、西欧文明や西欧デモクラシーに対して強い拒絶反応を示していました。しかし、ワイマール期には、徐々に民主主義の側に移行し、ナチス・ドイツの圧制や残虐さを目の当たりにし、亡命を経ることによって、決定的な回心を経験することになるのです。
その到達点からみたとき、ドイツの精神史がどのようにみえたのでしょうか。演説では、ロマン派文化とドイツ市民の政治生活は、一つのコインの裏表のように対応し合っており、それは市民革命の流産(典型的には1848年革命の挫折)によってつくられたいびつなドイツの精神的社会的構造の所産であるとしました。そして自分自身もドイツ人と生まれたからには、このドイツの運命と罪とに無関係ではありえない。それどころか、ドイツの運命と罪は、まさにマン自身において内なる矛盾――豊かな文化芸術的伝統への矜持と、惨めな政治生活への侮蔑とに引き裂かれた――として意識され、その克服に苦難の長い日々を必要としたのです。
マンの分析によれば、ルターの宗教改革に由来する精神的伝統としての「内面性Innerlichkeit」こそ、ロマン派的文化芸術と思弁哲学の肥沃な培養土でありました。しかし他方で、そこには政治的社会的要素が抜け落ちていた――ルター自身においても、解放者としての魂は農民一揆への憎悪と背中合わせだった。市民参加による自治という理念や、妥協による共同生活の巧みな処理能力に欠けており、ドイツ人にとって政治的なるものは、さもしい権力闘争――トランプ大統領が演じる貪欲、虚偽、欺瞞、破壊、反道徳的政治をみよ!――のイメージが湧くものでしかなかったのです。マンは、「一見思想的に深遠だが、世間知らず、この世離れしており、処世下手」と平たく述べていますが、いま風に言えば、公共的な生活が貧弱で、自由な社会空間形成ができていないということでしょう。大哲学者ヘーゲルに対しても、その自由概念は、ドイツ的現実において実際は自由でないことの裏返しなのだと、厳しい評価をしています。
ちなみに、ドイツ文化の特性を表わすものとして教養概念がありました。ヘーゲルがその市民社会論において市民としての成熟に必要な条件であるとした教養ですが、実際には政治的意味を抜き去られて内向きの精神文化に矮小化されてしまったと、マンは述べています。(大正時代の旧制高校的教養主義は、まさにドイツ的な教養を模範としており、特殊の媒介に欠けた普遍主義<人類主義>であり、社会批判の武器としては不十分でありました。次に来たマルクス主義は、その反動であるかのように教養青年たちの心をわしづかみにし、たちどころに政治青年を生み出しました)
その後、1871年に成立したビスマルクのプロイセン・ドイツにおいて、内面性とドイツロマン派の夢は、高度な技術と結びつき、好戦的な戦争国家として完成されていったといいます。プーチンのロシア帝国の見果てぬ夢が、世界一流の戦争の技術体系と結合して、危険な侵略国家へと肥大化するさまとよく似ているでしょう。日独伊の三国同盟において共通するのは、高い文化芸術的伝統をもちながら市民革命に失敗、権威主義的国家形成に道を譲らざるを得ず、社会・経済危機をファシズムで乗り越えざるをえなかったということでしょう。昨今の政治情勢をみていると、1930年代の危機の再来かと見えるところも多く、改めて当時の教訓を学び直す必要もあるのはないでしょうか。
さて、戦後のファシズムへの批判的省察ということでいえば、ドイツの同盟国であった極東の日本でも、敗戦の翌年に丸山眞男という少壮の学者が、「超国家主義の論理と心理」という論文を論壇に発表しました。その論攷は、戦争の精神的深手からまだ立ち直っていなかった知識人サークルに衝撃を与え、喜ばしい驚きをもって迎えられます。丸山は極東軍事法廷での裁判記録をもとに、超国家主義――アジア全域へと拡大した国家主義――へと突き進み、世界戦争を引き起こして破産した、軍国主義者たちの内的精神構造をみごとに解明してみせました。丸山が剔抉した三十年戦争の指導者たちの精神構造は、ドイツ的内面性ともナチ的な意志と決断の政治とも縁遠いものでした。決断の主体としての自覚なく、勢いのある流れに付和雷同し、したがって行為結果に対する責任の自覚に欠けた矮小な人間たちでした。そういう意味で、政治家というより、自惚れだけは肥大な小官僚的精神傾向の持ち主だったのではないでしょうか。
ただし、マンと丸山において診断が一致する点がひとつあります。マンによれば、ドイツ的自由は外に向かってのみ世界の奴隷化をめざして発露するものでしかなく、対内的にはドイツ人は不自由な国民でしかないといいます。同じような分析を、丸山はかの「抑圧の移譲」という概念を使って説明しました。市民社会が未成熟で国民が不自由な抑圧状態にあるところでは、上から下へと抑圧が順次移譲され発散される構造になっている。そのおかげで、不満が暴発せず国家内の均衡と安定が保たれている。――それがむき出しのかたちで露見するのが、旧軍隊の内務班生活でした。野間宏「真空地帯」や大西巨人「神聖喜劇」において、旧軍隊の愚劣さと残忍さと抑圧の移譲のさまをわれわれは追体験することができます。
ところが、その場合、社会の最下層に位置する人々には、国内では己の受けた抑圧の移譲先が見つからない。しかし「外地」へ派兵されたとき、兵卒たちは目の前にいる虐げられた弱者に、抑圧の格好の移譲先を見出すことになります。日本兵の残忍さは、非人間的な戦場での待遇からくるストレスもあります――旧日本軍にはローテーション・システムがありません。が、それ以上に、占領地にあっては国内で自分たちにのしかかっていた抑圧の全重量を一挙に転嫁し解消しようとする心理的メカニズムが起動すると考えられます。かつて、司馬遼太郎は江戸の侍社会においては、いじめは常態であったと語ったことがあります。いま、学校から企業社会へいたる日本社会において、いじめが横行する事態は、抑圧の度が増して社会が不自由になっていることの証でしょう。抑圧の最下層にいる社会的弱者への重圧は、刃をおのれ自身に向けるか、他者に向けるかして、いずれにせよ、どこかで暴発せざるをえないのです。そういう意味で、今日を戦前の再来、新しい戦前として捉えようとする試みは、間違ってはいないのでしょう。
トーマス・マン生誕150周年:反動派から反ファシストへ
――トーマス・マンの150回目の誕生日を記念して、彼が「ドイツの聴衆」に向けたラジオ演説が再放送された。そこでは、彼は反ファシズムの闘士としての姿を示している。
出典:taz.5.6.2025 Von Dirk Knipphals
原題:Thomas Manns 150. GeburtstagVom Reaktionär zum Antifaschisten
https://taz.de/Thomas-Manns-150-Geburtstag/!6088764
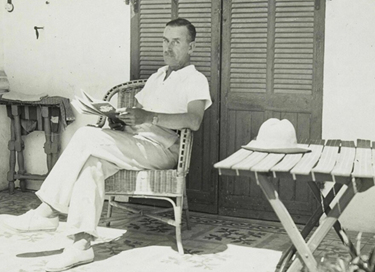
1933年の夏、トーマス・マンはフランスのサンナリー=シュル=メールで亡命生活を送り、その後スイスへ移動し、最終的にアメリカ合衆国へ移住した。Foto: ETH-Bibliothek, Zürich/Thomas-Mann-Archiv
ドイツ人の良心に語りかけ、揺さぶるのは、言葉だけでなく、彼の声でなければならない。彼自身の声。ナレーターが文章を読み上げるのではなく。彼にとってそれは重要なことだった。そのため、当時おそらく世界で最も有名な現役作家だったトーマス・マンは、1941年3月から毎月1回、ハリウッドの録音スタジオまで車で連れて行ってもらうようになった。彼は自分で車を運転しなかった。生涯を通じて運転免許を取得したことはなかった。妻のカティアが運転したり、娘のエリカが運転したりしたが、時々、運転手も雇った。録音スタジオで、この60代の作家は、当然ながらカリフォルニアのカジュアルな雰囲気の中でもきちんと服装を整え、マイクの前に座り、準備した原稿を読み上げる。彼は第二次世界大戦中ずっとそうし続け、さらに数ヶ月間、1945年11月まで続けた。BBCの外国語放送局は、毎回5分の放送時間を割り当てようとしたが、彼は英国放送局と交渉して8分まで延長し、完全に内容についての自由を確保した。この状況はその後も変わりなかった。演説はレコードに録音される。トーマス・マンが戻されるのは、最初は借りた別荘に、1942年からはロサンゼルスのパシフィック・パリスデーズにある1550サンレモ・ドライブの、亡命中に建てた別荘にであるが、その間にレコードは宅配便で空港に運ばれ、次の便でニューヨークへ送られるのだ。
敵のラジオ放送を聞くことは罰則の対象
そこでレコードは空港で受け取られ、ロンドンのBBCに電話回線が繋がれる。レコードが再生され、大西洋の向こう側で話された言葉が再びレコードに録音される。そして最後に、演説はトーマス・マンの声がドイツに放送される。ドイツでは敵対放送の聴取は違法とされており、妨害放送によって妨げられる。トーマス・マンの言葉を実際に聞いた人の数は不明である。これらの放送演説は、フィッシャー出版社により今春、『ドイツの聴衆たち!』というタイトルで再刊された。著者のメリー・キヤックによる刺激的な解説文と、最初の版への序文が収録されており、トーマス・マンは技術的な実現についても明らかな誇りを持って述べている。このレコードの旅路——カリフォルニアの太陽が降り注ぐ地から、ドイツ空軍によって爆撃されたロンドンまでの全行程——は、歴史的なミニシリーズの良い出発点となるであろう。亡命先からのナチス・ドイツとの闘い、カリフォルニアでの亡命生活全般、トーマス・マンのほかにベルトルト・ブレヒト、テオドール・W・アドルノなど多くの人々がいたが、いつか誰かがそのようなシリーズを始めるかもしれない。
ラジオでの演説は、作家のイメージに新たな一面を加える
演説は合計59件あり、決して未知のものではない。しかし、それらは長い間評価されてこなかった。実用的なテキストや付随的なテキストとして軽視されてきた。この機会に、6月6日にトーマス・マンの150回目の誕生日を迎えるにあたり、それらは彼のイメージに新たな側面を加えるだけでなく、この作家のイメージ全体を再定義したり、あるいはむしろ揺さぶったりすることができるかもしれない。そして、彼らは現在の状況において真の宝物である。強固なAfDとその他の政治的困難に直面しているからである。
トーマス・マンは演説の中で、ありったけの表現を尽くしている。彼はナチズムの「悪魔の汚物」と、それに対する「憎悪」について語っている。ヒトラーを「貧弱な歴史の偽造者で偽りの勝利者」と称し、「愚かな民族虐殺者」「吐き気を催すような」「空っぽの殻」「愚かな下品な存在」であり、「歴史の光が当たった最も忌まわしい人物」と表現している。ドイツを「民族の暴走者」であるとも。時折、彼は普段の文章では言葉一つ一つを慎重に選んでいる人物であるにもかかわらず、これらの演説では自身の嫌悪感を自由に表現したいという欲求に駆られているように感じられる。
ここでは、皮肉屋トーマス・マンが語っているわけではない。また、リューベックのブルジョア階級や戦前の山間のサナトリウムを舞台にした見事なシーンを描いた作家でもない。また、同性愛について多くの暗示や複雑な表現で回りくどく語る作家でもない。ここにいるのは、戦闘モードの作家である。1930年以降、ドイツでナチ党が帝国議会選挙で18.3%の得票率を獲得した頃には、ナチスは彼にとって単なる政治的対立相手ではなく、敵となった。これは、文学研究者カイ・ジーナが明快な研究『善と悪――トーマス・マンとしての政治活動家』で説明している通りである。しかし、これらのラジオ演説では、この「燃え上がる怒りの修辞」(マン研究者のディーター・ボルヒマイヤーの表現)に留まらない。トーマス・マンはドイツ人に戦争の経過についても報告している。ドイツ国防軍がまだ進撃を続けていた頃、彼は、ドイツ人たちが本当に勝利を望んでいるのかと尋ねた。「ヒトラーの勝利の結果として生まれる世界は、単なる普遍的な奴隷制の世界ではなく、絶対的なシニシズム(冷笑主義)の世界となるだろう」 戦争の潮目が変わった後、彼はドイツ人に対し、この犯罪的な政権下では平和は不可能だと警告した。
トーマス・マンは早い段階で聴衆にホロコーストを突きつける
1941年11月、彼は「ロシアで、ポーランド人とユダヤ人に対して行われた、そして現在も行われている『言葉にできないこと』」について言及した。そして戦争の進行に伴い犠牲者の数を次第に増やさざるを得なくなった彼は、聴衆に直接問いかける。「今、私の話を聴いているあなた、ヒトラーの絶滅収容所について知っていますか?骨粉から人工肥料が作られているのです」――アウシュヴィッツが時代の象徴となることは、彼にはすでに明白だったようだ。しかし、なぜどうしても彼自身の声が語られるべきなのでしょうか? 当初、演説の原稿はロンドンに送られ、そこで演説者が朗読していた。1941年2月の演説(朗読のみで行われた最後の演説)において、トーマス・マンはベルリンのスポーツパレスで行われたアドルフ・ヒトラーの演説に対する自身の印象を述べ、その際、嫌悪感を隠すことなく表現している。 「憎悪の叫び」と彼は書き、ドイツ語の「破壊」について言及している。彼はそれに我慢できない。 ドイツ語が、アドルフ・ヒトラーの騒がしい、演説で頻繁に声を張り上げる声と関連付けられることを、彼は許すことができない。したがって、彼は翌月すぐに自らマイクに向かって演説を行った。「今回は私の肉声を聞いてください。それは友人の声、ドイツ人の声です」と、演説の冒頭で述べる。
トーマス・マンの声とヒトラーの声
トーマス・マンの声対ヒトラーの声――まさに一騎打ちの対決だ。言葉だけではドイツの戦争機械に対抗できないことを、彼自身もよく知っている。しかし、彼は証言する。自らリングに上がり、ヒトラーの主張に反対する声を上げることで、彼はナチスがドイツ全体を代表する正統性を明確に否定している。この状況に至った経緯について考える際、彼はドイツに対して決して手加減しない。ナチズムは「ドイツの生活に長い根を張っている」と彼は述べ、その意味するところは、ドイツのロマン主義の特殊な道筋であり、その退廃的な形態は「常に殺人的な腐敗の種を内包していた」と指摘している。そしてさらに、「これらは、ドイツの技術時代への優れた適応力と相まって、今や文明全体を脅かす爆発的な混合物となっている」。ある意味では、彼は西側諸国との結びつきを予見している。カイ・シーナが示したように、彼はラジオ演説の文言ではなく、そのやり方において、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領とイギリスのウィンストン・チャーチル首相の演説をモデルにしていた。彼は、大衆への扇動を狙ったフェイクニュースやナチスのプロパガンダに、民主主義と戦闘的理性へのコミットメントをもって対抗している。
「ドイツ人である権利」
これらのラジオ演説に深く掘り下げてみる価値は、今でも十分にある。現在の状況下でも、強まったAfD(ドイツのための選択肢)に適用できる多くの論点が見つかるであろう。トーマス・マンが自由について書いたことは、まさに現代的な響きを帯びている。「ドイツの自由の概念は常に外向きのものでしかなかった。それは『ドイツ人であることの権利』、つまり『ドイツ人であること以外は何も望まない』という意味だった」。さらに、「彼は、国家のエゴイズムを条件付けたり制限したり、それを抑え込もうとするものすべてに対する、自己中心的な抵抗の概念そのものだった。」 さらに続けて、「外向きの反抗的な個人主義——世界、ヨーロッパ、文明との関係において——は、内面では奇妙なほどの自由の欠如、未熟さ、鈍い服従と共存していた」
――後略――
(機械翻訳を用い、適宜修正した)
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14276:250615〕






