日時:2025年9月20日(午後1時~5時)
場所:明治大学駿河台校舎 研究棟2階第9会議室
(講師1)白井 聡さん(政治学者、京都精華大学准教授) 「右派ポピュリズムの台頭と資本主義社会の持続可能性への懐疑」
・現代の右派ポピュリズムの台頭をどう見るか?
独(AFD)・仏(国民同盟)・英(リフォームUK)・米(トランプによる共和党)・
日本(參政党、日本保守党)
・共通点:既成政党の「外から」登場、外国人嫌い(具体的/抽象的)、グローバル化に対
する不満と反発
・要因:「リベラルなもの」への嫌悪感、知識人・エリートに対する反発、存続可能性への
不安=存在論的不安
・グローバリゼーションとは何であったのか?
資本の運動に対する制約解除―先進国における産業の空洞化・移民労働力の大量輸入
移民現象の本質:安い労働力を求める資本の欲動
・なぜ、リベラルは嫌悪されるに至ったのか?
リベラルとは:「社会民主主義」の呼び換え、階級闘争の後退、「階級」から「ポリティカ
ル・コレクトネス」「多文化主義」「多様性」「ジェンダー」「マイノリティ」へ、
アイデンティティ・ポリティクス
リベラルの敗北と勝利:資本主義批判の停止=新自由主義への屈服、「リベラルな価値観」
の公的機関への浸透、1968年革命の一帰結であり「勝利」。真の勝者は何(誰)か?
リベラルの倫理主義の浅薄性:ポリコレの笑止、多文化主義=移民推進
リベラルの倫理主義のウザさ:ウオーキズム、価値観の「アップデート」、「多様性」を唱
えながら不寛容、極限例としての「ノー・ディベート」~ポストモダニズムの一帰結
リベラルの大衆蔑視・傲慢:没落した白人労働者階級=ホワイト・トラッシュ、知識階級
を占拠
典型事例としてのトランスジェンダリズム(性自認主義)の文脈:後期近代の「何でも自
己決定」の極限、「性的なもの」の社会的位置づけの混乱
・「リベラルなもの」の日本的文脈
55年体制の終焉により野党勢力が「社会主義」を放棄・「リベラル」に転身
・「存続可能性への不安」・・・近代資本主義の前提条件の変化:人口増加の終わり=資本主義 の終わり→この不安をリベラルは無視し、彼らのコスモポリタンな「倫理」を主張。
* 以上を通して、白井氏は、いわゆる「リベラル(旧左翼)」の問題性を指摘した。
(講師2)住沢博紀さん(『現代の理論』DIGITAL代表編集委員 日本女子大名誉教授)
「20世紀の自由民主主義への収斂から、21世紀の拡散する民主主義へ」
上記の白井聡講師が、「現代の右派ポピュリズム台頭の、ある種の必然性と、それを促したいわゆる<リベラル派>の問題性を指摘した」のに対して、住沢博紀講師は、EU諸国あるいはイギリス・ドイツの議会選挙結果に見る右翼ポピュリスト政党の動向などを参照しながら、それでも、日本では、「18歳からの選挙権・被選挙権」施行などに踏み切り、「停滞した企業風土を変えることが大事であろう」と述べている。特に若い世代の役割が重要であり、「ポピュリズムに対抗できる若い世代へのアピール」として以下を強調した。
・日本のポピュリスト政策は結局失敗し実現できない。その結果としての無駄な時間と費用を認識すべき。
・何が本当の既得権で、何に生産的投資を向けるべきかを考えるべき。とりわけ若い世代への様々な人的投資を通じて、停滞した企業風土を変えるべき。
・外国人の「優遇」というデマに関して、外国人労働力は日本の経済的基盤になっていることに注目すべき。
・ポピュリスト政党のSNSに加担するのではなく、自らの世代の政策要求をとりまとめ、同世代のネットワークをつくり自分の政治的ハイマートを形成すべき。
さらに、「戦後世界の出発点となった日本国憲法は、今なお、あるいは今だからこそ有効。日本は普遍的な憲法的価値基盤があることに自信を持ち、権威主義化する世界に法治主義と多国間主義を訴えることができる」と強調した。
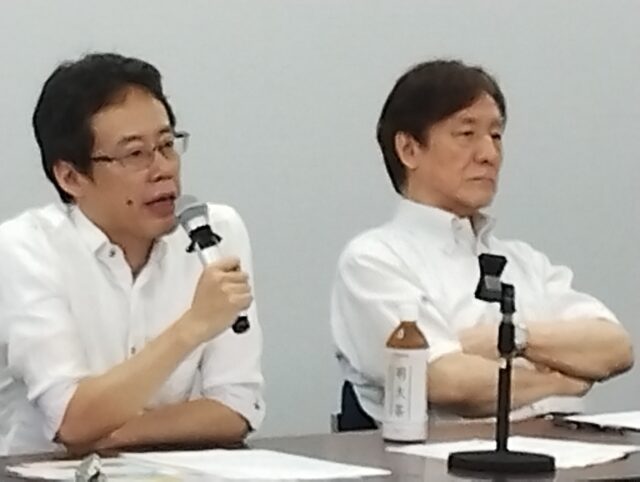
* 以上、二人の講師から、かなり異なる「右派ポピュリズム」への状況認識およびそれへの対応、が提起された。これらを受けて、より踏み込んだ議論が期待される機会であったのだが、残念ながら、残りの時間が限られていた。
ただ、この問題は、今後も引き続く現代の基本的な社会問題であり、老若ともに真剣に真向かわなければならない。その意味では、今回の討論集会を第一歩として、さらに継続的に議論を深め、「何を為すべきか?」を共に探っていかなければならないだろう。
(司会担当、池田祥子)
◆討論集会での講演、質疑、意見交換の模様は以下のユーチューブ(URL)からご覧ください。








