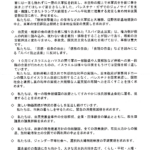2024年3月に、松竹伸幸氏が日本共産党を相手取っておこした訴訟は、氏に対する党の除名という処分が不当なものであるとして、それの撤回と復権を求めたものです。松竹氏の法廷闘争には、いわゆる左派系の著名な弁護士が弁護を引き受け、さらには内田樹氏らリベラル系の論客も支援活動に加わっています。この間の日本共産党の一連の国政選挙や地方選挙での大きな敗北については、先進国に共通する左翼リベラルの一般的な後退という世界同時的な趨勢と関連しつつ、松竹氏らの――YouTubeを駆使しての――こうした運動がボディブローのように効いているのではないかという印象をもちます。しかしそれに対する共産党の対処の仕方は、本来の支持者である左派リベラルの離反を招いているという問題の深刻さや、党の影響力の急速な減退という危機的状況に対応するものになっていません。かつてであれば、党の機関紙(誌)や関連雑誌で反撃の論陣を張ったでしょう。しかし、党勢の衰えは理論戦線でも顕著で、まともな反論もできず、嵐の通り過ぎるのをただ待つがごとき姿勢です。松竹氏に対する除名処分は、氏が異論を提起したからではなく、党の規律に違反したからというのが党の表向きの言い分です。具体的には、党内問題に属する党首公選制という組織改革案――共産党中央は党攻撃の文書としています――を勝手に外部で発表したことが、重大な規律違反行為にあたるとしたのです。しかし、外からの憶測の限りですが、組織内部で問題提起しても握りつぶされてしまうと考えたがゆえに、あえて危険を承知で、松竹氏は外部で発表する道を選んだのではないでしょうか。長く党本部に勤務し、政策委員会の安保外交部長でもあった松竹氏だけに、その辺の微妙な空気、党内力学を熟知していたはずです。この問題は一般社会組織における「内部告発」制度の設置などとリンクしており、ひとり政党の問題ではないので
す。

松竹伸幸氏の共産党除名撤回裁判の報告会。右から二人目が松竹氏。YouTubeから
このトピックに触れての私の最初の印象は、共産党は、コミンテルン時代からの組織文化をいまだに引きずっているというものでした。それは程度の差はあれ、中国共産党とも共通するもので、トップの独裁的采配、思想的不寛容、閉鎖性、自己中心的な党派性(セクショナリズム)、ジェズイット的規律、弱みを見せたがらない、政治的思想的道徳的に完全な党だと見せたがる見栄っ張りの党(前衛党意識の裏返し)などが、指摘できるでしょう。
共産党の組織文化に対する外部社会の関心は、いわゆる組織原則としての「民主集中制」の問題に集約されているといっていいでしょう。換言すれば、それは政党民主主義の問題であり、結社の自由の枠内で、民主主義をどこまで徹底できるのか、異論の自由や分派(少数派)の存在をどこまで許容するのか、という古くて新しい問題が提起されているのだと、私は理解します。
本論に入る前に、コミンテルン=スターリン主義的な政治文化から、今なお実質的な党首である志位和夫議長がどれほど自由でないかについて触れておきます。
以前、志位議長は、選挙での敗北を受けての責任の取り方という意味で、また長期政権の弊害という意味で、党首交代の可能性を問うた記者に対し、「党の方針が間違っていないのであるから、党首が交代する必要はない」と、記者会見の席で怒りをにじませて答えたといいます。党首がだれになろうと、それは政治結社の自由に属することであり、記者たちのような外部の人間からとやかく言われる筋の話ではない、というのが本音だったのでしょう。
志位氏のこの返答には二重の問題点があるように思います。まずひとつは、民主主義の本質にかかわる問題であり、二つめは、科学的認識論にかかわる問題です。
まず志位氏は「党の方針は間違っていない」としていますが、これは甚だしい独断です。そこには、間違っているのか、正しいのかを決めるのは自分たち前衛党の指導者であるという根深い優越意識がにじみ出ており、かつて前衛党神話として批判されたところのものです。また、科学的社会主義の立場に立つ自分たちが誤ちをおかすはずがないという独善意識、これを無謬神話といいました。かつてスターリン(主義)批判の際指摘されたこうした神学的属性から、日本共産党が依然として自由でないことを証し立てています。党の方針や政策に誤りがないとしたら、どうして敗北を重ね、長期低落傾向から抜け出せないでいるのか。常識的にみて、どこか方針に誤りや現状にそぐわないところがあるがゆえに、人々から支持されないのではと省みるのが普通でしょう。あるいはそうと考えてはいるが、どうしていいか分からないので、開き直るしかないのでしょうか。民意の大勢とのずれを自覚し、その根本原因を探り当て、新たな方針を立てる努力を率先して行うのが政党指導者のとるべき態度でしょう。十年一日のごとく党勢拡大を唱え、それが実行されない、あるいは成果が上がらない原因が、ひとり一般党員の怠慢にあるとするがごとき態度は、あまりに愚かで傲慢であり、指導者としての責任回避に映ります。政党の指導者が、もし政治的正しさへの接近に不可欠の民主主義的な熟議や自己検証、自己審査をネグレクトして、敗北の責任を取ろうとしないとすれば、それは重大な過ちで、その被害は党内的にも党外的にも甚大です。
二つめは、認識論に関わる問題です。
どうも志位氏には、個人的信念と客観的認識を混同する傾向があるようです。いわゆる科学的社会主義に不動の信念を持つのは、志位氏の個人的自由です。しかし政党の理念やプログラムは、個人的信念の源泉ではありえても、直ちにその真理性が保証されているものではありません。社会主義は歴史の必然であると力んでみても、現状ではそれを否定する(反証する)事実が山のようにあるわけですから、その正しさを論証し、人々を説得するのは容易ではありません。市民社会の自由な公共的な言論空間のなかで、実践的にエビデンス(観察や事実)によって検証され、専門家集団や一般の人々からその政治的正しさが認知されてはじめて真理の仲間入りをするのです。したがって信念は絶対的であり得ても、現実に開かれている限り認識にはどこまでも相対性がついて回ります。だからこそ、知的道徳的に謙虚さが必要なのです。松竹氏に対する共産党中央の態度は、中央に楯突く反逆分子は切って捨てるしかないという一方的断罪であって、とても熟議のうえの批判という代物ではありません。ガリレオ・ガリレイを断罪したカトリック教会の相貌に日本共産党のそれが似たようにみえてくるのは、避けがたいところです。
ヘーゲルとマルクスに共通する弁証法のコアな概念は「矛盾」です。矛盾こそ事物発展の原動力であるという彼らの教説に忠実であれば、党内矛盾は次のステップへのきっかけになるものです。矛盾を怖れ、異論を怖れ、多事争論を怖れるのは、スターリン的な一枚岩の党の亡霊に未だに憑りつかれているからでしょう。そして、それは前例踏襲の官僚主義と表裏一体のものなのです。いずれにせよ、1970年代初頭に、先進資本主義国における新たな変革の党として再登場したころの姿勢に比べると、政治的知的に大幅に後退した印象は否めません。
<政党法―政党政治確立のために>
日本には政党法が存在せず、そのためもあって民主主義的な党統治という面からみて在来のどの政党も不十分であり、とくに政治資金の不明朗な扱いが腐敗の温床となり、国民の政治不信のおおもとになっています。そのなかで例外的に厳密な党則の運用を行なっていると思われる日本共産党においてすら、除名や除籍問題において、民主主義や人権の侵犯・侵害と思われる事例が散見されています。つまり議会制民主主義のバロメーターである政党政治の成熟度は、全般的に依然低位の水準にとどまっているといっていいと思います。
この点に危機意識をもってでしょう、経済同友会は、2013年に「日本には政党を規制する公的なルールがないに等しい」として、政党法の制定を求める提言をしました。しかし、それから10数年経過した今日においても、党利党略が深く絡んだ仕方で政治資金、議員定数などの問題が、恣意的間歇的に話題になるだけで、本格的な政党法の論議はまったく不在です。
政党法については、ドイツが世界で最も先進的な例だと言われています。1969年に、ドイツでは政党法が制定され、すべての政党は、政治綱領、組織構成、党運営、人事、資金管理等、全てにわたって定められたルールを満たすよう義務付けられています。日本では、政党の党則にかかわる問題は政党の内部問題であって、公権力はそうした問題にいっさい介入すべきではないというのが、常識なようです。たしかに公権力が部分社会(政党、企業、諸団体)の問題にむやみ介入しないというのは、結社の自由や営業の自由を守るうえで当然のことでしょう。しかし部分社会の内部問題であろうとも、それが人権を損ねるような普遍性のある問題である場合、内部問題であっても公権力が介入して一定の裁きを下すことはありえることです。現に企業内での不当労働行為、ハラスメントや過重労働などの事例をみれば、明らかです。共産党は、そういう事例に対して「職場に憲法なし」と糾弾し、私企業内でも人権を守るべきことを日頃率先して強調してきた政党です。今日、いわゆる内部告発(通報)に対し、通報者を保護する「公益通報者保護制度」が設けられたのも、組織の内部問題という逃げ口上で人権侵害を放置するのを許さないためなのです。また医療機関などでは、倫理審査委員会や救済委員会などが設置され、自己審査機能を強化するのが、当たり前の世の中になりつつあります。まして政党は公益性に強く関わる組織であり、それだけに私党ではなく公党としての自覚と義務意識が必要なのです。
ドイツの場合、政党への助成金交付とからめ、各政党に公党としての義務を課しました。ドイツの政党法における対処のしかたは、なかなか優れたものです。政党法という法律で、民主主義の観点からどのような政党であろうと遵守すべき規準を設け、それにその枠組みに則って各政党が結社の自由な活動を行使するという二重構造になっています。つまり公権力である裁判所が党内問題に直接介入するのではなく、党内に審級制の仲裁裁判所を設置することを義務づけて、自主的かつ公正に党内紛争の処理ができる仕組みをつくり上げているのです。公権力は、政党が仲裁裁判所の運用を正しく行なっているかどうかをチェックするだけであって、裁定の内容には不介入です。
この立法の背景にある考え方は、ひとつのまとまりのある政治結社といえども、多様な意見や異論の存在は不可避であるということでしょう。それを非和解的な対立に至らしめずに、当事者が極力納得できるかたちで処理し統一を確保する――そのための適法的システムとして仲裁裁判所を設けるということでしょう。
以下、ドイツ政党法と、それの「緑の党」による応用例の、ほんの一部を紹介します。
<ドイツ政党法>
第 7 条 構成
(1)政党は、地域支部により構成される。各地域支部の規模及び範囲は、党則に規定する。当該地域の構成は、個々の党員が政党の意思形成に適切な協力をなし得る程度に完備されたものでなければならない。政党組織が一の都市州の領域に限定されている場合には、地域支部を設けることを要せず、この場合は、その組織がこの法律でいう政党である。地域支部間の組織上の連合は、党組織の団体としての可能な構成を著しく妨げない限り、許される。(強調 筆者)
第 10 条 党員の権利
(1)政党内の所轄機関は、党則の細目規定により、党員の入党について自由に決定する。入党申込みの拒絶は、明示の根拠を要しない。一般的に入党を禁止することは、期限付きのものであっても許されない。判決により被選挙権又は選挙権を喪失した者は、党員になることができない。
(2)党員及び政党の各機関の代表者は、平等な表決権を有する。表決権の行使は、党則の細目規定の定めるところにより、党員が党費を完納していることを要件とすることができる。 党員は、いつでも直ちに離党する権利を有する。
(3)党則には、次に掲げる事項について規定しなければならない。 1. 党員に対して採り得る規律 2. 規律措置を正当とする根拠 3. 規律措置を命じることのできる党機関党務から解任し、又は党務就任資格を剥奪する場合においては、その議決には理由を付さなければならない。
(4)政党は、党員が党則を故意に犯し、又は著しく政党の基本原則若しくは秩序に違反し、 かつ、それによって政党に重大な損害を与えた場合に限り、当該党員を除名することができる。
(5)除名については、仲裁裁判所規則の定める所轄の仲裁裁判所がこれを決定する。上級審たる仲裁裁判所への控訴は、保障されなければならない。決定は、文書でその理由を付して行わなければならない。直ちに措置することを要する緊急かつ重大な事態の場合には、政党 又は地域支部の理事会は、仲裁裁判所の決定があるまでは当該党員の権利行使を差し止めることができる。(強調 筆者)
――中略――
第 14 条 政党仲裁裁判所(Schieldgericht)
(1)政党又は地域支部と個々の党員との紛争並びに党則の解釈及び適用に係る紛争を調停し、裁決するために、少なくとも政党及びそれぞれの最上位地域支部に仲裁裁判所を設置しなければならない。郡段階の 2 以上の地域支部のため、共同の仲裁裁判所を設置することができる。
(2)仲裁裁判所の構成員は、最高 4 年の任期で選挙される。仲裁裁判所の構成員は、政党若しくは地域支部の理事会の構成員、政党若しくは地域支部と雇用関係にある者又は政党若しくは地域支部から定期的に収入を得る者であってはならない。仲裁裁判所の構成員は、独立であって、いかなる命令にも拘束されない。
(3) 仲裁裁判所には、一般的又は個別的に、争いの当事者が同数を指名する陪席員を置く旨を党則で定めることができる。
(4) 仲裁裁判所の活動のために、当事者に対し、法律上の聴聞、正当な手続及び不公平のおそれがある場合の仲裁裁判所の構成員の忌避を保障する仲裁裁判所規則を定めなければならない。
―――仲裁裁判所には中央や州組織の幹部や利害関係者は、のぞかれるとしています。日本共産党のように中央幹部が規律委員会を実質的に仕切るのであれば、処分する側に有利な裁定を下すことは不可避です。たんなる不服申し立てではなく、上級裁判所への控訴権も保証しているのは、意義あることです。(N)
<「緑の党」の規約抄>
§2仲裁裁判所(Schieldgericht)
(1) 連邦党組織および州党支部には仲裁裁判所が設置されている。郡党支部レベルでも、郡党仲裁裁判所を設置することができる。仲裁裁判所の任務は、以下のとおりである。
1. 党員間、党機関間、党員と党機関間、あるいは党機関と連合機関間の紛争について、党の利益が影響を受ける場合、その調停または決定を行うこと。
2. 地域支部、党機関、団体の機関または個々のメンバーに対して懲戒処分を課す。
(2)政党組織の役員、あるいは政党に職業上または経済上の依存関係にある党員は、仲裁人になることはできない。仲裁裁判所の全構成員は独立しており、指示には拘束されない。また、解任されることもない。
(3)連邦仲裁裁判所は、原則として、1名の議長と4名の評議員で構成される。議長と2名の評議員、および2名の代理人は、連邦党員総会議会によって2年間選出される。その他の評議員は、紛争当事者がケースバイケースで指名する。選出された評議員のうち1名は、連邦党員総会によって副議長に指名される。仲裁手続きの実施は、仲裁規則によって規定される。
(4)連邦仲裁裁判所は、以下の事項について裁定する。
1. 州仲裁裁判所の決定に対する不服申立て
2. 連邦党組織と地域支部間の紛争、連邦党組織と連合間、州党支部間の紛争、同一の州党支部に属さない地域支部間の紛争、および上記党機関間の紛争
3. 連邦機関による選挙および決定に対する異議申し立て
4. 個別の場合において、本来管轄権を有する州仲裁裁判所が適切に構成されていない場合の州仲裁裁判所の指定。
(5)州仲裁裁判所は、以下の事項について決定する。
1. 地区仲裁裁判所の決定に対する不服申立て
2. 連邦党理事会の理事に対する懲戒処分、州党支部の機関およびその構成員に対する懲戒処分、ならびに地区党および地区支部の解散
3. 連邦仲裁裁判所も地区仲裁裁判所も管轄権を有しない、あるいはこれらが適切に構成されていないすべての事案。
連邦党理事会の理事に対する懲戒処分については、当該理事の居住地を管轄する州仲裁裁判所が管轄権を有する。
§3 平等な参加資格
(1) 政治における女性の平等な参加は、BUNDNIS 90/DlE GRÜNEN(同盟90/緑の党―党の正式名称)の政治目標である。公職および議員職の最低割当は、この目標を達成するための手段の一つである。「女性」という用語は、 自らをそう定義する者をすべて含む。このこと、およびその他の措置は、女性に関する規定で定められている。
(2) BUNDNIS 90/DlE GRÜNEN および BUNDNtsg}/DIE GRÜNEN の旧委員会、および派遣される委員会は、少なくとも補助として女性で構成され、女性候補者は、リスト選挙および選挙候補者名簿において、奇数番号の順位を確保される(最低割当)。選挙手続きは、女性のためのポジションと、すべての候補者(公開ポジション)のためのポジションを区別して投票が行われるように設計されなければならない。女性のみで構成される委員会や機関も認められる。既存の連邦機関、委員会、連邦作業部会も、少なくとも 50% を女性が占めるように構成されなければならない。この規則の例外は、BAG Schwulenpolitik(同性愛政策)である。
(3) 女性の平等な参加と同様に、ジェンダーの多様性の認識も、BUNDNIS 90/DlE GRÜNEN の目標である。トランスジェンダー、インターセックス、ノンバイナリーの人々は、当党において平等な参加権を得るべきである。すべての 委員会および会議は、この目標を尊重し、強化することが求められる。
――ジェンダーフリー、女性党員の積極的登用などが際立っています。(N)
§11 組織構造(Strukture)
(1)分権型の党組織と草の根民主主義(Basisdemokratie)を発展させるため、党規約は、地区、郡、州の各組織に最大限の自治権を規定している。決定機関は、それぞれの党大会および代議員総会である。
(2)郡委員会および州委員会は、そのプログラム、規約、財政、および人員に関して自治権を有する。そのプログラムおよび規約は、連邦組織の基本的合意に反してはならない。
(3)BÜNDNIS90の元メンバーは、「市民運動」と呼ばれる内部組織を結成する権利を有する。この組織はすべてのメンバーに開放されている。
――上意下達型の組織構造を排し、下級組織の権限を大幅に認めていることは画期的です。(N)

「緑の党」の規約文書(2021年版)
§15 女性評議会(Frauenrat)
(1)女性評議会は、連邦党員総会間の党の女性政策の指針を決定する。
女性評議会は、連邦党、議会グループ、州党支部の各機関間の活動を調整する。共同の政治的イニシアチブを立案・企画する。連邦党理事会に助言し、連邦党員総会から委任された事項を処理する。
(2)女性評議会は、以下の者で構成される。
1. 連邦党理事会の女性メンバー
2. 各州協党支部からの女性代表2名(うち1名はLAG女性によって指名される)。党員数が4,000人を超える州党支部は女性代表を1名追加派遣し、党員数が8,000人を超える州党支部は女性代表を2名追加派遣する。州党員総会における女性の投票に反して、女性評議会に女性が選出されることはない。
3. 連邦議会会派の女性議員2名、および欧州議会における同盟90/緑の党グループの女性議員2名。これらは、会派およびグループから派遣される。
4. 労働共同体女性政策およびレズビアン政策から、それぞれ2名の代表者(連邦労働共同体によって指名される)
5. 緑の青年連邦連盟の女性メンバー2名
6. 連邦党女性担当官、州党女性担当官、および連邦議会女性担当官(諮問権を有する)
(3)女性評議会の全メンバーは、BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN(同盟90/緑の党)の党員でなければならない。
(4)女性評議会のメンバーの任期は2年であり、再選は可能である。
(5)女性評議会は、少なくとも年に2回開催する。連邦党理事会が招集する。さらに、メンバーの5分の1または連邦党理事会が要求した場合、女性評議会は追加会議を開催する。
(6)女性評議会は、原則として女性のみが公開で会議を行う。ただし、単純過半数により一般公開を排除することができる。
(7)女性評議会は、その運営規則を定める。
<最後に>
私は法律関係については全くの素人なので、誤解や理解に行き届かない点があるかもしれません。その場合は、ご容赦ください。
共産党の民主集中制の組織原則でもっとも問題だとされていることのひとつは、組織が完全に垂直構造になっていて、異なる支部に属する党員は、相互に連絡を取りあったり、なんらかの連携行動に出ることは禁じられていることだとされています。党内に分派をつくらせないための措置であり、指導部は現行の路線と異なる世論形成が党内で進むことを極度に恐れていることの現れでしょう。ドイツ政党法でもこの点の直接の参考になる文言はないようです。ただ、「第7条 構成」の部で、「地域支部間の組織上の連合は、党組織の団体としての可能な構成を著しく妨げない限り、許される」とあります。断定はできませんが、党組織の水平構造を許容するものかもしれません。緑の党の規約には、これに対応する文言はありません。まだまだ研究の余地はありそうです。
「緑の党」は、もともとは保守系の環境政党だったのですが、70年代以降、68世代が加入戦術で大挙入党し、環境問題はもとよりジェンダーフリー運動の旗振り役となりました。その伝統を受け継いで、党則に女性党員の権利保障を色々なかたちで明記しています。
ドイツに政党法があるからといって、議会政治がなにもかもうまくいっているわけではありません。しかし政党の統治に共通の一般的規準を設けることによって、政党間の無用な摩擦や誤解が回避でき、その結果連立政権が継続的に成立してきたとも考えられます。いずれにせよ日本の無法状態は、政党の成熟を妨げ、政治腐敗を生み出す元凶ですから、政党法についての議論が進むことを願っております。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14536:251122〕