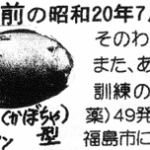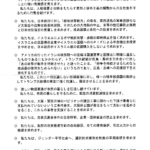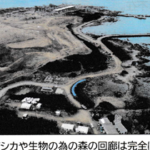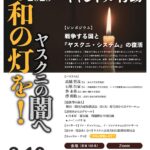――八ヶ岳山麓から(529)――
中国共産党機関紙人民日報の傘下紙である環球時報は、6月23日、英紙フィナンシャル・タイムズを引用して最近のトランプ米大統領による関税攻勢とアメリカの防衛予算増額要求に対する日本側の態度を分析した論評「なぜ日本はアメリカに対して頻繁に『NO』をいうようになったか」を掲載した。筆者は上海外語大学日本研究センターの主任教授廉徳瑰氏である。以下はその概略である。
英紙フィナンシャル・タイムズは、最近日本方面の 「消息筋」の話として、アメリカ政府が突然日本に防衛費の増額を要求したことに東京が 「激怒」、7月1日に予定されていた外交・防衛に関する日米「2+2」会談を取消したと報じた。このニュースは日米両国によって公式に確認されたものではないが、「日米間のギャップと溝がますます目につくようになっているのは確かだ」と報じている。
それによると、アメリカは重要な同盟国のひとつである日本に「寛大な態度」をとらないものだから、東京は失望している。日本政府は当初からアメリカ側に「絶対に屈しない」という強硬姿勢を示しており、関税問題でアメリカが広範な国際的批判と圧力に直面しているのを見て日本も遅延戦術をとり、その後の交渉で一定の優位に立つことを期待している。日本は関税問題で対米「強硬」な態度であるが、防衛費問題でも「不服従」の態度をとり対米交渉のカードを増やそうとしている。
防衛費の問題が日米間の新たな摩擦点になっているのは、意外でも何でもない。1947年に施行された戦後の「平和憲法」に従い、日本は長い間「専守防衛」を基本的な国是としてきた。1976年には時の首相三木武夫が防衛費はGDPの1%を超えないという原則を定めた。
しかし、国内政治が右傾化するにつれ、1980年代、「戦後総決算」を謳う中曽根康弘政権は、1%制限を撤廃することを提案した。しかし、財源の問題もあり日本の防衛費の対GDP比は以後1%を超えていない。だが2022年に至り、岸田文雄政権が「近隣諸国における安全保障上の脅威の増大」を口実に、2027年までに防衛費をGDPの2%に引き上げると発表した。
2%に引き上げるとしても、そのカネはどこから出てくるのかが常に問題になっている。2021年以降、日本の実質GDP成長率は年率1~2%程度に過ぎず、防衛費の増加は経済成長率をはるかに上回り、日本の財政に大きな負担をかけるうえに、為替変動と物価上昇が日本政府の資金調達難をさらに高めている。
まさにこの時、アメリカ側はまず防衛費をGDPの3%に引き上げるよう日本に要求し、その数日後にはこの数字を3.5%に引き上げるよう口を滑らせた。このような「口利き」は、日本政府内に広範な不満を即座に引き起こした(6月24日、林官房長官はアメリカの3.5%要求を否定した)。
(日米間の認識の)格差と亀裂の拡大が、ワシントンは「頼りにならない」との認識を広げてはいるものの、日本は長らく日米同盟を外交戦略の基軸としてきたのであり、この種の惰性を取り除くことは難しいだろう。しかし、日米同盟における日本の不平等な地位に対する不満は明らかになりつつあり、日本の政界や社会では対米「平等権」を求める声が高まっている。
現職の石破茂首相は、選挙期間中に早くも、日米間の地位同等を実現するために日米地位協定の改定を目指すと発言した。関税と防衛費の組み合わせは、間違いなく米国にいじめられている日本の「憤り」を増大させ、それゆえ米国との「対等な権利」を求める声に貢献するだろう。
現在、アメリカ政府の外交戦略は混乱している。広く批判を浴びている関税問題だけでなく、防衛費のような問題がNATO同盟国だけでなく他の非NATO同盟国からも強い反発を招き、今また中東に軍事介入する行動に出ている。米国の国際的イメージがさらに悪化し、その影響力が相対的に低下していくなか、日本はワシントンの思い通りにはならない「チャンス」を見出しているのかもしれない。
もちろん、日米同盟に「亀裂」が生じれば、「NATOのアジア太平洋化」のプロセスに影響を与えることは避けられない。近年、米国のアジア太平洋政策の進化と調整の産物である「インド太平洋戦略」に加えて、「NATOのアジア太平洋化」はアジア太平洋地域における米国の軍事的、全体的な戦略の動きを見るうえで重要な参考資料である。
ヨーロッパ諸国と日本の関係について、これは2つの観点から見るべきである。一方では、米国はアジア太平洋地域におけるプレゼンスが低下していると感じており、単独でアジア太平洋地域における絶対的な優位を維持することは困難である。このため、NATOにアジア太平洋地域へ手を伸ばすよう求めている。
すでに米・欧関係における劇的な動揺は、NATOの欧州主要同盟国の米国に対する安全保障上の依存関係を損ないつつある。国防の自主性を求める動きがさらに強まるにつれ、欧州諸国は今後、二国間レベルでもNATOの枠組み内でも、ワシントンに対する反発をより強く表明するようになるだろう。
同じ理由によって、日本はよりバランスの取れた外交を模索せざるを得ない、そのひとつの表れが、米国に対する「NO」の頻度の増加かもしれない。大西洋関係におけるやり取りが激しさを増したように、日米同盟間の分裂、亀裂、引っぱりあいも激しくなるだろう。この関係の変化がもたらす影響は、今後の二国間や地域の情勢の変化の中で徐々に明らかになるだろう。
おわりに筆者(阿部)から一言
石破首相は2月の日米首脳会談で、「防衛費増額はアメリカに言われてやることではない。日本が自らの責任において決断すべきものだ」と言った。その後コルビー米国防次官の「日本の防衛予算はGDB比3%に」という発言があったが、石破氏は3月5日の参院予算委員会でも同じ発言をくりかえした。これは大いに結構だが、赤沢亮正経済再生担当相は、7回目の対米交渉に出かけるが、「五里霧中」というだけで、交渉への構えは卑屈、低姿勢という印象しかない。
廉徳塊氏は「日本は関税問題では対米『強硬』な態度であるが、防衛費問題でも『不服従』の態度をとり対米交渉のカードを増やそうとしている」という。どう見てもこれは見間違いである。また最近のNATO首脳の発言を見ると、NATOがトランプ氏に反発するだろうという評価も間違いだ。
廉徳瑰氏の主張について、友人2人に感想を聞いてみた。S氏は「トランプ政権が今以上に目に見える形で日本を支配しようとすれば、日本人の『憤り』は徐々に芽生え、『日本の自立』へむけての動きが始まるのではあるまいか」「戦後100年を迎える前に『アメリカ従属』から自らを解放し、『独立国日本』を勝ち取る流れを掴みたい」と言った。
Y氏も同じ趣旨で、「この論考は中国共産党政権の間にある一種の『願望』を表現しているのではないか。つまり『アメリカ離れ』『中立化』である。日本の西南諸島の軍事力強化は、中国の軍事負担を増加さていることは確実だから」「日本が対米自立していくためには、中国のこのような日本への『期待』は利用価値があるのではないか。だが、中国の希望が実現する可能性は当面は低いだろう」という。
トランプ政権は、パレスチナのジェノサイドといい、イランへのミサイル攻撃と「無条件降伏要求」といい、国際法も何も無視してめちゃめちゃなことをやっている。日米交渉でも無理難題をふっかけてきたら、長年対米従属に甘んじてきた日本人も、廉徳瑰氏の期待に少しは応えるかもしれない。 (2025・06・25)
初出:「リベラル21」2025.6.30より許可を得て転載
http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6798.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14302:250630〕