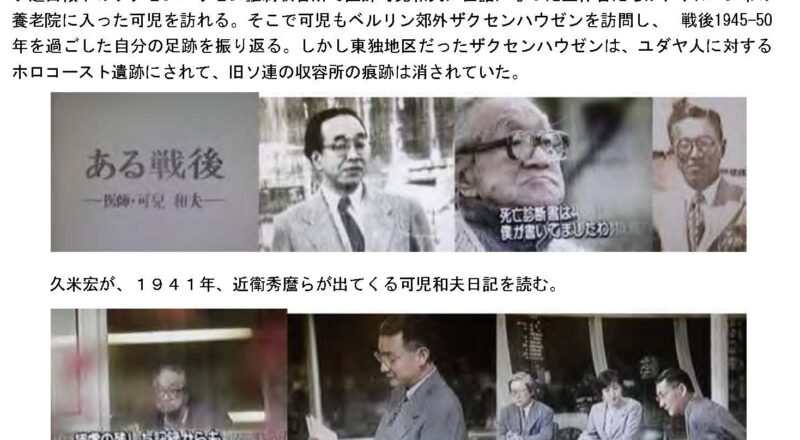2025.7.2 ● 更新用パソコンのDeramweaverがいきなりショートし、ほとんど完成していた7月1日付け本文が失われました。いくつかの深刻なハグも見つかり、ソフトの再インストゥール。1日遅れの更新です。異常気象によるものでしょうか。日本ばかりでなく、世界全体で酷暑の夏が到来しているのを見ると、この「異常」こそ正常で、これまでの「正常」の座標軸が変わったのではないか、と思わざるをえません。政治の世界でも、そうです。19世紀から20世紀・21世紀と積み上げてきた国際協調の世界秩序が、一人の政治家の狂気のきまぐれによって、破壊されようとしています。「正常と異常」と同じように、「正気と狂気」の分界線が、壊れたかのようです。「戦後80年」の日本の行方は、世界史の大波に翻弄されています。
● そのもとで、「戦後80年」を考えるには、一度30年前の1995年「戦後50年」に立ち戻って、そこで何が語られ、何が見逃され、何が受け継がれたかを確認すべきではないか、というのが、私が7月1日付け原案で書いていたことです。理由は、二つありました。一つは、「戦後50年」には、1945年敗戦時に20歳だった人が70歳になり、原爆・空襲・疎開などの被害体験ばかりでなく、朝鮮・台湾の植民地支配、大陸での三光作戦・細菌戦・毒ガス戦、名誉の戦死どころか食糧補給もなかった空腹・飢餓と感染症の蔓延など、加害体験を含む悲惨な戦争体験を多くの人々が語るようになり、新聞・雑誌・テレビでも、多くのドキュメンタリー、手記・証言が発表されました。その数は膨大です。朝鮮半島や中国・台湾・東南アジアからの、日本の加害の記録も多く、蓄積されてきました。
● しかも第二に、その5年前の竹下内閣期の全国全市町村に各1億円をばらまく「ふるさと創生事業」の一部として、金塊1億円や箱物作りとは異なる無難で堅実な使途として、自治体史編纂が進められていました。その村の歴史、町の歴史に、多くの普通の人々が、ひもじく厳しかった戦争体験と対照的な、戦後の高度経済成長と「豊かさ」を上塗りし、郷土史の近現代編や自治体広報などでも、無数の記憶・証言が文字や音声・映像になり、記録に残されました。体験を語る生存者が高齢化し数少なくなった「戦後80年」には、その貴重な生き残りの記憶の記録化も重要ですが、1995年が阪神淡路大震災・オウム真理教事件の年であったとともに、「インターネット元年」「ボランティア元年」であったことを想い起こし、30年前の貴重な証言・記録を再検証するとともに、生成AIをも使って膨大なデータの保存・数量化・分類、公共的デジタル・アーカイフ構築が可能となるのではないか、という問題提起です。
● その実例として、私自身が取り組んでいるのは、ちょうど30年前の1995年6月1日のテレビ朝日ニュースステーションで放映された、「ある戦後50年 医師・可児和夫」という番組の主人公「可児和夫」の探索です。可児和夫は、1904年岩手県生まれ、旧姓盛岡中学(現盛岡一高)から東京帝大法学部卒、さらに九州医専(現久留米大学医学部)で医学を学び、妻子を日本に残して1936年ドイツに留学、在ベルリン日本人会主事から、第二次世界大戦中は中外商業新報(現日経新聞)、朝日新聞のジャーナリスト、1945年5月ドイツ敗戦時は読売新聞特派員でした。在欧日本人のほとんどは、シベリア鉄道・満州国経由日本へ帰国しましたが、可児和夫は、音楽家近衛秀麿らとともに、ドイツに残りました。そこでソ連軍に捕まり、1945年7月から50年2月まで、ベルリン近郊のもともとナチスの強制収容所をソ連軍が占領して受け継いだザクセンハウゼン捕虜収容所で、まともな尋問もなしで長い収容所生活を送りました。東西ドイツ分裂国家成立で、50年にようやく解放され、日本の家族と連絡もとれましたが、そのまま毎日新聞初代ベルリン特派員として、東のベルリンから西のボンに移って残留、西独では、日本大使館のドイツ語の仕事やドイツのラジオ・テレビ放送に日本通の評論家として出演、ついに日本には一度も帰らず、ケルンでベルリンの壁崩壊、ドイツ統一を見て、1996年に死去しました。貴重な戦争・捕虜体験と数奇な人生を歩んだ日本人です。
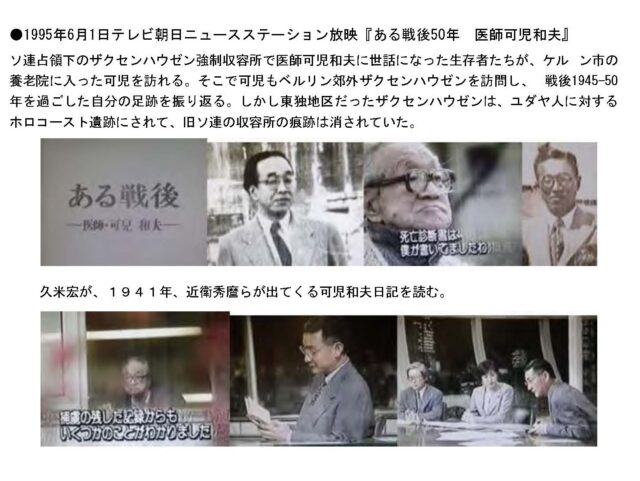
● 可児和夫の戦後ソ連軍占領によるザクセンハウゼン収容所体験は、『文藝春秋』1951年2月号に、可児自身の手記「一日本人の体験した25時ーー東独のソ連収容所の地獄の記録」として発表されました。そこで医師として多くの捕虜を励まし生きる希望を与えたことが、ドイツ語でも報道されました。幼時に日本で分かれた息子の可児秀夫は、江戸川乱歩賞作家「梶龍雄」になり、多くの推理小説をドイツの瞼の父に贈りながら、1990年には亡くなりました。ちょうど東欧革命・冷戦崩壊からドイツ統一の時期で、かつてザクセンハウゼン収容所で可児和夫に救われた人々が、可児の所在と存命を見出し、ドイツのメディアで大きく取り上げられました。1995年6月、久米宏・小宮悦子のテレビ朝日ニュースステーション「戦後50年」特集で、同じ体験をした収容所の旧友たちとの再会と、車椅子でのザクセンハウゼン収容所跡地(現追悼博物館)再訪が、実現しました。同年12月8日、日米戦争開戦の日の『日経新聞』文化欄には、可児和夫を「ドイツの父」として慕ってきた在独日本人ジャーナリスト中島英子さんの「絶望収容所に温顔の医師」という記事も、掲載されました。その中島さんが、翌96年の可児和夫の死後、多くの資料と日記を遺贈され、その生涯全体を調べて、30年後の「戦後80年」に、記録に残そうとしています。
● たまたま私が日独関係史を研究・執筆し、しかも可児和夫と同じ盛岡一高出身ということで、本「ネチズンカレッジ」経由で、著名なピアニスト、スタニスラフ・ブーニンの日本人夫人となった中島英子さんから、可児の岩手時代の調査依頼がありました。それを、岩手在住の元毎日新聞記者であった私の友人に協力してもらい、宮沢賢治の弟・清六と旧制中学で同級であった可児和夫の、誕生から青年時代が、ようやく明らかになりました。その中間報告は、この友人の力を得て、『岩手日報』2022年2月20日付けの大きな記事になりました。中島ブーニン英子さんの可児和夫評伝も、ようやく書物になりつつある「戦後80年」の6月、ここ数年癌と闘病してきた友人は、力尽きて、天に召されました。本カレッジの熱心な読者で批評家でもあった友人の死は、私にとって大きなショックで、かけがえのない喪失です。3年ぶりで東北新幹線に乗り、友人のキリスト教花巻教会での葬儀にでてきましたが、同じく闘病中・リハビリ中の私にとっても、心身の負担の大きい、いのちの重みを考える「戦後80年」の旅になりました。本カレッジの今後についても、改めて、考えていくつもりです。
初出:加藤哲郎の「ネチズン・カレッジ』より許可を得て転載 http://netizen.html.xdomain.jp/home.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔eye5981 : 250703〕