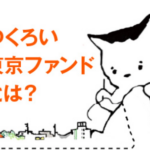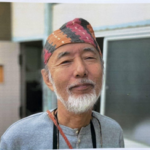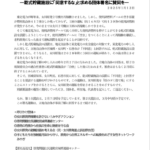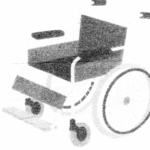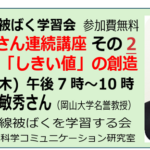市民と労働者による患者支援運動の始まり
1968(昭和43)年1月、新潟水俣病の患者(被災者の会)や支援組織(民水対)が水俣を訪問することを契機に、水俣では市民による初めての患者支援組織である「水俣病市民(対策)会議」が誕生した。水俣市で水俣病に関して市民が目立った動きを見せるのは、1959(昭和34)年以来のことであった。同会議は、政府に対して水俣病を公害として認定するよう働きかけた。
一方、新日窒による執拗な切り崩しや転属に耐え、新日窒労組第一組合は存続していた。そして、同組合は同年8月30日、それまで市民として、水俣病と闘ってこなかったことを人間として、またチッソ原因工場の労働者として「恥」であるとする宣言と謝罪を行った(「恥宣言」)。
チッソ(1965年より社名はチッソとなった)は、補償問題の再燃と、闘争的な第一労組が患者と結びついたことに非常な危機感を抱いていた。チッソは、1967(昭和42)年8月に発表した、合理化を推進して水俣工場を縮小し従業員をさらに削減する「五カ年計画」を推進している最中だった。
3日後の8月29日、水俣市では、チッソと関係の深い商工会議所や医師会、観光協会、商店会などを発起人として「水俣市発展市民協議会」が結成された。チッソは橋本市政後援会をつくり、市長を味方に取り込んでいた。協議会は、チッソの「五カ年計画」を支持する決議を行った。(橋本彦七は中村止市長が健康上の理由で退陣し再選していた)
協議会は「患者の味方もする」という態度をとってみせた。橋本市長はチッソとともに患者の慰霊式を行うことを水俣病患者家庭互助会(以下、互助会)に持ちかけ、9月13日に水俣市公会堂で実施した。これは水俣市政が慰霊を政治利用する始まりであった。また互助会に対する切り崩し工作の始まりだった。会の幹部を温泉の歓楽街に接待するなどして懐柔していたのである。
公害認定と新たな補償を求める動き
政府は、1968(昭和43)年9月26日、ついに水俣病を公害病と認定した。
患者たちは新たな補償を求める運動を始め、1959(昭和34)年の「見舞金契約」を白紙とし、会社と交渉し、まとまらなければ第三者に斡旋を依頼し、それでも決まらなければ裁判を行うことを決定していた。
11月15日、チッソは、見舞金契約の再現を望み、寺本知事らの第三者機関に補償額の基準設定を依頼したいと発言したが、知事は「厚生省で示すべきだ」と拒否した。
そのとき佐藤栄作内閣で、厚生大臣は園田 直(すなお)。不知火海を挟んだ水俣の対岸、天草の一町田村(いっちょうだむら・下島南部で現在の河浦町)出身だった。現職厚生大臣として初めて水俣市を訪れたことや、公害認定を敢行したことで患者たちは大臣に期待していたところがあった。しかし、直後の11月30日、内閣改造によって園田厚生大臣は退任し、斎藤昇に替わった。互助会では、自主交渉で行こうという意見が多くなった。
12月19日、チッソは厚生省に、補償基準を示すか、そのための委員会を設置するよう申し入れた。チッソは互助会からも国に掛け合ってほしいと働きかけた。患者たちは、大臣が替わっても公害認定した国のことをまだ信頼していた。彼らは上京し、厚生省、通商産業省、経済企画庁、総理府に要請を行った。
白紙委任の要求と、互助会の分裂
1969(昭和44)年2月、厚生省が第三者機関を設置する意向を示した。しかし、厚生省は設置の条件として「委員人選の一任」と「結論に従う」という白紙委任の確約を互助会とチッソに求めてきた。つまり「斡旋」ではなく「仲裁」であった。チッソはすぐに確約書を提出した。
2月28日、既に懐柔されている互助会会長は確約書に捺印するよう患者たちに説得したが、すんでのところで市民会議のメンバーが駆けつけ「これを押してしまえばおしまいよ」と説得して止めた。
互助会は3月1日に改めて総会を開き、会長は確約書の押印を説得、しかし賛同は得られなかった。そこで「あっせん依頼書」に変更して提出することになった。だが厚生省は「確約書」でなければ第三者機関設置は困難と回答した。
4月5日、互助会会長は総会にて「確約書」の内容のままタイトルを「お願い書」にして提出することを提案したが、激論となり、業を煮やした会長は「お願い書に捺印したい者はついて来い、裁判したい者は勝手にやれ」と退席した。
こうして互助会は「一任派」と「自主交渉派」とに分裂した(のちの川本輝夫らの「自主交渉派」とは別もの)。その夜、互助会執行部はチッソや市役所職員と車で会員宅を回っていたという証言がある。かなりの数が切り崩され、互助会97世帯中「自主交渉派」として残ったのは34世帯だった。
4月10日、「一任派」は54通の確約書を厚生省に提出した。4月12日、「自主交渉派」はチッソに補償要求(一時金1,300万円、年金60万円)を申し入れた。
4月15日、熊本市で本田啓吉(熊本第一高校教師)や渡辺京二(歴史家)ら30名によって「水俣病を告発する会」が結成された。このあと全国的に波及する患者支援運動の最初の一撃となる。
4月17日、「自主交渉派」の申し入れに対し、チッソは「第三者機関による解決を図るように申し入れたため補償要求には応えられない」と回答した。
4月20日、「自主交渉派」はチッソの回答を受けて、訴訟に踏み切ることを決定した。
4月25日、厚生省が設置した第三者機関である「水俣病補償処理委員会」が発足した。
ついに訴訟へ
5月8日、「自主交渉派」は集会を開き、訴訟提起を決定し、「訴訟派」となった。
5月18日、全国から弁護士222人が参加し、訴訟弁護団が結成された。県内弁護士が23人、県外弁護士が約200人だった。
そしてついに6月14日、29世帯112名がチッソを相手取り、総額6億4,000万円余の慰謝料を請求し、熊本地裁に提訴した。「今日ただいまから、私たちは国家権力に対して立ちむかうことになったのでございます。」原告代表渡辺栄蔵のあいさつは、被告は民間企業チッソであるにもかかわらず、国家への「仇討ち表明」となった。チッソが国家の傀儡に見えていたのである。
この裁判に負けたら水俣では生きてはいけないと彼らは考えていた。当時の地方の漁村集落で裁判を起こすということは、現代の我々の想像を超える覚悟が必要だった。
チッソ側の被告代理人はみな一流の弁護士だった。一方、原告側の弁護士は多くが名前のみの参加で、実行部隊は県内の20数名だった。
訴訟の主要な論点は、チッソの過失の有無であった。
チッソの主張と過失論争
1969(昭和44)年9月末、被告チッソの第一準備書面が提出された。チッソは、水銀が〈毒物及び劇物取締法〉に規定する毒物であることは認めるが、それは1964(昭和39)年に同法が改正された後のことである、と主張した。つまり、チッソは違法行為はなかったと主張したのである。
具体的には、以下の点を主張した。
- 1962(昭和37)年半ばまで、アセトアルデヒド製造工程中に塩化メチル水銀が生成するという事実は、理論上も分析技術上も予見し得なかった。
- メチル水銀化合物によって水俣病が起こるということも予見不可能だった。
- 水俣工場と同じ方法でアセトアルデヒドを製造してきた工場は他にも多数存在するが、かつて水俣病を発生したという例を見ない。
- 魚介類への移・蓄積を経て人に水俣病を発生させるという理論は、当時存在しなかった。
以上のことから、被告には過失がないという主張だった。これを覆し、裁判所を納得させるのは至難の業だった。まったく新たな過失論が必要だったのである。
組織した弁護団では太刀打ちできないことがわかり、熊本大学の研究者らに呼びかけ、9月7日、水俣病研究会が結成された。早くから患者を診察してきた原田正純や、工場をよく知る第一組合の労働者、法律学(富樫貞夫)や社会学(丸山定巳)の専門家、ほかに石牟礼道子(当時は文芸主婦と言われた)や宇井純(環境学者)が参加した。
法律学の富樫が新たな過失論を創出した。それは理論物理学者の武谷三男の考え方にあった。武谷は、核実験が人類に与える健康被害の考え方について、現時点では有害という証明がないから容認されるとするアメリカの多くの科学者の考えに対し、異を唱えていた。そこから、過失論について<危険の発生を予見すべき注意義務>の怠りという点に過失の焦点を絞っていった。
訴状の準備中、チッソは水俣病に関わる資料の焼却をしようとした。それを頼まれた職員がたまたま第一組合の職員だったため、焼却せずに極秘で持ち出され、訴状作りに寄与した。
公害の法整備と救済法設立の流れ
ここで時間を遡って公害関連の法整備を整理しておこう。
1960年代後半になると、日本各地に公害が社会問題として顕在化した。国は対策を講じ始め、1963(昭和38)年、四日市の大気汚染に対応する形で、厚生省と通商産業省が工業技術院の黒川真武を団長とする黒川調査団を編成し、現地調査を行った。
これは、当時計画していた巨大石油化学コンビナート(三島市・清水町・沼津市にまたがり、四日市を上回る規模)について、地元住民の公害への心配を払拭するためのものであった。
1964(昭和39)年、三島・沼津のコンビナート建設問題調査が行われ「事前に措置を講じれば公害は防除できる」との結論を出した。しかし、地元の反対は強く、かつてない規模の反対運動が展開された。公害発生のおそれのある企業の誘致に反対することによって、公害を事前に防止しようとする日本で最初の住民運動であった。そして、1965(昭和40)年10月27日、計画は撤回された。
1965(昭和40)年に公害審議会が設置され、1966(昭和41)年10月に「公害に関する基本施策について」の答申が実施された。
1967(昭和42)年には〈公害対策基本法〉が成立した。それまでは、それぞれの公害(例えば水質汚濁や大気汚染)に対して個別に対応していたが、この法律は、まず公害とは何かを定義し、各行政機関、事業者の責務を規定した。また、政府に環境基準を定める権限を与えた。以降、この法律は総合的な対策を推進するための法的根拠となった。
これにより、1968(昭和43)年5月8日にイタイイタイ病が、同9月26日には熊本・新潟両水俣病が公害認定をされた。
公害対策基本法には具体的な公害防止対策や被害者救済策は規定されていなかった。それで1969(昭和44)年12月15日には「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(「救済法」と略す)が制定と同時に公布された。これによって、公害認定を受けた被害者が公害病として救済されることになった。
認定申請と棄却、そして行政不服審査
1968(昭和43)年、水俣病が公害認定されたのを契機に、同年10月、死亡した患者7名、生存患者10名が認定申請を行った。生存患者のなかに川本輝夫がいた。彼は水俣病で精神病院(水俣保養院)に入れられ狂死した父のことも申請した。ところが、水俣病患者審査会は、死者は審査不可能だとして受け付けなかった。1969(昭和44)年5月29日、5名を認定し2名を保留、13名を棄却した。
「認定業務は民事上の補償問題と切り離して運用すること」を指示した〈厚生省事務次官通達〉が発せられていた。救済法を正しく運用していれば、全員すぐに認定されるはずだった。しかし、患者たちが認定されるとチッソに賠償責任を求めることが予想されたため、この通達の遵守は不徹底となり、このように棄却者が出た。認定に歯止めをかけないとチッソが危うくなる(=チッソを守らなくてはいけない)という意識は、認定審査会の医師たちにまで浸透していた。
しかし、かれらはここで強力な敵を作ってしまった。もしここで川本らを認定していたら、水俣病が歴史に刻んだ軌跡はずっと浅いものになっていただろう。
水俣病患者認定制度の変遷
最初に水俣病か否かを判断する組織は、水俣病が公式確認から約1カ月後の1956(昭和31)年5月28日に設置された水俣市奇病対策委員会であった。水俣保健所を中心に市衛生課・市立病院・医師会・新日窒附属病院で構成された。1957(昭和32)年2月19日、奇病調査研究会と改称した。
1959(昭和34)年12月30日に、「見舞金契約」を結ぶ直前の12月25日、補償対象=患者を認定する機構として、厚生省に水俣病患者診査協議会が設置された。熊本大学の教授、水俣市立病院院長、水俣市長、葦北郡医師会会長、熊本県衛生部長、水俣保健所所長、そして新日窒附属病院院長(細川一)の7名で構成された。これが、水俣病であるという診断(判断)権限が(医師ではなく)行政に掌握された瞬間であった。
1961(昭和36)年9月14日、水俣病患者診査協議会は解散し、熊本県衛生部所管の水俣病患者診査会となった。そのころ存在が明らかになった胎児性患者の診断を行うために委員は増員され、10名となった。1964(昭和39)年2月28日、水俣病患者審査会設置県条例が定められ、水俣病患者診査会は県知事所管の水俣病患者審査会になった。
1969(昭和44)年12月15日に交付された救済法、法の対象となる地域と疾病が指定され、熊本・新潟両水俣病は救済対象の公害として認められた。それを受けて熊本県は県知事の諮問機関として熊本県公害被害者認定審査会を設置し、1970(昭和45)年1月14日に発足した。認定権者である知事は、審査会の答申を受けて患者を認定する。
1974(昭和49)年8月10日、鹿児島県も独自に認定審査会を発足させた。それまでは熊本県が両県の患者の認定を行っていた。
1970(昭和45)年2月20日、認定審査会が開かれ、審査基準が決定された。驚くべきことに、それまで水俣病の審査認定基準は明文化されていなかった。この日初めて文書化されたが「マル秘」とされ、翌年に県議会で議員の質問によって初めて公開された。それには、水俣病と認定されるには「ハンター・ラッセル症候群」といわれる求心性視野狭窄、聴力障害、知覚障害、運動失調の4項目すべてに加え、疫学条件が揃わなくてはいけないという非常に厳しい条件だった(成人の場合)。ハンター・ラッセル症候群とは、1940(昭和15)年にイギリスで発生したメチル水銀中毒の労働災害事例に基づいたもので、水俣病とは発症経路が全く異なるものだった。
行政不服審査請求
川本輝夫は自身が棄却された衝撃に加え、申請させた患者が認定されなかったことに責任を重く感じた。だが、棄却という結果の取り消しを求め、審査請求の申し立てをする「行政不服審査」という方法があった。1962(昭和37)年に行政不服審査法が制定されていたのである。棄却された患者たちは、厚生大臣に対して不服を申し立てるということに恐れをなしたが、川本の説得で8名がそれに応じ、合計9名がそれを行った。1970(昭和45)年8月18日、それは厚生大臣に提出された。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔study1342:250202〕