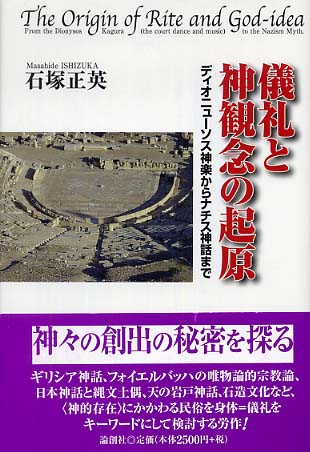歴史における神話のアクチュアリティ(1)
- 2012年 3月 17日
- スタディルーム
- ミュトスロゴス石塚正英神話
1 先史の神話あるいは神話の起源
2 ミュトスからロゴスへ、あるいは神話の非神話への転用
3 20世紀における近代化=合理化神話
4 20世紀神話のアクチュアリティ(1)――ファシズムとコミュニズム
5 20世紀神話のアクチュアリティ(2)――ファシズムと家族神話
*掲載は1~5を5回に分掲、注は最終回末尾に一括掲載
————————
1 先史の神話あるいは神話の起源
21世紀の現在、なぜ神話か? その疑問には本稿の全体をとおして答えるとして、前世紀の神話とくれば、なによりもまずナチスのイデオローグであったアルフレート・ローゼンベルクの著書『二〇世紀の神話』(1930年)を想起する(注1)。それほどに、20世紀の神話といえばファシズムやナチズム、それにソ連東欧の社会主義が思い浮かぶ。その際、通常使用される「神話」という語は、現実や史実にもとづくのでなく空想や虚構にもとづく物語、といった意味になる。この意味における用法としては、例えば次のように言える。イタリアやドイツ、ソ連の民衆に対してムッソリーニ、ヒトラー、スターリンの体制が客観的な根拠なしにでっち上げたナショナリズムやレイシャリズム(racialism)、コミュニズム(スターリニズム)は、20世紀神話の代表である。これらの体制が国民に提示する政策や利益は、あらかたフィクションである。
しかし、なんの根拠もない、事実無根の理論や政策に、はたして20世紀の文明諸国民が、そう易々と騙されるであろうか。なるほど、そう簡単には騙されるはずのない人々が騙されるが故に神話なのだ、そこにこそ神話の真の意味が潜んでいるのだ、としたい向きもあろう。だが、なぜ神話は、善悪のうち悪の方に成立しやすく、善については成立しにくいのか。善良な方、ないし好ましい方での使用例は、ないわけではない。例えばスポーツ競技では、連戦連勝の無敗神話、などと表現する。けれども、この場合の使用法でも、勝者はいずれ敗北する、つまりいいことは絶対に永続しない、という観念を下敷きにしている。かように、神話は悪ないし劣の価値意識にまつわる概念として定着している。けれども、神話の語義を先史地中海にみいだすと、この語はもともと相対的に善悪と関係なく生まれたことがわかる。あるいはまた、善とも悪とも関連していたということでもある。
本稿ではまず第一に、先史地中海における神話の語源や起源について議論し、第二に、くだって文明時代に派生した新たな神話概念の様々な領域への転用を検討する。そして第三に、20世紀における神話の中核として「近代化=合理化」および「家族」「ファシズム・コミュニズム・民主主義」を取り上げてみることとする。その上で、人権思想もまた神話形成の中核をなしていること、歴史上において神話は絶大なる現実有効性(アクチュアリティ)をい発揮している点を浮き彫りにしてみたい。
* *
神話学者の松村武雄は、古代ギリシアにおける「神話」という語について、著作『神話学原論』(1940年)で次のように説明している。
「古代ギリシア人は、『ミュトス』という語辞を最も本源的には『ロゴス(logos)』の意味に用いた。(中略)ホメロスのごときも、ミュトスをこの意味――すなわち『言葉』とか、『話されるあるもの』とか、『口によって発せられるあるもの』とかいうほどの義に用いている。muthosという語辞は、英語のmouth、 高古ドイツ語のMucke、ギリシア語のmuzo, muia, muo, mustesなどにおけると同じように、mu, (lat., mu)から抽出されたものであり、こうしてmuもしくはmuoは、『唇を開くこと、もしくは閉じることによって聴き得べき音を立てること』を意味した。然るに、より後代になると、その意味が特定化せられて、たんに『話されるあるもの』ではなくて、『神性的存在態について話されるあるもの』を詮表することになった。紀元前6世紀~5世紀の詩人ピンダロスの時代には、ミュトスは明らかにこの意味を獲得している。」(注2)
それからまた、ギリシア神話の研究者グリマルは次のように述べる。「ミュトスはロゴスに対立する。それは空想と理性、物語る言葉と論証する言葉との対立である。」(注3)
以上の議論を参考に、私なりに「神話(ミュトス)」という語についての定義を下してみたい。まず、あるがままの現象を語るのがミュトスである。例えば、ハトを見たらハトと意識しそのように語り記す。ミュトスの世界では、ハトを神とする人はハトそれ自体が端的に神である。それに対して、あるがままの現象に対してその意味や概念を語るのがロゴスである。例えば、ハトを見たら平和を意識しそのように語り記す。ロゴスの世界では、ハトを神とする人はその動物の背後か深部に真善美、正義や平和の本質を見抜く。ハトはそうした本質の眷属(使い・代理)である。ロゴスは明らかに反ミュトスなのである。
確立したギリシア神話の世界では、ミュトスは存在しないか、極度に衰退している。代わってロゴスが前面に出ている。例えば、のちにプラトンがイデアに関連づけることになる普遍の本質は、なんら具象性をもたず神的・不可視的なものとなっている。一方に、時間の静止する点としての世界(永遠の存在)=アイオン(永遠)とカオス(混沌)を想定し、他方に、時間が経過してできる線としての、森羅万象生成の世界(生成の系譜)=クロノス(時間)とガイア(空間)とを想定するならば、ギリシア神話の成立する現場は、アイオンとクロノスが交差している。過ぎ去っていくようでいていつしか元に戻り、円環を描く。一つの円環においては時系列が存在するものの、神話に登場する物語はア・トポス(時空を超えて偏在すること)を特徴とする。似たような物語は別の場所や別の時代に再演されて系譜(ゲネアロギー)をつくっている。ウラノスのゲノス→クロノスのゲノス→ゼウスのゲノス、と進む間に、神話には真善美、正義や平和といった意味=本質が付与され、一見すると具象的な展開の中に意味=本質が語り継がれるようになった。こうして、かつて先史野生のペラスゴイ人のもとでは具象のままの展開であったミュトスは、有史文明のギリシア人のもとでは抽象の展開するロゴスに変貌していったと言える。
ミュトスからロゴスへの転化の過渡期を生きたヘシオドスの『神統記』に関連させて、研究者パウラ・フィリップソンは次のように明言している。「その詩人にとっては夜の感覚されうる諸現象がとりもなおさず夜の意味であり、夜の作用であり、またそれに内在する規範でもあるのである。内と外は――ゲーテの表現を用いてよいなら――分離しているのではなく、夜の神的本質としてのもろもろの現象の総体となってあらわれているのである。なぜなら、現象の背後や上に神の存在があるのではなく、現象がすなわち神的存在、神の本質なのだからである。」(注4)
また、ギリシアの東方に存在したメソポタミヤ地方の先史神話「ギルガメシュ」に関連させて、研究者リヴガー・シェルフ・クルーガーは、次のように述べている。「原始的心性にとって、事物はまったく異なった意味をもつ。われわれが精神的あるいは物質的とよぶものは、彼らにとっては区別されていない。(中略)身体が魂であり、魂が身体である。身体に関わることがきわめて精神的であり、心に関わることがきわめて物質的なことがあある。」(注5)
ギリシアの神話世界はオリエントの神話世界と重なっている。例えばゼウスの妹デーメーテールは、最初エジプトか黒海のかなたかで崇拝されていた頃は、なによりもまず穀物の神であっただろう。接頭語の「デー」は、ガイアの語源「ゲー」と同じであり、大地を意味する。「デー」はまた、大地から芽吹く「穂」をも意味する。「メーテール」は「母(mater)」ないし「物質(materia)」を意味する。デーメーテールとは、ようするに大地母神、穀物の母神なのである。ここまでがミュトスである。それ以外のこと、たとえば誰それの子だとか誰それの妻だとかは、ロゴス=狡知の介入をみた結果をさらけ出している。ケレーニイは、無意識ながら、デーメーテールをクロノス・ゼウスと結びつけるのでなく、ペルセポネー(コーレー)と結びつけることによって、デーメーテールの中にミュトスを読みとっている。(注6)
ギリシア神話からヘブライ・キリスト教神話にうつろう。ヘーゲル学派のシュトラウスは『イエスの生涯』(1835~36年)の中で、聖書物語に結実することになる様々な口承や伝説はすぐれた個人の意識的な作為ではなく、民衆の精神、共同体の精神であり、その物語の舞台となっている民衆(共同体)や時代の産物であるとした。シュトラウスの言う神話とは、何らかの実生活を土台にして民衆の想像力が産み出したものなのである。(注7) その際、伝達の手段は文字でなく民衆が自ら発する言葉だった。また、信仰の対象は超然たる神霊ではなく、聖者の遺骨だった。古代においてキリスト教徒とは何か? それは、ブッダの遺骨=舎利を崇拝する仏教徒と同様、聖者の遺骨を崇拝する原初的信仰者のことなのである。キリスト教徒とは姿なき神イエスを崇拝する者という観念は、古代世界ではむろん中世カトリック世界でも実に不自然なものであった。とくに下層社会ではながくキリスト教が浸透する以前の神がみが信仰されていたし、キリスト教に改宗してからでも、それに土着の民間信仰をうまく適応させていた。遺骨信仰はその代表例である。
以上の議論や解釈を参考にミュトスとロゴスの関係を整理すると、次のようになる。われわれが常識として知っている神話はミュトスでなくロゴスである。では、前者から後者への展開すなわちロゴスの意味での神話の成立はどのようにしてすすんだか、その問題を次節で検討する。
出典:石塚正英『儀礼と神観念の起原』論創社、2005年、第7章
(Copyright©2012 ISHIZUKA Masahide All Rights Reserved.)
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔study458:120317〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。