「古代史への尽きぬ興味(2)-『日本書紀』が投げかける諸問題」
- 2017年 5月 14日
- カルチャー
- 合澤 清(ちきゅう座会員)
*遠山美都男著『天武天皇の企て 壬申の乱で解く日本書紀』(角川選書2014)
(遠山美都男著『天智と持統』(講談社現代新書2010)をも参照した)
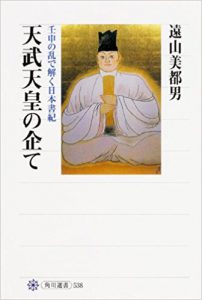 「壬申の乱」は天武の陰謀によって起きた
「壬申の乱」は天武の陰謀によって起きた
この本の最後の部分と「あとがき」で著者はこの著作の意図を次のように述べている。
「『日本書紀』というわが国最初の本格的な史書の骨格部分が、天武という紛れもない歴史の「勝者」によって企画・構想された、まさに「勝者の歴史」であったこと」
「『日本書紀』全体の構想が壬申紀を起点に組み立てられており、そして、その構想に古代中国の歴史の影響が濃厚であるのは、『日本書紀』を編纂した古代日本の律令制国家が、その手本とした中国と同質の世界帝国たることを目指した(あるいは物まねした)ことによると考えられる。『日本書紀』は、一般にいわれるように単純な意味での「万世一系」の天皇史を描いてはいなかった。」
『日本書紀』の編纂が時の権力を合理づける目的で行われたという見解は、おそらく古代史研究者のほとんどに共通するものであろう。ただ、それがどのような意味を持つのかに関しては様々に意見が分かれる。そして遠山の見解は「天武天皇の企て」という点にある。
つまり、遠山は、彼が研究の成果として得たある種の「仮説前提」=《『日本書紀』は(実際には皇位継承とは無縁であった)天武・持統による「皇位乗っ取りとその正当化」のために書かれたものであるということ》を『日本書紀』の当該箇所の丁寧な解読によって実証しようとしたのである。その要となるのが「壬申の乱」であり、『書紀』の中の「壬申紀」である。
当然ながら、この著書の圧倒的な分量が「壬申紀」の解読に当てられていて、本文が逐一引用され、解説が試みられている。また地名など、地理的な説明にも気が配られている。
そこで、前回の紹介と関連付けるために、少しお浚いをしながら、幾つかの点の再確認をしておきたいと思う。
『日本書紀』は天武10年(681)3月17日、川島皇子以下12名に詔して、「帝紀」と「上古諸事」を記定させ、中臣連大島と平群臣子首に筆録させたことをもって修史事業の始まりとされている。それが完成したのは養老4年(720)のことである。しかし、実際に書紀を撰述したのは、唐人の続守言と薩弘恪であり、両名は唐朝の正音(唐代北方音)に通暁し、最初の音博士を拝命していた。このことは前回紹介した森博達の論稿で詳しく説明されている。
ただ、このことに関して付け加えるなら、「壬申紀」を通じて、天武は絶えず漢の高祖(劉邦)になぞらえられている。それは、ただ単に天武の性格描写のみならず、出自(ライバルの項羽は名門の出であったが、劉邦は単なる庶民出でしかなかったこと、つまり天武には「そもそも皇位継承の資格がなかった」ことと同じ)や、劉邦と同じく「赤帝」の子と称し、自軍兵士の目印に赤い布を巻かせたこと、そして中国で易姓革命が起きたのと同様に、今や天命が革まるとき(革命=壬申の乱)がきたとの記述などに見られる。また、随所に散見する文にも、固有名詞を変えただけの古代中国の史書からの引き写しがある。こうしたことから、この撰述者が『史記』の高祖本記や『漢書』高帝紀などに関する深い知識をもっていたことがわかる。これらのことからも唐人の学者が編纂にあたって主要な役割を果たしたらしいことは十分あとづけられるように思う。もちろん、下図を描いたのは天武や持統らの一派であることは間違いない。
ここでお断りしたいのは、便宜上、天智、天武、持統などと天皇の中国風称号を使っているが、前回述べたように天武・持統の段階で初めて「天皇」という称号が用いられるようになったのであり、その意味では、諱(いみな=本名)を使うべきかもしれない。
天皇の称号が問題になった序に、次のことに触れておきたい。梅原猛は『水底の歌-柿本人麿論』の中で、前回引用した箇所に続いて次のように述べている。「(上山春平との共同研究で、次のような考えに至った…)天皇は、政治的概念であるより、宗教的概念であり、天皇はその発生の形態において、地上の国を支配するようにはできてはいず、歴史的偶然によって天皇の国家支配が行われた後も、天皇概念に含むそのような非政治性は、長く日本の天皇に付着しているのではないか。」(筆者の注:「天皇」号の成立時期をめぐって、欽明朝、推古朝、「大化改新」期、天智朝、天武・持統朝、「大宝律令」成立期などの諸学説があることを最近知った-森公章氏の研究)
再び本題に戻る。『日本書紀』の「壬申紀」は「壬申の乱」をどうとらえているのかといえば、「壬申の乱の「元凶」(「奸臣」また「君側の奸」)は、あくまで大友皇子をとりまく5人の重臣達、蘇我赤兄、中臣金、蘇我果安、巨勢人、紀大人」であり、大友皇子は彼らに担がれたにすぎないとされている。(遠山『天智と持統』)
つまり『日本書紀』の述べるところでは、天智が臨終に近く、枕辺に天武(天智の実弟)を呼び、自分の後を継ぐように言ったのに、天武はそれを断り、大友皇子にその母、伊賀采女(宅子娘、やかこのいらつめ)を後見人にして継がせるよう勧め、自分は出家して吉野へ隠棲するから許可を得たいと申し出る。天智はそれを承諾したが、5人の重臣たちは吉野で天武を弑虐しようと企て、その準備にとりかかる。それ故彼はやむなく立ち上がったという筋書きである。
なんだか胡散臭さの残る話である。以下のような疑問がわいて来る。この話は、『史記』列伝中の「伯夷と叔斉」の例にならって、兄弟同士互いに地位を譲りあったという美談なのか?そして地位を辞退した天武をきわめて「信義に熱い高潔な士」として描こうとしたのであろうか?それとも、①天智は天武の野心を試したのか、②もし天武が素直に引き受けていたらどうなっただろうか、③大友皇子はどういう立場だったのだろうか、またその実権はどの程度だったのか、④5人の重臣たちはどれほどの力をもっていたのだろうか、またなぜ、天武に反対して大友皇子を担いだのか、天智の意思を忖度したからか、⑤天武に最初から野心があったとすれば、いったん吉野へ引くことで、政権奪取のための準備が可能と判断するいかなる根拠があったのだろうか、⑥なぜ、天武は時の政権に対抗しうるだけの兵力を短期間(「壬申の乱」は高々1~2か月間でしかなかった)に集めることができたのだろうか、等々。
遠山の大胆な仮説では、実際には天武の敵は大友皇子(彼を排除して天皇位を奪取すること)であり、5人の「奸臣」云々は取ってつけたにすぎない。「天皇位」の正統な継承権は大友側にあるのであり、天武は傍系というよりも「ほとんど継承権はなかった」(この時代には同母から生まれた弟には継承権はなかった)というのである。「天皇位簒奪」という悪逆非道さをカムフラージュするために苦心して作文されたのがこの史書だったというわけである。もちろん、『紀』編纂には、それまでの「大王」(オオキミ)から「天皇」という絶対的な支配者(大神により指名された特別な一家族による累代の継承)体制へと移行するための伝承づくりが目論まれていること、これが中国式の律令制施行による中央集権化、それによる権力機構の強化と並行して進められたことが重要である。
「『日本書紀』は、天武天皇と持統天皇による大友皇子殺害という犯行を隠蔽し、正当化するために、まずは天智天皇が「天命開別」すなわち「中国的な王朝の始祖」であったとした。天智天皇に始まる王朝という構想をその基底に導入することにしたわけである。その上でこの王朝が、実際に中国においてもしばしばみられたように、奸臣たちの台頭によって滅亡の危機に瀕していたことにした。そして、天智天皇没後、天武天皇と持統天皇が敢然と立ちあがったのは、あくまで王朝を蚕食する奸臣たちを掃討し、天智天皇の王朝の正義と秩序を回復するためであったとしたのである。」(遠山『天智と持統』)
様々な疑問と異説を検討する-古代史の謎解きの面白さ
遠山のこの書では触れられていないが、大友皇子は実際には近江朝に即位して「弘文天皇」と尊号されていたといわれる(誰が、いつこのように尊号したのか?)。大友皇子=「弘文天皇」とすれば、歴史上、天武の仕掛けたこの乱は、時の天皇への反逆に他ならず、天武は「逆臣」ということになる。逆臣によってつくられた「万世一系の天皇史」である。そうでないとすれば、まだせいぜい畿内の王にすぎなかった二人による「大王(=天皇)」位を狙っての権力闘争であった、とも解することができる。
実際に考古学者の森浩一は、この乱を「大友皇子と天武による」内輪もめ(内訌)という様に読んでいる。
しかし、先述した梅原猛・上山春平説では、政治を(大王に代わって)代行するのは太政官(それゆえ、その肥大化が進んだ)であり、天皇は政治的役割の比重が比較的軽い君主であった、という。こうなると、壬申の乱も、その後の様々な政治的な改革なども、誰かが天武・持統の背後でコントロールしていたのではないかと疑うこともあながち的外れとはいえなくなる。
ここで少し過去に遡りながら、この時代の社会状況に目を遣りたいと思う。
天武・持統によって捏造された『日本書紀』を読めば、そこでの天智への、また「大化改新」への扱い、崇敬が特別なものであることがわかる(先にも見たが、天智を「天命開別」と持ち上げ、王朝の始祖とするなど)。なるほど実際に「大化改新」なる革命が天智(中大兄皇子)と中臣(藤原)鎌足らによって実行されたのであれば、それも当然だと思われる。
しかし、このことに対しても異論が多々見受けられる。まず、ほとんどの古代史家は645年の変に対して、これを「大化改新」とは呼ばない。干支の年号をとって「乙巳(いつし)の変」と呼んでいる。なぜなら、「大化改新」は、天智によって行われたのではなく、孝徳の下で行われたからという。「孝徳は、俗に「大化の改新」といわれる政策を発布し、実行に移した。」(森浩一『敗者の古代史』)
遠山によれば、「乙巳の変とは、『日本書紀』の描くような「王政復古」などではなく、実態としては史上最初の王位の生前譲渡を目指した政変だったと考えられる。そのように見るならば、この政変を断行したのは、政変の結果王位と王権を掌中にした孝徳や、彼を支援する立場にあった蘇我倉山田石川麻呂らであったと言えよう…若き日の天智は、この功績によって、孝徳政権で、王権の軍事部門を統括する役割が与えられていたのではないか。」(遠山『大化改新』中公新書)
実際に、「この政変を契機に史上初の譲位が実現し、皇極天皇(天智の母)の譲りを受けて孝徳天皇(天智の叔父)が即位している」。そして天智らが蘇我入鹿を、また蝦夷の暗殺を実行したことまでは事実であるというのが今日までの大方の意見であるが、実はこの件に関しても、「天智は入鹿を殺していない-現場にいなかった」(中村修也『偽りの大化改新』(講談社新書2006)という説が出されている。
ここで遠山が「孝徳と蘇我倉山田石川麻呂」らが背後で糸を引いていたのではないか、と述べている点については若干の異論があるのだが、そのことは後述する。
私自身はこの問題にはわりにオーソドックスな見方をしている。森浩一の次の記述などを参考にして考えたい。まず、「乙巳の変」が起きた日は、大陸からの大事な使者を迎えた当日であり、宮廷は厳粛な雰囲気に包まれていたものと思われる。事件は使者と皇極が大極殿で謁見中に起きている。
「皇極4年(645)6月、飛鳥板葺宮で三韓の使者を迎え天皇みずからも臨席する国家行事があった際、中大兄の発案で、入鹿が殺され、蝦夷は自宅で自害した」
これは使者と皇極、および居並ぶ重臣に対する大変無礼な、許しがたい振る舞いであるはずだ。ところが、「「乙巳の変」に対して皇極は中大兄の罪を問うことなく」済ませている。これはなぜか?自分の息子で皇位継承者だからか?しかしことは国際問題である。
「中大兄皇子は舒明天皇を父とし、天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ、後の皇極/斉明天皇)を母とする。」
ここで、遠山により「政変を断行した」と言われる孝徳とはどういう人物か、見てみる。森浩一によれば、「孝徳は能力あるものの抜擢に努め、政権を固めたときに、中大兄を皇太子、阿倍内摩呂(倉梯麻呂)を左大臣、蘇我倉山田石川麻呂を右大臣、中臣鎌子(鎌足)を内大臣に据えた。孝徳は内政外交面で大変優れていた。」
その孝徳に対して中大兄がとった態度は、「孝徳天皇は中大兄皇子らと厳しく対立したため、飛鳥京に残った中大兄らは、孝徳を(新しく造った)難波宮に置き去りにして憤死させた(といわれる)。(その後、「過渡的に」皇極が重祚して斉明天皇となったのだが、)また、孝徳天皇の皇子である有馬も斉明4年(658)に、斉明や中大兄皇子への謀反の罪で19歳で処刑され」てしまう。
中大兄の放縦で乱暴すぎる性格に対し、孝徳は「賢帝」と見なすべきではないだろうか。遠山のように孝徳が中大兄らを政治陰謀の駒に使ったとは考えにくい。むしろ中大兄の側にこそ、陰謀家の匂いが強いとしか思えない。
その後、中大兄は663年に白村江へ出兵して(「ヤマト・百済連合」対「唐・新羅連合」の間の海戦)、大敗するのである。その上、敗戦後僅か4年しかたっていないのに、近江の大津宮へと遷都し、翌年(668)ここで即位したといわれる。遷都の理由は、「唐・新羅連合軍」が、余勢をかって日本まで攻め寄せてくることを心配し、「対馬、筑紫、長門、讃岐、河内とヤマトの境の高安山などに百済式の山城を築き山と防御の姿勢を示した。それでも不安で、その4年後に都を近江に遷した」という。
遷都に次ぐ遷都、海外への派兵と敗戦、防御砦の建築など、恐らく庶民は困憊しつくしていたものであろう。その結果、多くの庶民は「公然と近江遷都に反対した」といわれる。つまり人心(民心)は、とっくに中大兄から離反している。こういう皇子がどうして天皇位を継承できたのだろうか、疑問だ。ここで非常に興味深いことを森浩一が書いている。
「大化という元号は『紀』では使っているが、金石文など同時代史料ではまだ証明されていない。孝徳の政治の大きさに7~8世紀の人が感心して大化の元号を追贈したとかんがえられる。」
この意味は大きいと思う。中大兄は実際に天皇位を継いだのであろうか、という疑念が湧く。「三韓の使者を迎え」た式場での乱暴狼藉、孝徳天皇への無礼な働き、有馬皇子を陥れ自殺に追い込んだこと、そして白村江海戦での大敗北。これではかばいきれないのではないだろうか。
天武の吉野隠棲から「壬申の乱」に至る謎はむしろこの辺りにあるのではないだろうか(と、私のような素人の古代史探索者は推論するわけである)。
少々長くなったので、今回はここまででいったん擱筆する。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔culture0478:170514〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。


