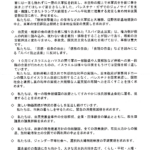≪西欧における権力の大形式、権力の大よそのエコノミーを、次のように再編成することができるかもしれない。まず、封建的タイプの領土性において誕生し、概ね掟の社会―慣習法と成文法―に対応し、約束と争いのゲームを繰り広げる、裁判
本文を読む書評の執筆一覧
書評 『叛逆』 アントニオ・ネグリ マイケル・ハート著
著者: 宮内広利≪ヘーゲルにおける<他者>のドラマおよび、主人と奴隷のあいだの抗争は、ヨーロッパの拡大とアフリカ、アメリカ、アジアの民衆の奴隷化という歴史をその背景とすることによってのみ生じたものなのだ。言葉を換えるなら、ヘーゲル哲学の
本文を読む【書評】『狼と香辛料』~中世ヨーロッパ商人の時代小説
著者: 木村洋平『狼と香辛料』は、ファンタジー世界を舞台にしたライトノベルで、2006年の第1巻は著者のデビュー作でもある。全17巻で完結し、シリーズ累計400万部を売り上げている。 今回は、第1巻から第5巻までを面白く読んだ。テレビア
本文を読む原爆の怖さと被爆体験を語り尽くす -[書評]中沢啓治著『はだしのゲン わたしの遺書』(朝日学生新聞社、¥1300円+税)-
著者: 岩垂 弘原爆による被害は言語に尽くしがたいほど悲惨。核爆弾の使用はもう絶対に許してはならない――中沢啓治著『はだしのゲン わたしの遺書』(朝日学生新聞社刊)を読み終え、改めてそう痛感した。広島・長崎の被爆から67年余。この本は
本文を読む書評 『国家と革命』レーニン著
著者: 宮内広利かつてわたしたちは、「プロレタリア独裁」という直截な歯切れの良さに心酔していた時期があった。当然のように言葉を包む暴力の予感も抑圧の危険さも知っていたはずなのだが、なぜか革命に対する片思いの時期を思い出しても、どのよう
本文を読む書評、ロナルド・ドーア著『日本の転機—米中の狭間でどう生き残るか』(ちくま新書、2012年11月)
著者: 矢吹晋碩学ドーアさんの新著を紹介したい。北京から一時帰国した友人がいきなり、ヤブキ先生の本をドーアさんが引用していましたよ、と語りかけた。まさか、そんな話は間違いに決まってるよ、とまぜかえしたところ、鞄から『日本の転機』を取り
本文を読む書評:「猥雑な」イエス伝―小嵐九八郎著『天のお父っと、なぜに見捨てる』
著者: 山川哲「猥雑」という言葉の本来の意味は「入り混じる」ということだが、この本はあえてそのような視座をとりこんでいるようだ。そして、世間一般に流布している「イエス伝」(新約聖書の世界)を大胆に書き換えて独自に物語化している。もっと
本文を読む新自由主義を考える人の必読書 ―経済生活にもある大量虐殺― 書評 中山智香子著『経済ジェノサイド―フリードマンと世界経済の半世紀』(平凡社)
著者: 半澤健市《三つの観点からフリードマンをみる》 本書はミルトン・フリードマンを教祖とする新自由主義批判の書である。 見事な出来映えである。気鋭の論客である著者・中山智香子(なかやまちかこ)は1964年生まれ、早稲田大とウィーン大の
本文を読む【書評】開沼博『フクシマの正義』を読んで
著者: 木村洋平はじめに ーー開沼博さんのご紹介 福島でいま、なにが起こっているのか。関心をもつひとに、信頼できる研究者が語る。開沼博(1984~)さんは、若手の社会学者で、福島県いわき市に生まれ、震災よりも以前から、すでに地元福島の原
本文を読む『研究不正と国立大学法人化の影-東北大学再生への提言と前総長の罪』の書評
著者: 希望「研究不正と国立大学法人化の影-東北大学再生への提言と前総長の罪」(日野ら)の第三章を中心に論ずる。当該部分は井上明久東北大学前総長の研究不正と二重投稿の一部に対する東北大学調査検討委員会及び日本金属学会の不適切な対応に
本文を読む昭和16年12月8日 -『日本人の「戦争」』と「日本浪漫派 Made in USA」-
著者: 半澤健市「昭和16年12月8日」というタイトルで書くのは三度目である。 今年は、太平洋戦争の意味を問い続けた著作を読んだ。タイトルは『日本人の「戦争」―古典と死生の間で』。著者河原宏(かわはら・ひろし、1928~2012)は長く
本文を読む『風力発電が世界を救う』を読んで -エネルギー新時代とチャレンジ精神-
著者: 安原和雄原子力発電が魅力も存在価値も失ったいま、頼りにすべきは、もはや再生可能エネルギー、すなわち風力、太陽光、小規模水力による発電、さらに農林畜産業の廃棄物によるバイオマス発電などである。なかでも著作『風力発電が世界を救う』
本文を読む2030年 中国はどうなる
著者: 阿部治平――八ヶ岳山麓から(52)―― 胡鞍鋼など著『2030年 中国はこうなる』(科学出版社東京)を訳者丹藤佳紀さんから頂戴した。胡鞍鋼は21世紀初頭「西部大開発」のプランを提起した中国共産党中央のブレーン、有数の経済学者であ
本文を読む『縮小社会への道』が訴えること -いのち尊重、脱原発、脱経済成長を-
著者: 安原和雄経済は常に拡大・発展していくものだと思い込んでいる政・財界人や経済学者たちからみれば、21世紀は経済が縮小していくほかない時代だという問題提起は驚愕に値するかも知れない。しかし考えてみれば人間の一生も同じではないか。成長
本文を読む賢治作品の魅力は「くり返し」と「二面性」 -川村光夫著『宮沢賢治の劇世界』を読む-
著者: 岩垂 弘宮沢賢治ブームである。昭和初期の東北冷害に際し賢治が農民たちに献身的に奉仕したことが、東日本大震災を機に改めて多くの人々の関心を引いているからだろう。それに応えて賢治に関する情報を発信しようと、賢治の出身地の岩手県花巻
本文を読む科学技術の進歩に解決を押しつけてはならない -書評:「縮小社会への道」-
著者: 川弾降雄本書は京都大学に2008年発足した、縮小社会研究会(HP:http://vibration.jp/shrink/)の活動経過報告である。著者から「216頁まで絞り込んだが、それでも予定枚数をオーバーしてしまった」とのお
本文を読むレアメタルも毒性を持っている -書評「重金属のはなし」-
著者: 川弾降雄金属の代表的な特徴の中でも、・伸展性に富む(変形や加工しやすい)こと、・熱と電気の良導体であること、が身の回りの生活で金属製品が使われる大きな理由である。これらに・採取しやすいこと、・高価でないこと、・強さを持つこと、
本文を読む書評 小林敏明『<死の欲動>を読む』
著者: 宇波彰ジャック・ラカンが1964年に行なった『セミネールXI 精神分析の四基本概念 』は、彼のセミネールのなかでも特に重要視されている。(2010年にベルギーのラカン研究者クリスチァン・フィーレンスは、このセミネールについて
本文を読むジャパメリカからチャイメリカへ?
著者: 加藤哲郎昨年三・一一以来、日本における原子力発電の歴史を調べてみると、一九八〇年代後半から九〇年代初めが大きな転機であった。ソ連のチェルノブイリ原発事故から「グラースノスチ」=情報公開が認められ、東欧革命・冷戦崩壊・ソ連解体に至
本文を読む橋下徹言説に対する徹底批判 書評 -森田実著『「橋下徹」ニヒリズムの研究』(東洋経済新報社)-
著者: 半澤健市本書は森田実(もりた・みのる)による橋下徹(はしもと・とおる)論である。 一方は40年のキャリアをもつ政治評論家。一方は次代リーダー候補として注目されている若手政治家。勝負の結末はどうなるのか。 《『橋下語録』を繰り返し
本文を読むテクノクラートによる「対米従属」史 -書評 孫崎 享著『戦後史の正体 1945-2012』(創元社)-
著者: 半澤健市本書は読者にショックを与える本である。どんなショックか。対米従属外交の実態をキャリア外交官が暴露するショックである。著者は「はじめに」にこう書いている。 「この本は、かなり変わった本かもしれません。というのも本書は、こ
本文を読む過剰な詠嘆と希薄な歴史認識 ―書評 三枝昂之著『昭和短歌の精神史』(角川ソフィア文庫)―
著者: 半澤健市著者三枝昂之(さいぐさ・たかゆき、1944年~)は早大卒、歌人。歌集のほか評論も多数。本書は第56回(2006年)芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した原著の文庫化。 《「短歌の精神」への興味》 私は短歌に無知である。日刊紙
本文を読む書評 村上隆夫著『仮説法の倫理学』
著者: 犬伴 歩倫理学はその本来の役割を果たしてきたのだろうか。高度経済成長以降のこの数十年を見ても、沖縄をめぐる問題、ベトナム戦争との関わり、公害問題、社会格差と貧困、原発事故が代表事例である利便と安全との関係など、倫理学が発信すべ
本文を読む書評 ディディ=ユベルマン、小野康男、三小田祥久訳 『時間の前で』(法政大学出版局、2012年)
著者: 宇波彰先に私はディディ=ユベルマンの『イメージの前で』の書評をこのブログに載せたが(2012年4月4日)、その原書は、1990年つまり著者37歳の時に刊行されたものであった。今回訳出された『時間の前で』の原書は、その10年後
本文を読む中国に急所を握られたアメリカ -書評 矢吹晋著『チャイメリカ―米中結託と日本の進路』(花伝社) -
著者: 半澤健市「チャイメリカChimerica」とは「チャイナ+アメリカ」のことである。 ふざけた印象を与える単語だ。しかし実態はふざけたものではない。それを明快に説くのが本書である。 《経済史家の著作に語源》 この言葉の初出は、経済
本文を読む原爆と原発は人類の過ちである -全廃に向けて猶予は許されない!-
著者: 安原和雄「反原発」の運動や著作は最近増えてきた。このことは歓迎したいが、どこか物足りない印象も拭えない。なぜなのか。それは「原爆と原発」を一体として捉え、論じなければならないという視点が弱いからだろう。その点、最近の著作『原爆
本文を読む書評 ディディ=ユベルマン、江澤健一郎訳『イメージの前で』(法政大学出版局、2012年)
著者: 宇波彰ディディ=ユベルマンは、1953年生まれのフランスの美術批評家である。1990年に刊行された本書は、著者の若い活力を感じさせる力作である。なぜ力作といえるのか。それはディディ=ユベルマンが、美術史もしくは美術批評におけ
本文を読む生活者と一緒にロマンを語り、夢を語れ -[書評]中澤満正著『これから生協はどうなる――私にとってのパルシステム――』(社会評論社、¥1800円+税) -
著者: 岩垂 弘今年2012年は、国連が設定した「国際協同組合年」。世界各国の政府と国民が協同組合について理解を深め、協同組合をさらに発展させるために1年間かけて努力しようとの狙いから設けられた「国際年」である。そんな折り、協同組合の
本文を読む成田史学史の特色を発揮した力作 -書評 成田龍一著『近現代日本史と歴史学』(中公新書)-
著者: 半澤健市《サラリーマンと学者の認識ギャップ》 私は金融マンの定年退職後に大学院で日本近代史を学んだ。 だからサラリーマンの「歴史観」をよく知っているし、アカデミズムの「歴史認識」も少しは知っているつもりである。二つのグループの
本文を読む「まだ絶望を語る時ではない」 -書評 山口二郎著『政権交代とは何だったのか』(岩波新書)-
著者: 半澤健市《民主党応援団による失敗の総括》 民主党応援団を自認する政治学者山口二郎による「政権交代」とその「失敗」の物語である。著者は1993年以来、中道左派政党による政権交代の実現を望みながら研究を続け、実践にもコミットしてき
本文を読む