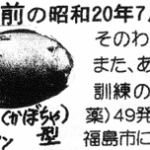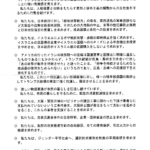*だれでも。いつからでも聴講できる思想史講座です。 *思想史講座語塾―「未完のナショナリズムー津田左右吉『我が国民思想の研究』を読む *「未完のナショナリズム」というタイトルで始めました。この講座では津田左右吉の『文
本文を読む青山森人の東チモールだより 第340号(2017年1月28日)
著者: 青山森人生涯年金制度の見直し案は大統領府へ 訂正 前号「東チモールだより」(第339号)で、2017年度の一般国家予算額約13憶9000万ドルを、「ポルトガルの通信社『ルザ』の報道によれば(2016年10月14日)、これは201
本文を読む「ヘイト・デマ ニュース番組」の元凶・DHCとの闘いにさらなるご支援をー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第99弾
著者: 澤藤統一郎よく晴れた、暖かい土曜日の午後。DHCスラップ訴訟勝利報告集会にご参集いただき、ありがとうございます。 本日講演いただいた田島泰彦先生、弁護団の皆さま、貴重な発言をいただいた皆さま、そしてこれまでのご支援をいただいた皆さ
本文を読むたんぽぽ舎から TMM:No2985
著者: たんぽぽ舎たんぽぽ舎です。【TMM:No2985】 2017年1月27日(金)地震と原発事故情報- 5つの情報をお知らせします 転送歓迎 ━━━━━━━ ★1.2度目の原発大事故(大惨事)発生が一番の心配 東電福島第一原発事故後6
本文を読む脱原発 台湾の次は韓国 韓国通信 NO515
著者: 小原 紘韓国通信 NO515 台湾の「脱原発」に祝杯をあげたい。一昨年台湾を訪れ、建設中止に追い込まれた第4原発を見学、現地市民たちと交流した。東日本大震災で多額の救援募金に取り組んだことはよく知られるが、同時に地震の多い台湾
本文を読む1.31 軍事研究推進制度に反対する緊急署名呼びかけ人による記者会見
著者: 杉原浩司今年度の18倍にのぼる110億円もの予算案が提出された軍事研究推進制度にどのような姿勢をとるべきか。日本学術会議の「安全保障と学術に関する検討委員会」での議論が佳境に差しかかっています。 1月16日に行われた委員会では、
本文を読む盛岡地裁「浜の一揆訴訟」 傍聴満席の法廷で
著者: 澤藤統一郎原告ら代理人の澤藤大河です。原告準備書面(5)の内容を要約して陳述いたします。 本準備書面は、次回から立証段階にはいる予定で、主張段階最後の準備書面として、原被告双方の主張を整理し、原告主張を補充する目的とするものです。
本文を読むトランプ大統領、公約にあくまで拘り、それが怖い
著者: 熊王信之近年の阪神・タイガース、如何にも阪神らしく弱いのでタイガースでは無くて、我が家の猫さん並みになってしまっています。 私は、いくら貶しても仕方が無いので、最近はメジャーリーグのデトロイト・タイガースの試合を観るようになりま
本文を読む福島反原発ツアー“割り勘=白タク”逮捕へのアピールへの賛同者を募っています
著者: 太田光征【至急】Fw: 福島反原発ツアー“割り勘=白タク”逮捕へのアピールへの賛同者を募っています 大畑です。 よろしくお願い致します。 賛同していただける方は以下までご連絡御願いします。 長内経男 携 帯:090-1267-1
本文を読むDHC吉田への逆風のさなかに「勝利報告集会」ー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第98弾
著者: 澤藤統一郎タイミングよく、DHCと吉田嘉明に対する世の批判の風が強く吹く中で、明後日(1月26日・土曜日)の午後、「DHCスラップ訴訟勝利報告集会」が行われる。 その集会の目玉は二つある。 一つ目は、田島泰彦上智大学教授(メディア
本文を読む1・28第92回社会的企業研究会のご案内 ≪地域における「一人親家族の就労支援」を考える~大阪豊中市庄内「カフェぐるり」「銀座食堂」の経験を通じて~≫
著者: 藤井敦史2016年は「子ども食堂」が社会的にも大きな関心を呼びました。それに関連して、一人親家族の問題も以前に比べて取り上げられるようになりました。「シングルマザーの3人に2人、高齢女性の2人に1人が貧困層、一人暮らしの女性の
本文を読む変革のアソシエ講座2016年度開講(2017年2月)
著者: 木畑壽信【註記:時間表示のないものは、すべて、19時から21時までの開講です。】 2月1日(水)【特別講座】「宇野弘蔵『経済原論』と現代世界」(伊藤誠) 2日(木)[13時30分~15時30分]「ジル・ドゥルーズ研究会」(横
本文を読む自転車エコライフ通信 154号
著者: 中瀬勝義新宿山ノ手七福神を巡りました。 https://chikyuza.net/wp-content/uploads/2017/01/523473b4396c0c744f6b877e9906a32a.pdf https://c
本文を読む日本政府の「平和の少女像」撤去圧力に抗議する官邸前アクション
著者: 植松青児2/1(水)18:30-19:30 首相官邸前(東京メトロ国会議事堂前駅3番出口) 呼びかけ;戦後70年ミニシンポ実行有志 メール;1945to2015@gmail.com、 twitterアカウント;@1945to20
本文を読むたんぽぽ舎から TMM:No2984
著者: たんぽぽ舎たんぽぽ舎です。【TMM:No2984】 2017年1月26日(木)地震と原発事故情報-3つの情報をお知らせします 転送歓迎 ━━━━━━━ ★1.1.22関電本店包囲全国集会の厳寒の中での熱気と“音海の大ダコ” 高浜町
本文を読むSJJA&WSJPO【西サハラ最新情報】196 モロッコが戻りたいカダフィのアフリカ連合
著者: 平田伊都子なんでアメリカはカダフィを殺したの? ナショナリスト<アメリカファースト>に対抗できるグローバリストは<アフリカ連帯>のリビアのカダフィだったのに、、 アメリカはCIAの捏造情報でイラクのサダムを殺し、アラブの春を扇動
本文を読む【要申込】セミナー:どこへ行く、原発輸出?~泥沼化する国際原子力産業の実態と各国の選択~
著者: 紅林進【要申込】セミナー:どこへ行く、原発輸出?~泥沼化する国際原子力産業の実態と 各国の選択~ http://www.foejapan.org/energy/export/170131.html ◆日 時:20
本文を読む領土・人民だけでなく、天皇が時まで支配する元号制
著者: 澤藤統一郎本夕、「日の丸・君が代」弁護団会議。処分取消・第4次訴訟の結審を間近に、最終準備書面の作成打ち合わせに忙しい。その席で、「被処分者の会」の共同代表である岩木俊一さんから興味深い文書をいただいた。 「平成元年3月8日」と日
本文を読む卑屈な日本、嵩にかかるトランプのアメリカ
著者: 合澤清「極端主義者」トランプは米国内ばかりでなく、世界中の世論を真っ二つに割りながら第45代米国大統領に就任した(1月20日)。直後の日本とEUの反応は、対米関係を象徴的に語るものである。 日本のメディアは、一応は米国内での反
本文を読むコミュニティの危険性
著者: 藤澤豊グローバリゼーションの弊害を軽減するためや、グローバリゼーションの行きすぎを押しとどめようという視点からコミュニティを重視した話を耳にする。そこには国境を越えて活動する資本になす術もなく取り残された住民としての危機感と素
本文を読むたんぽぽ舎から TMM:No2983
著者: たんぽぽ舎たんぽぽ舎です。【TMM:No2983】 2017年1月25日(水)地震と原発事故情報- 4つの情報をお知らせします 転送歓迎 ━━━━━━━ ★1.1/22高浜原発うごかすな!豪雨と厳寒・ビル嵐めげず1000人 大阪高
本文を読む「変えよう選挙制度の会」2月定例会「みんなで選挙市民審議会の中間答申を読んでみよう!」
著者: 紅林進「変えよう選挙制度の会」2月定例会 テーマ:みんなで選挙市民審議会の中間答申を読んでみよう! (解説と意見交換 田中久雄さん) ※「選挙市民審議会」については下記サイトを参照してください。 https://
本文を読む大分県立竹田高等学校剣道部熱中症致死事故について
著者: 安岡正義その事故は2009年8月22日に起こった。大分県立竹田高等学校剣道部主将、工藤剣太さん(当時2年生)が、顧問教員から、およそ「指導」の枠を超える執拗で理不尽な暴行を受け、重い熱中症のために命を落としたのである。 &nbs
本文を読むスパイにされた姉 戦時下カトリック弾圧―「共謀罪」の本質が見える
著者: 澤藤統一郎本日(1月24日)の衆議院本会議。代表質問で、志位共産党委員長が、今国会に提出予定とされる、共謀罪新設法案についてアベ首相を問いただした。正確には、組織犯罪処罰法の改正案。 既に「共謀罪」は手垢にまみれている。3度の廃案
本文を読む経済学の貧困と経済学者の劣化(4) - 労働力人口は成長の決定要因ではないのか―吉川洋著『人口と日本経済』を質す(続)
著者: 盛田常夫キャッチアップ過程における労働力価値の再評価 (前回に続いて、労働力人口と労働生産性についての吉川洋氏の考え方を検討する) もう1点、吉川氏の議論から完全に欠落している視点がある。それは高度成長期の非常に高いGDP成長率
本文を読む淡交会環境セミナーのご案内
著者: 中瀬勝義「ゆたかで楽しい海洋観光の国へ、ようこそ!」 日時: 2月25日(土) 15:30-17:30 所: 東京環境工科専門学校 講師: 中瀬勝義(海洋観光研究所) https://chikyuza.net/wp-conten
本文を読むウクライナ危機から3年:制裁解除は当然
著者: 塩原俊彦ウクライナ危機が表面化してから3年が経過する。日本では、ウクライナ危機への関心はすっかり薄れているように感じられる。しかし、ドナルド・トランプ米大統領の登場で、対ロ経済制裁の解除が俎上にあがっており、各国は過去の経済制裁
本文を読む経済学の貧困と経済学者の劣化(3) - 労働力人口は成長の決定要因ではないのか―吉川洋著『人口と日本経済』を質す
著者: 盛田常夫アベノヨイショの「エコノミスト」に共通するのは、政府の累積債務問題と将来の労働力人口減少問題を徹底的に軽視する姿勢である。なぜなら、アベノミクスは、「高い経済成長を復活させることによって、日本経済は再び黄金時代を迎える
本文を読むスラップを受任する弁護士の責任を問うー「DHCスラップ訴訟」を許さない・第97弾
著者: 澤藤統一郎DHC・吉田に対する反撃の訴訟に、共同不法行為者として、原告代理人として訴訟を担当した弁護士も被告にするかどうか。まだ結論に至っていない。考え方は、次のようなものだ。 専門家責任という成熟しつつある法律用語がある。専門家
本文を読む2/11【講演会】象徴天皇制の魅惑(茨城・つくば)
著者: 戦時下の現在を考える講座連続学習会・象徴天皇制を考える No.3 象徴天皇制の魅惑 退位? 元首化? 「国民の天皇」の現在を解く ・2月11日(土) 14:00-16:30 ・つくば市立春日交流センター 大会議室 (つくば市春日2-36-1、筑
本文を読む