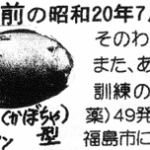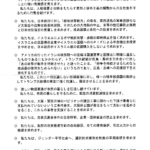https://chikyuza.net/wp-content/uploads/2018/05/d4f1263cf5a262457ad2b733d6ee4949.pdf
本文を読むなぜ、「浜の一揆」なのか
著者: 澤藤統一郎控訴理由書の冒頭に、原審での結審期日に、原審原告ら訴訟代理人(弁護士 澤藤大河)が口頭で述べた最終意見陳述を掲記しておきたい。事案の概要と、控訴人(原告)らの考え方が、よくまとめられているからである。 「原告ら訴訟復代理
本文を読む「国体」論による鮮烈な戦後批判 - 白井聡『国体論―菊と星条旗』を読む -
著者: 半澤健市気鋭の政治学者白井聡(しらい・さとし、1977~)の近著『国体論―菊と星条旗』は次のように始まる。(■から■) ■本書のテーマは「国体」である。この言葉・概念を基軸として、明治維新から現在に至るまでの近現代日本史を把握
本文を読むミュンヘンとワルシャワ、気まま旅(6)
著者: 内野 光子5月9日、午後からは、きのうのダッハウに続きKさんの案内で、市内をめぐった。この日の待ち合わせ場所のマリエン広場は、びっくりするほどの賑わいで、新市庁舎の前には、舞台が設置され、周辺で踊る人たちもいる。舞台には”euro
本文を読む「獣医大いいね・総理」の独白
著者: 澤藤統一郎昨日(5月22日)の朝刊各紙。いずれもトップに、「首相『獣医大学いいね』」の大見出しだった。2015年2月に、私が官邸に加計孝太郎を迎えて15分間面談し、学校法人「加計学園」の獣医学部新設の説明を受けて、「新しい獣医大学
本文を読む江東自転車エコライフ通信 167号
著者: 中瀬勝義江 東 区 の 花 め ぐ りを紹介します。 https://chikyuza.net/wp-content/uploads/2018/05/6806151fdbd133cee87fab8d66b70035.pdf 〈記
本文を読む【NAJAT講座】6/19「武器貿易条約(ATT)第4回締約国会議に向けて」
著者: 杉原浩司8月下旬に日本で武器貿易条約(ATT)第4回締約国会議が開催されるのを 機に、世界の武器貿易をどのように制限できるのかを考える講座を企画し ました。この会議に市民がどのように関わっていけるのかを探るガイダン スでもありま
本文を読むある時代の産物のひとつ
著者: 藤澤豊「四十にして迷わず」などと、よくもまあ臆面もなく言ったものだと思う。よほどの人なのだろうが、迷うほどには気がつかなければならないことに気がつかなかっただけではないのか。あまりにも知らなければならないことが多すぎて、四十ど
本文を読むリハビリ日記Ⅲ ①②
著者: 阿部浪子①孫育て 真夏日の午前、わたしはS病院のリハビリ室をたずねた。7か月ぶりだった。S病院は浜松市内にある、リハビリテーション専門の病院だ。脳内出血を発症してから1年2か月が経過していた。わたしは、S病院を退院してから介護
本文を読むBBCのシリア内戦まとめ(3) - この悲惨な戦いはいつ終わるのか -
著者: 坂井定雄シリア国民はどこへ逃れたのか(UNHCR=国連難民高等弁務官事務所による、2018年2月現在) ▼近隣諸国でのシリア難民登録数 トルコ 3,540,648 レバノン 995,512 ヨルダン 657、62
本文を読む「築地市場の行方」第二弾~築地を守り豊洲を生かす シンポジウム
著者: 紅林進昨年8月に開催され大きな反響を呼んだシンポジウム「築地市場の行方」の第二弾で す。 昨年末、小池都知事は、築地にある東京中央卸売市場を正式に豊洲へ移転することを 決定。開場日は2018年10月11日と発表しました。 しか
本文を読むミュンヘンとワルシャワ、気まま旅(5)
著者: 内野 光子5月9日、朝のキャンパス、英国庭園 この日は、午後から、Kさんに案内していただくことになっていて、午前中は、そのコースにはないミュンヘン大学と英国庭園へと出かけた。ミュンヘン大学(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学と呼ぶら
本文を読む緊急のご賛同お願い ― 「NHK大阪記者の不当異動人事中止を求める要望」
著者: 澤藤統一郎加計問題が愛媛県文書(「いいね文書」)の開示で新たな展開を見せている。森友問題についても、明日(5月23日)国有地値下げ交渉に関わる大量の新文書が提示される。アベ内閣は、既に詰んでいるはずなのだが、潔く投了という気配はな
本文を読む■維新と日本近代・2 なぜこの農村の国学者は常に遅れて発見されるのか ―鈴木雅之『撞賢木』を読む
著者: 子安宣邦「凡そ世(世界)になりとなる(生々)万物(人は更なり、禽獣虫魚にいたるまですべて有生のたぐひ、)尽く、皆道によりて生り出づ(道のことは下にいへり)。道ある故に、世にある万物は生り出たるものなり。」 鈴木雅之『撞賢木』総説
本文を読むお江戸舟遊び瓦版 585号
著者: 中瀬勝義江渡狄嶺「或る百姓の家」 萬生閣、大正14(1922)年11月 を紹介させて頂きます。 (右隅の黒枠をクリックすれば画像が拡大します) https://chikyuza.net/wp-content/uploads/20
本文を読むなぜ35万人以上が死亡、120万人が難民化したのか - BBCがまとめた「シリア内戦7年間」(2) -
著者: 坂井定雄内戦を戦った勢力 シリア政府の重要な支援者はロシアとイランであり、反政府勢力の主な支援者は米国、サウジアラビアとトルコだった。 以前からシリアに軍事基地をもっていたロシアは、2015年にアサド大統領を支援する空爆作戦を開
本文を読む破れ鍋に綴じ蓋
著者: 熊王信之昨年来のこの国を揺るがすモリもカケも、中央省庁キャリア組の官僚がアベ政権、就中、首相に「忖度」したのではないか、とは多くの方々が言われる処です。 しかし「忖度」してまかり間違えば自身に違法行為の謗りを受ける恐れのある行い
本文を読む「学習指導要領」の暴走を止めよう! (1) 新「高等学校学習指導要領」の根本的問題点
著者: 青木茂雄2018年3月に、前年の小中学校に続いて高等学校の新学習指導要領が改定「告示」された。教育基本法改悪以後、2度目の学習指導要領改定で、大改悪である。 今度の改定の特徴を一言で言い表せば、2006年の改悪教育基本法のねらい
本文を読む書き初めに勇ましい字が出ぬように(かうぞう)
著者: 澤藤統一郎一昨日(5月19日)毎日新聞「仲畑流万能川柳」の年間賞表彰式があった。 2017年の投稿59万句から選ばれた年間大賞は、 書き初めに勇ましい字が出ぬように 2017年1月1日に掲載された句。大阪府高槻市作野一男(柳名
本文を読む三菱電機から買わないで!6/9 秋葉原・ヨドバシAkiba前アピール
著者: 杉原浩司三菱電機不買のキックオフ会見(4月19日)、本社&タイ大使館への申し 入れ(4月23日)、憲法集会でのスピーチ(5月3日)などを行ってきまし たが、まだまだ不買運動は盛り上がっているとは言えません。 そこで、アキバの家電
本文を読む自らの植民地主義に向き合うこと―カナダから、沖縄へ:『ヘイト・クライムと植民地主義』(三一書房)から転載 Facing my own colonialism – from Canada to Okinawa: Satoko Oka Norimatsu
著者: ピースフィロソフィー今年1月に三一書房から刊行『ヘイト・クライムと植民地主義 反差別と自己決定権のために』(木村朗・前田朗共編)に書かせていただいた一章「自らの植民地主義に向き合うこと―カナダから、沖縄へ」(94-112頁)を、許可をいただ
本文を読むなぜ35万人以上が死亡、120万人が難民化したのか - BBCの分析「シリア内戦7年間」(1) -
著者: 坂井定雄七年前の2011年3月、「アラブの春」に励まされ、民主化を求めて大規模なデモが発生したシリア。アサド独裁政権が、軍と治安警察を総動員して過酷に弾圧。それが、シリア内戦の発端となり、軍の一部も反旗を翻して民主化勢力に加わり
本文を読む本間宗究(本間裕)の「ちきゅうブッタ斬り」(191)
著者: 本間宗究(本間裕)道に食あり、食により道を失う 最近の「官僚の不祥事」については、まさに、「食により道を失った状況」とも言えるようだが、このことは、「禅」の言葉である「道に食あり、食により道を失う」というものである。つまり、「道」という、
本文を読む【直前再掲載】5・26公開講座『こどもと若者たちの貧困問題をめぐって』 講師:橘ジュン(BONDプロジェクト代表)
著者: ちきゅう座運営委員会日時:2018年5月26日(土)15時~16時45分(14時45分開場) 会場:明治大学駿河台校舎研究棟・第1会議室(4F) BONDプロジェクトは2009年に創立。10代20代の生きづらさをかかえる女の子たちを支える活
本文を読む6.23シンポジウム「明治150年」に問う―沖縄と天皇制
著者: 深沢 一夫―東アジアの戦後が激しく変わろうとしている今 琉球列島の軍事植民地化と象徴天皇制批判の視座から 侵略と併合の「明治150年」を問う-6.23シンポジウムに多くの参加を! 日 時 6月23日(土)14時 会 場 専修大
本文を読む「9条俳句訴訟」東京高裁控訴審判決を傍聴して
著者: 石川愛子5月18日(金)、「9条俳句裁判」(詳細は「9条俳句市民応援団ホームページ」へ)の東京高裁での判決日。101法廷は傍聴人でいっぱいだった。2時からの裁判、2分間の報
本文を読む「アパートで暮らしたい・・・」-おにぎりパトロールでの出会いから-
著者: 村尾知恵子3月下旬、今年の桜は開花が早かった上、満開の桜を眺めている期間も例年より長かった。路上生活の人々もお花見に行っているのでしょうか。「こんにちは、ど~ですか」と挨拶を交わした人はいつもより少ないようでした。日中が暖かいせい
本文を読むミュンヘンとワルシャワ、気まま旅(4)
著者: 内野 光子5月8日5時、マリエン広場で ダッハウ強制収容所からマリエン広場に戻り、Kさんは別れ際に、ランチは青空市場でいかがですか、と勧めてくださった。それから「新市庁舎の仕掛け時計は5時ですよ」とも。マリエン広場の賑わいは、なる
本文を読むミュンヘンとワルシャワ、気まま旅(3)
著者: 内野 光子「見取り図」再掲 ゲオルク・エルザ―の独房に遭う 展示室③を出ると、1997年に設置されたという、ダッハウの犠牲者慰霊碑④が目に入る。高圧電流の通る有刺鉄線を越えようとして、命果てた人々を表現したという。 収容者の点呼が
本文を読むミュンヘンとワルシャワ、気まま旅(2)
著者: 内野光子5月8日、ダッハウ収容所へ、大勢の若い見学者たちに圧倒される 9時に中央駅構内のスタバでガイドのKさんと待ち合わせ、一日乗車券を手渡された。列車Sバーン2でErding行きと反対方向に乗ればよく、ダッハウ駅の先で二手に分
本文を読む